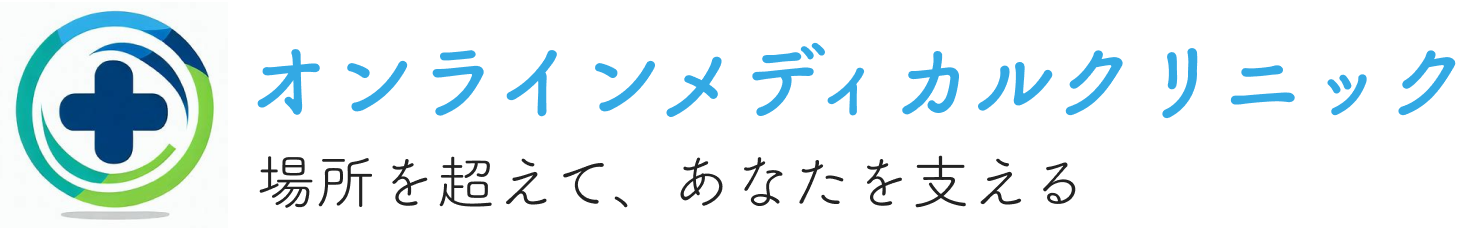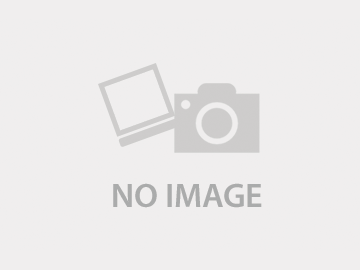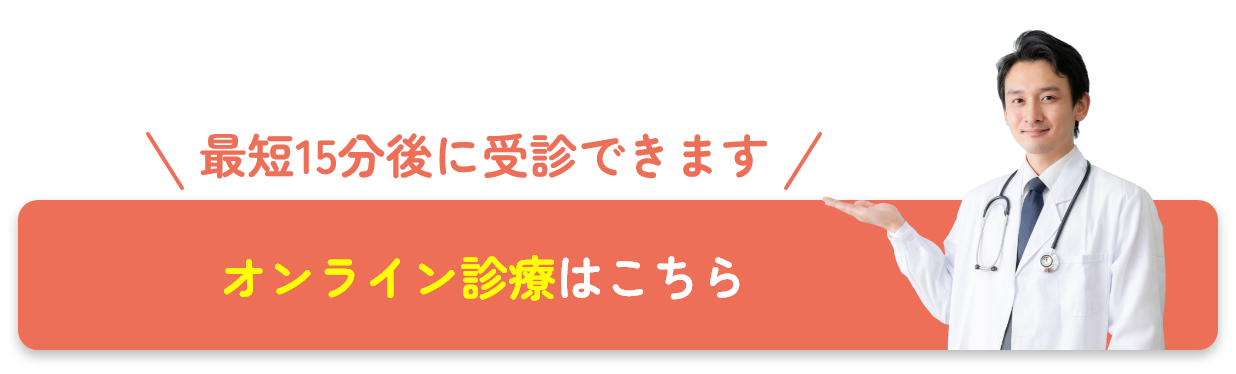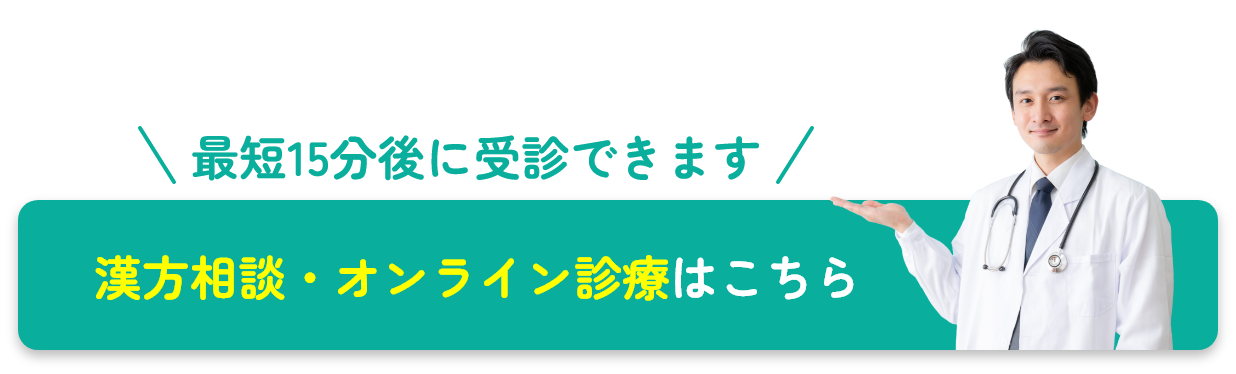食欲不振とは、お腹が空かず食べたい気持ちが起こらない状態を指します。
精神的なストレスや胃腸の機能低下など様々な原因で起こり、長引くと体力の消耗による疲れやすさや貧血を招き、健康状態がさらに悪化しかねません。
本記事では、食欲不振のタイプ別におすすめの漢方薬とその効果、正しい服用方法や生活改善策、そして症状が改善しない場合の受診の目安について解説します。
食欲不振のタイプ別おすすめ漢方

一口に食欲不振と言っても、その原因や体質によって症状の出方が異なります。
漢方では患者の「証(しょう)」に合わせて処方を選ぶため、同じ食欲不振でも人によって用いる漢方薬が違います。
ここでは、考えられるタイプ別に代表的な漢方薬をご紹介します。
胃腸が弱くて食べられないタイプ
もともと胃腸の働きが弱く、少量の食事でもすぐお腹がいっぱいになってしまうタイプです。
検査をしても異常がないのに胃もたれや食欲不振が続く場合、漢方では「脾胃の気(消化吸収エネルギー)の不足」が原因と考えます。
こうした胃腸虚弱の方には、六君子湯(りっくんしとう)という漢方薬がおすすめです。
六君子湯は8種の生薬からなり、弱った胃腸を元気づけて消化機能を高める処方です。
実際、六君子湯は消化管ホルモンの一種であるグレリンの分泌を促し、食欲を増進させる作用があることが分かっています。
機能性ディスペプシア(FD:胃もたれや早期満腹感など胃の機能低下による症状)に対しても、六君子湯は有効性が高い薬剤としてガイドラインで強く推奨されています。
ストレスで食欲が落ちるタイプ
緊張や不安など精神的ストレスが原因で、食欲が湧かなくなるタイプです。
強いストレス下では自律神経が乱れ、交感神経優位の状態になるため、消化管への血流が減って消化機能が抑えられ、空腹感や食欲が低下します。
またストレスホルモンの作用で脳の食欲中枢も抑制され、「食べたい」という信号自体が弱まってしまうのです。
このような神経性の食欲不振には、心の不安を和らげつつ胃腸を元気づける漢方処方が適しています。
例えば加味帰脾湯(かみきひとう)は、胃腸の働きを助けながら不足した血(けつ)を補い、不安感や落ち込みやすさを改善する処方です。
生薬の酸棗仁(さんそうにん)や遠志(おんじ)などが精神を安定させる効果を持ち、同時に人参や白朮・生姜といった健胃生薬が含まれているため、ストレスで消耗した心身を立て直し食欲を回復させるのに役立ちます。
ストレスで胃がキリキリしたり神経性胃炎の傾向がある場合には、半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)という処方もよく使われます。
半夏瀉心湯はみぞおちのつかえ感や吐き気を改善し、ストレスによる胃もたれや神経性胃炎の症状を和らげる効果があります。
体が冷えて消化力が落ちているタイプ
身体が冷えやすく、そのため消化吸収の力が低下しているタイプです。
冷たい飲食物をとると下痢しやすい、胃が重く感じる、といった傾向があります。
漢方では「脾陽虚(ひようきょ)」といって、消化機能を温めるエネルギーが不足している状態と考えられます。
このタイプには胃腸を温めて機能を高める人参湯(にんじんとう)がおすすめです。
人参湯はその名のとおり高麗人参を主薬とし、体を内側から温めながら胃腸の働きを改善する作用があります。
ベースとなっている四君子湯(しくんしとう)が消化吸収力を回復させ気力を補う処方で、それに含まれる生姜をより強力な乾姜(生姜を乾燥・炮熱したもの)に変えて温める力を高めたのが人参湯です。
体の冷えによる食欲不振や下痢傾向に効果的で、「冷え性で胃腸の調子が悪い」という方の食欲改善に用いられます。
なお、お腹が冷えて下痢しやすい急性胃腸炎のような場合には、胃苓湯(いれいとう)という処方も用いられます。
胃苓湯は胃腸の水分バランスを整えて下痢や嘔吐を止める働きがあり、冷たいものによる下痢や食あたりなどに対応します。
症状に応じて、温めるだけでなく余分な水分をさばく処方も検討されます。
胃もたれ・吐き気があるタイプ
食欲はないばかりか、食べるとすぐ胃がもたれて吐き気がするようなタイプです。
胃の中に食べ物が停滞しやすく、ゲップや胃の不快感を伴うこともあります。
原因によって処方の選択が異なりますが、胃のつかえを解消し吐き気を抑える漢方薬が有効です。
代表的なのは前述の半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)です。
半夏瀉心湯は、処方名が示すとおり「瀉心=みぞおちの痞えを取る」薬で、胃もたれや嘔気など胃の上部の症状を改善する作用があります。
体力中程度の方向けで、胃腸のゴロゴロ鳴る軟便傾向を伴う神経性胃炎にも用いられます。
一方、体力が比較的ある人で油ものなど食べ過ぎによる胃もたれが主な場合には、平胃散(へいいさん)という処方も選ばれます。
平胃散は胃腸の余分な湿(水分停滞)を取り除き、消化を助ける処方で「胃がもたれて消化が悪く、ときに吐き気や食後の下痢がある」人に適します。
胃腸が丈夫な人の一時的な食べ過ぎや飲み過ぎによる食欲低下には、このような健胃薬的な漢方で対応できることもあります。
疲れや体力低下で食欲が出ないタイプ
慢性的な疲労や病後の体力低下により、エネルギー不足で食欲がわかないタイプです。
全身の倦怠感、手足のだるさ、顔色の悪さなどを伴うことが多く、いわゆる「夏バテ」や長引く病後の食欲不振が該当します。
漢方では気血両方の不足や臓腑の機能低下が背景にあると考え、身体を補って食欲を増進させる処方を用います。
代表的なのが補中益気湯(ほちゅうえっきとう)です。
補中益気湯は文字通り「中(消化機能)を補い、気を益す」処方で、胃腸の働きを高めて食欲を出し、気力を回復させる効果があります。
体力虚弱で胃腸機能も衰えて疲れやすい人の食欲不振に広く用いられ、夏バテによる食欲低下や病後・術後の衰弱にも効果が期待できます。
人参や黄耆、白朮など補気の生薬がしっかり配合され、柴胡や升麻といった生薬で沈みがちな気を持ち上げる作用もあるため、飲み続けることで全身の活力が増してきます。
実際、「少し動くと疲れる」「夏バテで食欲がわかない」というチェック項目に当てはまる方に適した処方です。
補中益気湯でも追いつかないような重度の虚弱状態では、十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)や人参養栄湯(にんじんようえいとう)といった、補中益気湯にさらに補血作用を加えた処方が用いられることもあります。
いずれにせよ、疲労や体力低下が著しい場合は早めに漢方医に相談し、適切な処方で体調を立て直すことが大切です。
関連記事:夏バテを即効治すことはできる?つらい症状を軽くする食べ物と飲み物
食欲不振に効く漢方の飲み方

漢方薬の効果を十分に引き出すためには、正しい方法で継続的に服用することが重要です。
ここでは、漢方薬を服用するタイミングや期間、予防的な利用方法について解説します。
服用のタイミング
漢方薬は一般的に食前または食間に服用するのが基本です。
食前とは食事の30分~1時間前、食間とは食後2時間ほど経過した頃を指し、いずれも胃に食べ物が残っていない空腹時にあたります。
これは、胃の中に食物があると漢方薬の有効成分が食物繊維に吸着されて吸収が阻害されるためで、空腹時に飲むことで最大の効果を得るためです。
したがって「朝起きてすぐ」「昼食と夕食の中間の午後」「就寝前(胃が空の状態なら)」など、1日3回服用の場合はこれらのタイミングに飲むと良いでしょう。
服用時は水か白湯で飲みます。
苦くて飲みにくい場合、少量のぬるま湯に溶いて一気に飲んだり、オブラートに包んだりする工夫もあります。
また、万一飲み忘れた場合は次の服用時間まで待ち、2回分を一度に飲まないようにしてください。
多少時間がずれても継続することが大切であるため、できる範囲で空腹時を意識しつつ、忘れたときは無理にまとめて飲まず次回からまた規則正しく服用しましょう。
服用期間
漢方薬は症状の原因を体質から改善していくため、西洋薬のように即効で治るとは限りません。
効果が実感できるまでの期間は人それぞれですが、基本的には処方された用法用量を守ってしばらく続けることが重要です。
一般的な目安として、1ヶ月ほど服用しても症状に全く変化がない場合は、一度服用を中止して医師や薬剤師に相談することが推奨されています。
逆にいえば、多少の改善が見られるうちは続けて服用し、徐々に体調が整ってくるか様子を見ます。
症状が改善してきたら医師の指示に従い減量・中止を検討します。
急性の症状で用いる漢方(例えば感冒に対する葛根湯など)は数日で切り上げる場合もありますが、食欲不振のような慢性的症状では数週間~1ヶ月程度を一つの区切りにすると良いでしょう。
服用を始めてから食欲や体調にどのような変化があったかを観察し、改善が見られない場合には処方の見直しや他の治療の必要があるかもしれません。
自己判断でだらだら飲み続けるのではなく、定期的に専門家に経過を報告して指示を仰ぎましょう。
予防目的の服用
漢方薬は症状が出てから対処するだけでなく、未病(病気になる前に整える)目的で服用することもあります。
食欲不振に関して言えば、「夏になると毎年食欲が落ちる」「疲れるとすぐ食が細くなる」という体質の方は、そうした状況に陥る前に漢方で体調を整えておく方法があります。
例えば夏バテ予防として、暑くなる前の初夏から補中益気湯を飲み始め、夏の間も継続することで食欲低下を防ぎ体力を維持するといった使い方があります。
補中益気湯は胃腸を強化し気力を補う薬であるため、夏場に起こりがちな食欲不振の予防に適しています。
同様に、ストレスで食欲が落ちやすい人が普段から帰脾湯を服用しておくことで精神バランスを整え、ストレス耐性を高めておくケースもあります。
ただし予防目的とはいえ医薬品であることに変わりないため、自己判断で長期連用するのではなく医師・薬剤師に相談の上で開始・中止の判断をするようにしてください。
漢方薬は体質に合えば健康維持にも役立ちますが、不必要に飲むことは避け、あくまで必要な期間・タイミングで賢く活用しましょう。
漢方薬の選び方と使う際の注意点

漢方薬は約150種類もの処方があり、症状や体質に合わせて適切なものを選ぶ必要があります。
また、西洋薬とは異なる注意点もあります。
ここでは漢方薬を選ぶ際の基本と、使用上の留意点を整理します。
市販と処方の違い
漢方薬には、医師が診察に基づいて処方する医療用漢方製剤と、ドラッグストアなどで購入できる一般用漢方製剤(OTC漢方薬)があります。
両者は含まれる生薬成分や処方内容そのものは基本的に同じですが、違いとして市販薬は安全性に配慮して有効成分量がやや少なめに調整されている場合がある点が挙げられます。
病院で処方される漢方薬は医師の診断のもと症状に適合したものが処方されますが、市販の漢方薬は自分で症状に合ったものを選んで購入する形になります。
そのため、同じ処方名でも市販薬では適応症が限定的だったり、用量が調節されているケースがあります。
例えば、病院で処方される補中益気湯と市販の補中益気湯エキス錠では、生薬の抽出量(1日量)が市販薬の方がやや少なく設定されていることがあります。
このような差はありますが、正しく使えば市販薬でも効果は期待できます。
ただし症状が重い場合や自分で選択に迷う場合は無理をせず医療機関を受診して処方してもらう方が確実でしょう。
症状に合ったものを選ぶ
漢方薬選びでもっとも重要なのは今の自分の症状・体質に合った処方を選ぶことです。
漢方医学には「同病異治」(同じ病名でも証により処方が異なる)という考え方があり、食欲不振だからこの薬と機械的に決められるものではありません。
例えば一口に食欲不振と言っても、胃もたれ主体なのか、冷えがあるのか、疲労が強いのか、精神的ストレスかで適する薬は変わります。
本記事の前半でタイプ別に紹介したように、自分のタイプにマッチする漢方薬を選ぶことが大切です。
市販薬を購入する際は製品の説明書きをよく読み、「体力中等度」「虚弱」「実証」などの適応体質や具体的な症状が自分に合致するか確認しましょう。
分からない場合は薬剤師に相談して選んでください。
逆に病院で処方される場合は、医師が証を見極めて処方を決めてくれます。
症状だけでなく普段の体質や他の不調なども遠慮なく伝え、自分に合った漢方薬を処方してもらいましょう。
服用中の薬との飲み合わせを確認する
漢方薬は天然由来の生薬からできていますが、だからといって他の薬との併用が全て安全というわけではありません。
西洋薬と一緒に飲むと好ましくない場合や、生薬同士が作用を強め合い過ぎる場合があります。
例えば甘草を含む漢方薬を複数併用すると偽アルドステロン症のリスクが高まる可能性があります。
また、西洋薬でも利尿剤や心不全の薬と甘草の併用は注意が必要など、相互作用が知られている組み合わせがあります。
現在ほかに服用中の薬やサプリメントがある方は、漢方薬を開始する前に必ず医師・薬剤師に併用して問題ないか確認しましょう。
特に処方薬を飲んでいる場合は自己判断で市販の漢方薬を追加せず、主治医に相談してください。
市販の漢方薬でも、実は同じ生薬が入った別の漢方薬を重複して飲んでいたというケースもあります。
医療機関で処方を受ける際も、他に飲んでいる薬をきちんと伝えるようにしましょう。
使用前に専門家に相談する
漢方薬はドラッグストアでも手軽に入手できますが、症状に合ったものを安全に使うために専門家への相談をおすすめします。
初めて漢方を試す場合は、漢方に詳しい医師の診察を受けてみるのが理想的です。
医師でなくても、薬局の薬剤師や登録販売者に症状を説明すれば適切な漢方薬を選ぶ手助けをしてくれます。
また、妊娠中・授乳中の方や、高齢で持病がある方、小さなお子さんに漢方薬を使う場合などは特に注意が必要です。
そのような場合も自己判断せず、医師や薬剤師に服用可能かを確認してください。
漢方薬にも副作用や禁忌があり、体質によって合わないこともあります。
例えば体力のない人に瀉下作用の強い大柴胡湯は不向きですし、逆にがっちりした人に人参養栄湯では効きません。
専門家のアドバイスのもと、自分に合った漢方治療を安全に取り入れましょう。
関連記事:オンライン診療における処方箋のもらい方をわかりやすく解説
関連記事:双極性障害のご家族をやむなく入院させたい場合に考えるべきこと|よつば民救
漢方以外でできる食欲不振の対処法

漢方薬による体質改善と並行して、日常生活の工夫でも食欲不振の改善を目指しましょう。
胃腸をいたわり、生活習慣を整えることが回復への近道です。
ここでは、自宅でできる主な対処法を紹介します。
胃腸を休ませる食事
食欲がないときに無理に普通の食事を詰め込むと、かえって胃腸に負担をかけてしまいます。
食欲不振が辛いときは思い切って1食抜くか、いつもの半量程度に減らして、まず胃腸を休ませましょう。
空腹を感じないのに無理に食べる必要はありません。
「食べなきゃ」と焦るとストレスにもなります。何か口に入れたいときは、一度にたくさん食べず少量ずつ複数回に分ける方が負担が軽減します。
また、食べる場合は消化の良い食べ物を選ぶことが大切です。
お粥やうどん・煮込んだ野菜スープ・豆腐料理など、胃に優しく栄養バランスの良いものがおすすめです。
脂っこい揚げ物や刺激の強い香辛料、生野菜や硬い食品などは避けましょう。
どうしても量が食べられない場合は、栄養補助的にスポーツドリンクや経口補水液・ゼリー飲料などで水分と最低限のエネルギーを補給しても構いません。
便秘があると食欲低下に繋がるため、適度な水分・食物繊維の摂取も心がけてください。
まずは胃腸に優しい食生活で、消化器をリセットすることから始めましょう。
ストレスや睡眠の見直し
精神的ストレスや睡眠不足は食欲不振の大きな原因になります。
ストレスがたまると自律神経のバランスが乱れ、胃腸の動きも悪くなってしまいます。
そこで、ストレスを上手に発散し心身をリラックスさせる工夫が必要です。
趣味の時間を持つ、軽い運動をする、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かるなど、自分なりのリフレッシュ法を取り入れてみましょう。
運動はストレッチや散歩など無理のない範囲で構いません。
体を適度に動かすと夜の睡眠が深くなり、結果的に自律神経の安定につながります。
十分な睡眠も欠かせません。
寝不足が続くとそれ自体がストレスとなり、食欲低下を招きます。
毎日6〜7時間程度の睡眠時間を確保し、できれば夜更かしをせず日付が変わる前には就寝する習慣をつけましょう。
寝る前にスマートフォンを見る時間を減らし、リラックスできる環境を整えることも大切です。
さらに、緊張で胃が締め付けられるような人は呼吸法やツボ押しも試してみるとよいでしょう。
深呼吸を意識すると副交感神経が働きリラックスできます。
食欲増進に有効とされるツボには、中脘(ちゅうかん)や足三里(あしさんり)、胃兪(いゆ)などがあります。
指圧マッサージで刺激すると胃の不快感やストレス緩和に効果が期待できます。
このようにストレスケアと休養を十分にとることで、食欲も徐々に回復しやすくなります。
生活習慣のリズムを整える
不規則な生活は自律神経の乱れを招き、結果的に食欲不振の一因となります。
規則正しい生活リズムを意識して、体のリズムを立て直しましょう。
朝は決まった時間に起きて太陽の光を浴び、夜は適切な時間に眠るという基本的な生活サイクルを整えることが大切です。
朝日を浴びると体内時計がリセットされ、昼は交感神経が活発に、夜になると自然にお腹が空いてきて眠気が訪れるという、本来のリズムが戻ってきます。
日中はこまめに休息を挟みつつ活動し、1日3食できるだけ同じ時間帯に食事をとるように心がけてください。
食事時間が毎日バラバラだと胃腸が混乱しがちなので、少量でも朝・昼・夕と欠かさず摂ることが望ましいです。
夜遅い食事は胃に負担をかけるため、夕食は就寝3時間前までに済ませるのが理想です。難しい場合は、軽めの夕食と間食で調整すると良いでしょう。
また、仕事で昼夜逆転しがちな方は、休日だけでも朝型の生活に寄せてみてください。
生活の乱れを少しずつでも正すことで、乱れていた自律神経のバランスが安定し、空腹感や食欲が自然と戻ってくることが期待できます。
体は正直で、規則正しいリズムが戻れば「お腹が空くのが当たり前」という状態に近づいていきます。
生活習慣の見直しは地味ですが、根本的な改善策として非常に重要です。
食欲不振で医療機関を受診すべきタイミング

一時的な食欲不振はよくあることですが、長引く場合や全身状態に影響が出ている場合は放置しないでください。
以下のようなケースに当てはまるときは、早めに医療機関で相談することをおすすめします。
3日以上食事がとれない
食欲不振の状態が何日も続いている場合は要注意です。
目安として、丸3日間ほとんど食事が摂れない、または水分だけで固形物が全く喉を通らないという状況ならば、早めに受診しましょう。
体に必要な栄養が不足し始め、体力の低下や臓器への負担が心配されます。
特に高齢者や持病のある方は、数日食べないだけで脱水や栄養失調に陥りやすいため、2日程度でも深刻なら受診を検討してください。
医師には、いつからどの程度食べられていないかを具体的に伝えましょう。
急激な体重減少
短期間で明らかに体重が減少している場合も要チェックです。
食事量の減少に比例して体重が落ちていくのは当然ではありますが、例えばこの1〜2週間で数キロ単位の減少があるなど急激な痩せ方をしているならば、何らかの異常が進行している可能性があります。
極端なケースでは、短期間に体重の5〜10%以上が減少すると危険信号です。
筋肉量の減少や栄養失調にもつながり、免疫低下や内臓への負担を招きます。
体重減少は客観的な指標なので、普段体重計に乗る習慣がない人も意識的にチェックし、著しい変化があれば受診して原因を調べてもらいましょう。
強い倦怠感
食欲不振が続くことで全身の倦怠感やめまい・立ちくらみなどが出てきたら、躊躇せず医療機関へ相談してください。
食事が十分取れないと鉄分やビタミンなども不足しがちで、鉄欠乏性貧血になってフラフラしたりだるさが強まることがあります。
肌や髪に元気がなくなるなど栄養失調の兆候が現れるケースもあります。
特に「階段を上がると息切れがする」「朝起きられないほど疲労感がある」等は深刻です。
また、発熱や嘔吐・下痢を伴う場合は、感染症や炎症性疾患など他の病気が原因で食欲不振になっている可能性も高いです。
このように全身症状を伴うときは一刻も早く受診し、必要な検査や治療を受けてください。
漢方を服用しても改善しない
市販薬や処方された漢方薬を一定期間試してみても症状が良くならない場合も、別の原因を疑う必要があります。
漢方薬を真面目に服用し生活改善も行ったのに食欲不振が続く場合、実は服用中の薬の副作用で食欲低下が起きている可能性や、胃腸以外の病気(例えば甲状腺機能低下症やうつ病など)が隠れていることもあります。
このようなケースでは、漢方だけでなく原因そのものへの対処が必要です。
改善しない食欲不振を放置すると、栄養不足による体力低下→さらに食欲不振という悪循環に陥ることも指摘されています。
「自分なりに色々やってみたが効果がない」という段階になったら、早めに消化器内科や専門医を受診しましょう。
医師にこれまで試した漢方やサプリ、期間と効果の有無を伝えることで、今後の治療方針の参考になります。
関連記事:ストレスによる食欲不振の原因とリスク:オンライン診療と漢方でできる改善策
漢方薬の処方ならオンラインメディカルクリニックにご相談ください

食欲不振の改善に漢方薬を取り入れたいとお考えの方は、オンラインメディカルクリニックをぜひご利用ください。
当クリニックでは医師と漢方薬剤師が連携し、患者さん一人ひとりの症状・体質を丁寧に伺った上で、その方に合った漢方薬を選んで処方しています。
初診からオンライン診療で対応し、自宅や職場からスマホ・PCで気軽に受診可能です。
オンラインメディカルクリニックなら忙しくて通院の時間が取れない方でも安心です。
平日夜20時まで診療対応しており、予約から問診・診察・処方まで全てインターネット上で完結します。
処方された漢方薬はご自宅への配送も可能なので、来院や薬局に行く手間もありません。
保険適用の漢方処方にも対応しており、公的医療保険の範囲で治療を受けられます(※症状や地域によって一部制約があります)。
「食欲不振で悩んでいるが、どの漢方を試せばいいか分からない」「遠方なので漢方の専門医が近くにいない」という方こそ、当クリニックのオンライン診療をご活用ください。
専門知識を持った医師があなたの体質に合わせた漢方薬をオーダーメイドで処方し、食欲不振の根本改善をサポートいたします。
お一人で抱え込まず、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
食欲不振は「体からの不調のサイン」であり、軽視せず原因に応じた対処をすることが大切です。
漢方医学の視点では、ストレスや冷え、胃腸虚弱など人それぞれ異なる原因(証)によって食欲不振が生じると考えるため、自分のタイプに合った漢方薬を用いることで根本からの改善が期待できます。
六君子湯、半夏瀉心湯、補中益気湯など症状別の代表処方があり、上手に活用すれば胃腸の調子を整えて食欲を取り戻す助けとなるでしょう。
オンラインメディカルクリニックのパーソナル漢方なら、自宅にいながら専門的な漢方治療の相談・処方が可能です。
自分に合った漢方の力と生活改善で、少しずつでも食欲と元気を取り戻していきましょう。