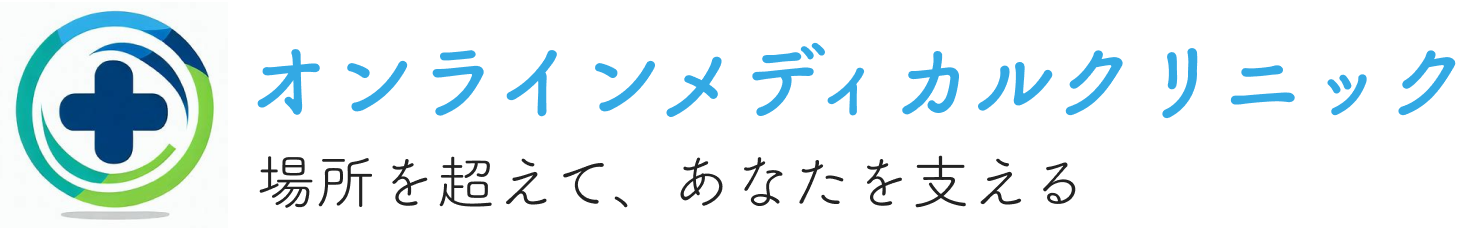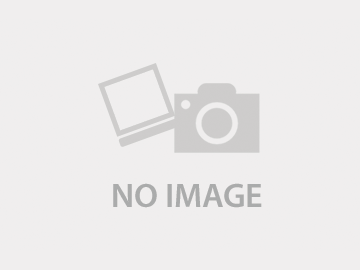感染性胃腸炎(胃腸風邪)は、毎年大人から子どもまで多くの人がかかる身近な病気です。
吐き気・嘔吐、下痢、腹痛、発熱といった症状が突然現れ、場合によっては長時間辛い状態が続くことがあります。
本記事では、感染性胃腸炎の原因や潜伏期間を始め、症状の経過と重症化のサイン、そして似た症状を起こす他の病気との違いを解説します。
ウイルス性胃腸炎の原因ウイルスと潜伏期間

ウイルス性胃腸炎は、その名の通りウイルス感染によって起こる急性の胃腸炎です。
感染性胃腸炎全体の約90%を占めており、毎年秋から冬にかけて流行します。
代表的な原因ウイルスにはノロウイルス・ロタウイルス・アデノウイルスなどがあり、それぞれ特徴や潜伏期間が異なります。
| 病原体 | 主な特徴 | 潜伏期間 | 主な症状 |
| ノロウイルス | 冬に流行・感染力が非常に強い | 約1~2日 | 激しい嘔吐、下痢、発熱 |
| ロタウイルス | 乳幼児に多い(大人も感染あり) | 約1~3日 | 水様性の下痢、嘔吐、発熱 |
| アデノウイルス | 年間を通して発生(季節問わず) | 約5~7日 | 下痢、腹痛、発熱(嘔吐もあり) |
ノロウイルスによる胃腸炎は、冬季(11月~3月)に流行のピークを迎えます。
感染力が極めて強く、カキなどの生食で感染するほか、感染者の触れた物品や嘔吐物・便を介しても広がります。
1~2日の潜伏期の後に突然の吐き気・嘔吐、下痢、腹痛、発熱などがあらわれ、通常は2~3日程度で回復することが多いです。
ロタウイルスは主に乳幼児で流行しますが、大人にも感染する可能性があり、白色~水っぽい下痢と激しい嘔吐が特徴です。
潜伏期間は1~3日程度で、発症後は発熱や腹痛も伴い、回復まで1~2週間かかることもあります。
ロタウイルスは毎年春先(2月~5月)に流行する傾向が強く、感染経路は嘔吐物・便や汚染された食べ物・水など多岐にわたります。
アデノウイルス(腸管アデノウイルス40/41型など)は季節に関係なく一年中発生し得るウイルスで、潜伏期間は5~7日程度と他のウイルスに比べ長めです。
症状は嘔吐、水様性下痢、発熱などで、通常1~2週間ほどで回復に向かいます。
なお、アデノウイルスにはプール熱(咽頭結膜熱)などを起こす型もありますが、腸炎を起こす型では上記のような胃腸症状が中心です。
以上のように原因ウイルスによって症状の強さや持続期間に違いがありますが、特効薬はなく、基本的に対症療法となる点は共通しています。
乳幼児ではロタウイルスワクチンの定期接種が行われており重症化予防に有効です。
ノロウイルスに対するワクチンは存在しないため、日頃から手洗いなどの感染予防策が重要になります。
関連記事:辛い下痢の時に薬が手元になくてもオンライン診療なら外出不要で入手可能!
ウイルス性胃腸炎の症状はいつまで続く?
主な症状と経過
ウイルス性胃腸炎にかかった場合、症状の経過は多くの場合「突然の吐き気・嘔吐」から始まり、その後に腹痛や発熱、下痢へと進行します。
以下に一般的な経過に沿った症状の流れと注意点を示します。
| 時期 | 主な症状 | 注意点・ケアのポイント |
| 初期(1~2日目) | 激しい下痢、嘔吐、腹痛 | 脱水に注意。嘔吐が落ち着くまでは飲食を控え、水分補給は少量ずつこまめに。 特に初発の数時間~半日ほどは嘔吐が続くことが多く、この間に脱水が進みやすい。 経口補水液等で水分・電解質を補給する。 |
| 中期(2~4日目) | 下痢(回数多い水様便)、発熱、倦怠感、食欲不振 | 体力消耗に注意。 発熱や下痢で体力を消耗しやすい時期なので、無理をせず十分に休養する。 食欲がなければ無理に食べず、水分と栄養補給はできる範囲で行う。 高熱や腹痛が強い場合は解熱鎮痛剤の使用も検討。 |
| 回復期(5日目以降) | 下痢の頻度減少、腹痛や倦怠感の改善、食欲回復 | 徐々に普段の生活へ。症状が軽減しても油断せず、消化に良い食事から少しずつ再開する。 体調が万全に戻るまでは無理な外出や勤務・登校を避け、十分な睡眠と栄養摂取で体力を回復させる。 |
通常、ウイルス性胃腸炎の急性期症状は数日~1週間程度で自然に改善に向かいます。
初期の1~2日間は嘔吐・下痢が最も激しく、特に発症後最初の6~12時間程度は繰り返し嘔吐するケースも珍しくありません。
この初期段階で重要なのは、とにかく脱水を防ぐことです。
嘔吐が続いている間は無理に食べさせず、吐き気が落ち着くまでは胃腸を休めます。
その上で少量の水や経口補水液をこまめに与え、体から失われた水分と塩分を補います。
中期(発症後2~3日頃)になると嘔吐は徐々におさまってきますが、代わりに下痢が続くことが多いです。
下痢は体内の病原体を排出するための防御反応でもあるため、数日間は下痢が続いても慌てず、水分とミネラル補給に努めましょう。
発熱や全身の倦怠感も見られますが、この時期は無理をせず安静に過ごすことが大切です。
消化管が弱っているため食欲も低下しますが、脱水予防のためスープやゼリー飲料などで少しずつ栄養補給をすると良いでしょう。
発症から4~5日経過すると、徐々に食欲が戻り始め、下痢の回数や腹痛も改善に向かいます(回復期)。
この段階では、体調が回復してきたからといってすぐに普通の食事に戻すのではなく、おかゆやうどんなどの消化に良い食事から再開します。
少量を摂って問題なければ徐々に量を増やし、最終的に通常の食事に戻していきます。
回復期でも油断せず、疲れが残っている場合は引き続き十分な休息を取りましょう。
特に乳幼児や高齢者では、回復に見えても脱水が残っていたり体力が低下していることがあるため、完全に元気になるまでは安静を心がけます。
重症化のサイン
多くの場合、ウイルス性胃腸炎は適切な水分補給と休養によって自然に快方へ向かいますが、中には重症化するケースもあります。
次のような症状・兆候が見られた場合は、胃腸炎以外の病気や合併症の可能性も含め、早急に医療機関を受診してください。
- 嘔吐が長引いて水分が摂れない(目安として丸1日以上嘔吐が続く、吐いてばかりで水も受け付けない)
- 激しい脱水症状の兆候(尿が12時間以上出ていない、口の渇き・めまい、ぐったりして反応が鈍い等)
- 血液が混じった吐物や血便が出る(消化管出血や重い細菌感染の疑い)
- 激しい腹痛が持続・増強する(普段と違う強い痛み、または痛みの部位が右下腹部に移動する等)
- 39℃以上の高熱や意識障害・失神(脱水の悪化や脳症などの可能性)
これらは重症化や他の疾患のサインであり、特に嘔吐・下痢による脱水が進むと命に関わることもあります。
「たかが胃腸炎」「ただの脱水」と侮らず、少しでも様子がおかしい場合は夜間でも躊躇せず受診しましょう。
乳幼児では症状の進行が早いことも多いため、発熱や嘔吐・下痢が続くときは早めに小児科を受診してください。
ウイルス性胃腸炎に似ている病気

吐き気・嘔吐や下痢、腹痛といった症状は、感染性胃腸炎以外の疾患でも起こり得ます。
「胃腸炎かと思ったら、実は別の病気だった」というケースもあり、放置すると危険な疾患が隠れていることもあります。
ここでは、ウイルス性胃腸炎と症状が似ている主な病気を紹介し、それぞれの特徴を解説します。
細菌性胃腸炎
細菌性胃腸炎はサルモネラ・カンピロバクター・腸管出血性大腸菌(O157)などの細菌感染による胃腸炎です。
症状自体はウイルス性胃腸炎と似ており、発熱・腹痛・下痢・嘔吐などが起こりますが、原因となる細菌によって特徴に違いがあります。
例えばサルモネラでは高熱を伴う下痢・腹痛、カンピロバクターでは腹痛・下痢・発熱に加えて嘔気や倦怠感が出ることがあります。
また腸管出血性大腸菌(O157)では激しい腹痛と血便が特徴です。
さらには加熱が不十分な生肉や、夏場に悪くなった食材を食べてしまうなど、食べ物由来の発症が多く見られます。
細菌性胃腸炎の治療では、原因菌によっては抗生物質の投与が必要になる場合があります(ウイルス性胃腸炎には抗生物質は無効です)。
症状が重く血便が見られる場合や、集団食中毒が疑われる場合には、早めに受診して便培養検査などで原因菌を調べることが重要です。
ウイルス性か細菌性か自己判断が難しいケースもあるため、高熱や血便など普段と違う症状がある時は医療機関で相談しましょう。
腸閉塞
腸閉塞とは、腸管が狭窄・閉塞して内容物が先に進まなくなる状態です。
過去の腹部手術による腸の癒着や、腸へのヘルニア嵌頓などが原因で起こります。
腸閉塞になると胃腸の流れがせき止められるため、食べ物や消化液が下流に進まず上流で渋滞し、激しい吐き気・嘔吐が繰り返されます。
一方で下痢はあまり見られないか、ごく少量しか出ないのが感染性胃腸炎との違いです。
お腹は膨れて張り、腸が動かないことで生じるしぶとい痛みが続くこともあります。
腸閉塞の場合、嘔吐しても詰まった原因が解消されない限り症状は改善しません。
放置すると腸管が壊死する危険もあるため、「吐いても吐いても止まらない」「便やガスがまったく出ない」という時は腸閉塞を疑い、早急に受診してください。
診断には腹部X線やCT検査が有用で、治療は絶飲食・点滴などの保存的治療から、原因によっては手術が必要になる場合もあります。
虫垂炎(盲腸)
虫垂炎(一般に「盲腸」と呼ばれる)は、虫垂が細菌感染などで炎症を起こす疾患です。
胃腸炎と初期症状が似る場合があり、嘔吐や発熱・腹痛が生じる点が共通しています。
しかし虫垂炎の痛みの特徴として、最初はみぞおち(心窩部)やおへその周辺の鈍い痛みで始まり、徐々に右下腹部へ痛みが移動して強くなる点が挙げられます。
胃腸炎ではお腹全体の不快感や差し込む痛みが波のように起こるのに対し、虫垂炎では右下腹に限定した鋭い痛みに変わっていくのが典型的です。
また、虫垂炎が悪化して腹膜炎を起こすと、歩く振動や咳でもお腹に響くほど痛みが強くなるのも特徴です。
この段階では発熱も高くなり、放置すれば膿んだ虫垂が破裂して重篤な状態になります。
「腹痛が先行し、嘔吐や発熱が後から出てきた」「腹痛の部位が時間とともに変化している」といった場合は虫垂炎を疑い、早めに外科または消化器内科を受診しましょう。
診察や腹部エコー・CT検査で比較的容易に診断がつき、治療は抗生剤投与や外科的切除(虫垂摘出術)を行います。
過敏性腸症候群(IBS)
過敏性腸症候群(IBS)は、ストレスなどがきっかけで腸の運動や知覚過敏が生じ、慢性的な腹痛や下痢・便秘を繰り返す機能性疾患です。
感染性胃腸炎とは異なり腸に炎症や感染が起きているわけではなく、検査をしても腸自体に明確な異常は見つかりません。
主な症状は腹痛・腹部不快感・下痢あるいは便秘(または両方を交互に)などで、症状が数ヶ月以上持続または再発を繰り返すのが特徴です。
一方、発熱や嘔吐といった症状は通常伴わず、症状が急激に悪化することもありません。
過敏性腸症候群は慢性的な経過をたどるため、「数日でケロッと治る」感染性胃腸炎とは経過が大きく異なります。
例えば、「下痢が何ヶ月も治らないが熱は無い」「緊張するとお腹が痛くなり下痢をするが、検査では異常なし」という場合はIBSの可能性があります。
治療も感染症とは異なり、食事や生活習慣の見直し・ストレス対策・整腸剤や腸の働きを調節する薬の内服などが中心です。
急性の症状ではなく長引く腹痛・下痢でお悩みの場合は、一度消化器内科でIBSの検査・治療を検討してもよいでしょう。
その他の疾患
上記の他にも、胃腸炎と症状が紛らわしい疾患はいくつか存在します。
例えば急性膵炎や胆嚢炎では上腹部の激痛と吐き気・嘔吐が起こりますが、下痢はあまり見られません。
また、虚血性大腸炎や潰瘍性大腸炎などの腸炎では、腹痛と下痢に加えて血便を伴いますが、慢性的な経過や中高年に好発する点でウイルス性胃腸炎とは異なります。
まれに心筋梗塞や脳卒中など消化管以外の病気が吐き気や嘔吐だけを引き起こし、「胃腸の風邪かな?」と誤解されるケースも報告されています。
いずれにせよ、通常のウイルス性胃腸炎なら数時間~数日で症状が改善するのが一般的です。
にもかかわらず「症状がどんどん悪化する」「いつまでも良くならない」「普段と明らかに様子が違う」という場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、詳しい検査を受けることが大切です。
早めに原因を突き止めて適切な治療を受けることで、重篤な事態を防ぐことができます。
感染性胃腸炎で病院を受診すべきタイミング

感染性胃腸炎は軽症であれば自宅で安静・水分補給を心がけることで自然に治るケースが多いですが、次のような場合は早めに病院を受診することをおすすめします。
乳幼児や高齢者、持病のある方が発症した場合
小さな子どもや高齢の方は脱水症状になりやすく、重症化しやすい傾向があります。
乳幼児では数時間で症状が悪化することもあるため、発熱や嘔吐が続く時は躊躇せず小児科を受診しましょう。
高齢者では嘔吐物の誤嚥による肺炎なども心配されるため、早めの受診が大切です。
水分がまったく摂れない場合
激しい嘔吐が何度も続き、水さえ飲めない状況では点滴による補液が必要です。
通常、激しい嘔吐は半日ほどで落ち着くことが多いですが、6~12時間以上嘔吐が止まらない場合や、尿が出ていない・唇が渇いてカサカサになるなど脱水の兆候が強い場合は、夜間でも救急を受診してください。
血便や激しい腹痛がある場合
血液の混じった下痢便が出る場合は細菌感染や腸炎の重症化が疑われます。
また、立てないほどの強い腹痛や右下腹部に限局する痛み(虫垂炎の疑い)など、普段と違う腹痛の時も、早急に診察を受けてください。
症状が長引く場合
通常は数日で快方に向かうはずの胃腸炎の症状が、5日以上経っても改善しない場合は、別の原因が隠れている可能性があります。
念のため病院で検査を受け、必要なら便の検査や血液検査を行ってもらいましょう。
以上のようなタイミングで受診することで、必要な治療(点滴や薬剤投与など)を速やかに受けられ、他の疾患が隠れていれば早期発見にもつながります。
「受診すべきか迷う」という場合は、各自治体の#8000(小児救急電話相談)や地域の医療相談窓口に電話して指示を仰ぐのも一つの方法です。
特に嘔吐が激しい時は移動も大変になるため、無理をせず救急車を呼ぶことも検討してください。
早めの対応が、重症化を防ぐ鍵となります。
ウイルス性胃腸炎の自宅療養時の注意点

ウイルス性胃腸炎と診断されたら、症状が治まるまでは自宅でゆっくり休むことが基本です。
他者への感染を防ぐためにも、症状があるうちは会社や学校を休み、自宅療養に専念しましょう。
ここでは自宅療養中の注意点をいくつか挙げます。
無理をしない安静の取り方
何より重要なのは充分な休養です。
発熱や下痢で体力が奪われているため、仕事や家事は可能な限り人に任せ、ゆっくり横になりましょう。
特に発症直後のつらい時期は、無理に食事を摂ろうとしたり動き回ったりせず、身体を温かくして安静に過ごすことが回復への近道です。
症状が改善してきても、油断は禁物です。
職場や学校への復帰目安は、嘔吐や下痢が治まり食欲も戻ってから少なくとも1~2日程度は様子を見て、体力が十分回復してからとしてください。
胃腸炎が治りかけの時期に無理をすると、ぶり返したり他の感染症にかかりやすくなったりする恐れがあります。
食事の目安と工夫
食事は胃腸に負担をかけない内容から始めることが大切です。
嘔吐や下痢がひどい間は固形物を無理に摂る必要はありませんが、少し落ち着いてきたらエネルギー補給を検討します。
以下を目安にしてください。
消化に良いものを少量から
おかゆ・柔らかく煮たうどん・スープ・ゼリー・すりおろしリンゴ等から始めます。
最初は一度にたくさん食べず、少しずつ頻回に摂るようにしましょう。
具合が悪化しないか様子を見ながら、徐々に量を増やします。
避けるべき食品
脂っこい揚げ物や肉類、乳製品、生野菜・食物繊維の多いものなどは症状が完全に治るまで控えましょう。
油脂や食物繊維は消化に時間がかかり、胃腸を刺激して下痢や腹痛を悪化させる可能性があります。
また、香辛料の効いた刺激物やアルコールも避けてください。
食欲が戻ってきても、回復期には胃腸が弱っています。
焦らず段階的に普段の食事に戻すことが大切です。
例えば、おかゆ→軟飯→通常のご飯というように徐々に固形物へ移行しましょう。
タンパク質源も、最初は脂肪の少ない白身魚や鶏ささみなどから取り入れます(症状が強い間は無理に食べず、回復期に少量から)。
野菜も加熱して繊維を柔らかくしたものから少しずつ摂取します。
食事を元に戻すには数日かけるくらいの気持ちで、「腹八分目」を心がけると良いでしょう。
水分補給のコツとポイント
感染性胃腸炎では脱水予防のための水分・電解質補給が何より重要です。
以下のポイントに留意してください。
吐いた直後は飲まない
嘔吐してしまった場合、すぐに水分を飲ませると再び吐いてしまうことが多いです。
吐いた後はまず口をすすぐ程度にとどめ、最低でも30分~1時間ほど胃腸を休めましょう。
少量をこまめに
少し時間をおいて嘔吐がおさまってきたら、スプーン1杯程度の少量の水分を与えます。
それで吐かなければ、10分ほど間隔をあけて再度少量飲む、といった形で進めます。
一度に大量に飲まず、少しずつ頻回に摂るのがコツです。
電解質を含む飲み物を
水やお茶だけでは塩分・糖分が補えないため、可能であれば経口補水液(ORS)やスポーツドリンク・薄めた果汁ジュース・味噌汁の上澄みなどを活用しましょう。
市販の経口補水液は吐き気が強くても吸収されやすい成分組成になっています。
甘すぎる飲料は胃に負担をかける場合もあるので、適度に薄めて与えると良いでしょう。
乳幼児の場合、母乳やミルクは基本的に継続して構いませんが、いつもより1回の量を減らし、回数を増やすなど工夫してください。
水分補給は「喉が渇く前に少しずつ」が基本です。
下痢が治まるまでの間、スポーツドリンクや経口補水液を常備し、喉が乾いていなくても定期的に飲むよう促しましょう。
特に小さなお子さんや高齢者は自分で渇きを自覚しにくいため、周囲が気を配ってあげてください。
吐き気が強い時は無理に固形物を与えず、水分と電解質の補給に徹することも大切です。
なお、点滴が必要かどうかの判断は難しいですが、尿量や意識状態を目安に「これは危ない」と思ったら早めに医療機関で相談しましょう。
関連記事:夏バテを即効治すことはできる?つらい症状を軽くする食べ物と飲み物
家族内感染を防ぐための対策

感染性胃腸炎は非常に感染力が強いため、家族や周囲への二次感染防止対策が欠かせません。
特にノロウイルスはごく微量のウイルスでもうつるため、一人発症すると家族全員に広がることもあります。
以下のポイントに気を付けましょう。
手洗いの徹底
家族全員、トイレの後や調理・食事前には必ず石けんと流水で手を洗う習慣を徹底してください。
アルコール消毒だけではノロウイルスやアデノウイルスには不十分な場合があるため、石けんを使った入念な手洗いが有効です。
下記にもありますが、手を拭いたタオルを共有したことで感染が広がることも考えられます。
吐物・おむつの適切な処理
嘔吐物や下痢便には大量のウイルスが含まれています。
処理する際は使い捨てのビニール手袋とマスク・エプロンを着用し、ノロウイルスの場合は特に塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)でしっかり消毒しましょう。
床に吐いた場合はペーパータオル等で静かに拭き取り、そのままビニール袋に密封して捨てます。
拭き取った後の床も薄めた漂白剤液で拭き、最後に水拭きしてください(塩素は金属を腐食するため)。
処理後は手袋を外してから改めて手洗いを行います。
共有物を避ける
感染者が使ったタオルや食器の共有は厳禁です。
タオル類はペーパータオルや個別のものを使用し、使用後すぐに熱湯消毒か漂白剤漬け置きしてから洗濯します。
食器や箸も別にし、洗浄は念入りに行いましょう。
トイレもできれば患者と別にするか、難しければ使用後に便座やレバーを次亜塩素酸ナトリウムで拭き取ると安心です。
家の環境整備
ウイルスはドアノブや手すり、スイッチなどにも付着します。
嘔吐・下痢の症状がある間は、家族も含めこまめにアルコール消毒や次亜塩素酸での拭き取りを行いましょう。
室内の換気も適宜行い、ウイルスがこもらないようにします。
嘔吐が激しい間は、看病する人以外は患者に近寄り過ぎないようにする配慮も必要です。
家族の体力を温存する
看病すると体力が減るため、それをきっかけに病気にかかりやすくなることがあります。
看病する方もしっかりと休み、体力をなるべく温存することで新たな病気にかかりにくくなります。
完全に感染を防げない場合も、早めに対策することで二次感染リスクを大きく下げることができます。
実際に兄弟や親が感染してしまった場合も焦らず、上記でご紹介した内容と同様の対処を行いましょう。
特にノロウイルスは症状が治まった後もしばらく(1~2週間程度)は便中にウイルスが排泄され続けます。
症状が治った後も、念のためしばらくは十分な衛生対策を続けることが大切です。
オンラインメディカルクリニックでは感染性胃腸炎の診察が可能

ウイルス性胃腸炎かなと思っても、「症状がつらくて外出できない」「忙しくて病院に行く時間がない」「嘔吐下痢で他の人にうつすと悪いから受診をためらう」ということもあるでしょう。
そうした場合に便利なのがオンライン診療です。
オンラインメディカルクリニックでは、ウイルス性胃腸炎についても自宅から医師の診察を受けることが可能です。
スマートフォンやパソコンで予約・ビデオ通話をするだけで医師に症状を相談でき、必要に応じてお薬の処方も受けられます。
オンラインメディカルクリニックの主なメリットは次のとおりです。
待ち時間ゼロ・24時間予約可能
平日夜20時まで診療対応しており、好きな時間・場所から予約・受診できます。
通勤通学の合間や自宅の空いた時間に受診でき、クリニックで長時間待合室で過ごす必要もありません。
初診から処方箋発行が可能
当クリニックでは初めての患者さんでもオンラインのみで診療と薬の処方まで完結できます。
診察後、電子処方箋が発行され、ご指定のいつもの薬局でお薬を受け取れます。
自宅への郵送も選択可能で、症状がつらく外出できない時でも安心です。
感染リスクの軽減
オンライン診療なら自宅などプライベートな空間で医師の診察を受けられるため、病院の待合室で他の患者さんから別の感染症をもらうリスクを避けられます。
感染性胃腸炎の場合、自分が外出することで他者にウイルスをうつす心配もなく、周囲への配慮という点でも有用です。
専門家チームによるサポート
複数の医師が在籍しており、必要に応じて専門の医療機関とも連携しています。
オンラインでの診察中に「やはり点滴が必要」「精密検査が必要」と判断された場合でも、速やかに適切な医療機関への案内が可能です。
オンラインで解決できること・できないことをきちんと見極め、患者さんの安全に配慮しています。
このように、オンラインメディカルクリニックを利用すれば、感染性胃腸炎のような急性疾患でも自宅から気軽に医師の診断を受けることができます。
もちろん重症の場合は最初から救急車を呼ぶべきケースもありますが、「受診すべきか迷う」「とりあえず医者に相談したい」といった段階で、オンライン診療は心強い選択肢となるでしょう。
オンラインメディカルクリニックは保険診療にも対応しており、初診から安心して利用できます。
感染症の流行期でも自宅で安全に診療を受けられますので、必要に応じて活用してみてください。
関連記事:下痢が止まらない時の対処法|受診の目安や危険のサインについて
まとめ
感染性胃腸炎はウイルスや細菌の感染によって起こる身近な病気で、秋冬シーズンを中心に毎年多くの人が罹患します。
自宅療養の際は、十分な休息と適切な水分・栄養補給に努めましょう。
昨今はオンライン診療といった便利なサービスも充実してきており、感染性胃腸炎のような急性疾患でも自宅から医師に相談できます。
症状が軽いうちに活用して適切な指示を仰ぐのも良い方法です。
感染性胃腸炎かなと感じたら、まずは水分補給と安静を心がけ、症状の推移を見守りましょう。
そして、少しでも「おかしいな」「重いかも」と思ったら早めに医療機関に相談してください。
監修医
島村泰輝
- 2012年3月 名古屋市立大学医学部 卒業
- 2014年4月 名古屋市立大学放射線科 入職
- 2015年4月 名古屋市立大学大学院博士課程入学 (専攻:生体防御・総合医学分野)
- 2019年3月 同大学院卒業、博士号取得
- 2019年6月 株式会社エムネス 入職
- 2022年10月 同 Medical Professional Service(医師部門)副本部長
- 2023年7月 オンラインメディカルクリニック開業
愛知県名古屋市出身。遠隔放射線画像診断を行う傍ら、AI開発、メディカル用プロダクト開発を行う。
医療としてはその他にも内科診療、訪問診療にも従事。医療はITでさらに良くなる事を信条として様々な取り組みを行う。
物理的、時間的に医療が届きにくい層に対して医療を届けるべくオンライン診療を中心としたクリニックを開業。今後は各種専門家とともに、遠隔地であっても質の高い医療を提供するサービスを構築していく。