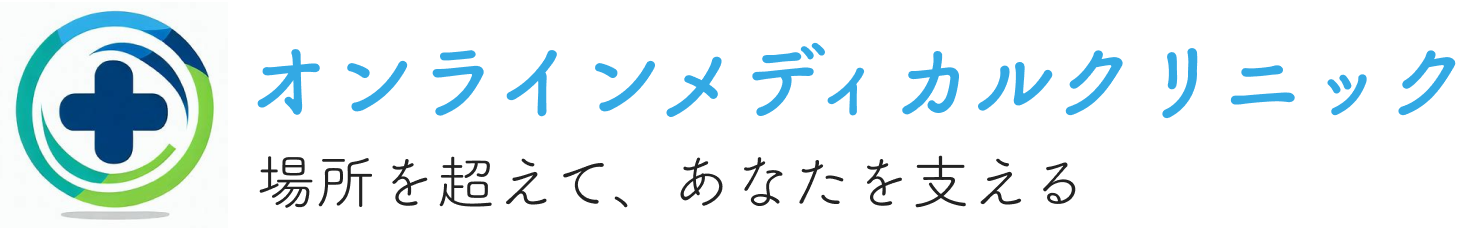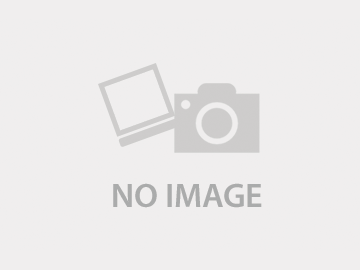夏場になると蚊やブヨなどの虫刺されに悩まされる方も多いでしょう。
虫に刺されたあと、 腫れがひどくなったり赤く腫れてしまったりすると不安にもなります。
病院に行くほどではないと思っても、「この腫れは大丈夫なのか?」と心配になることもあるかもしれません。
本記事では、虫刺されで腫れがひどくなる原因やアレルギー体質との関係、そして腫れが強いときの対処法や治療法について、最新の医学情報をもとにわかりやすく解説します。
また、特に注意すべき虫の種類や、症状が不安なときに利用できるオンライン診療についても触れます。
虫刺されによる腫れの原因(即時型反応・遅延型反応)

虫に刺されると、皮膚に虫の唾液や毒素といった異物が入り込むため、身体の防御反応として炎症が起こります。
この炎症反応には大きく分けて刺激反応とアレルギー反応の2種類があります。
刺激反応とは、刺された部位への直接的な物理・化学刺激によって起こり、刺された直後から痛みやヒリヒリ感・赤みが現れるものです。
一方、虫刺されによるアレルギー反応には時間経過により症状が現れるタイミングでさらに2種類に分類されます。
それが「即時型反応」と「遅延型反応」です。
即時型反応
刺された直後から数分以内にかゆみや膨疹(ふくらみ)、赤み(紅斑)が生じる反応です。
ヒスタミンなどが放出されることで、蚊に刺された跡にすぐ赤く膨れるような症状が典型的です。
通常、即時型のかゆみや腫れは数時間ほどで治まることが多く、跡形もなく消失します。
虫に刺され慣れている大人では、この即時型反応のみで軽く済む場合が多いでしょう。
遅延型反応
刺されてしばらく時間が経ってから(数時間~翌日以降)症状が出る反応です。
刺されて1~2日後に強いかゆみや赤みが出たり、硬く盛り上がった丘疹(ブツブツ)や水ぶくれ(水疱)が生じるのが特徴です。
遅延型の発疹やかゆみは数日~1週間程度続いた後に治ることが多いでしょう。
虫の種類によってはこの遅延型反応が主体となり、刺された直後は何ともなくても、翌日以降に腫れてくるケースもあります。
以上のように、虫刺されによる腫れはアレルギー機序によるところが大きく、即時型か遅延型かで現れ方が異なります。
ただし症状の出方には個人差が大きく、同じ虫に刺されても人によって腫れ方が違います。
これは、注入された毒液や唾液の種類・量の違いだけでなく、その人自身の体質や過去の暴露歴(今まで何度刺されたことがあるか)によって免疫反応の強さが異なるためです。
アレルギー体質の人や小さいお子さんでは強い反応が出やすいことが知られています。
次の章では、こうしたアレルギー体質と腫れやすさの関係について詳しく見てみましょう。
アレルギー体質と腫れの関係(ストロフルス・蚊刺過敏症など)
ストロフルス
アレルギー体質の方は虫刺されによる腫れもひどく出やすい傾向があります。
特に子どもは免疫反応が過敏に働きやすく、蚊に刺されたとき大人より強く腫れたり長引いたりすることが多いでしょう。
小児では蚊やノミなどに何度も刺されるうちに、刺されるたびに強いかゆみを伴う紅色のブツブツが出現するようになります。
この状態をストロフルス(丘疹状蕁麻疹)と呼び、虫刺されによる慢性的な蕁麻疹様の皮疹です。
ストロフルスは 小児に多い 皮膚病で、虫刺されに対する異常な過敏症反応によって繰り返し痒い丘疹が出現します。
蚊やノミ、イエダニ(ダニの一種)などの吸血昆虫が主な原因とされています。
見た目は蚊に刺された跡がたくさん集まったような赤いブツブツで、強いかゆみのため掻き壊しやすく、二次感染(とびひ)を起こす可能性も高いでしょう。
ストロフルスの症状は年齢とともに次第に軽くなり、多くは成長するにつれて数年で反応がおさまっていくとされています。
とはいえ、アトピー素因のあるお子さんなどは刺されない対策を十分行うことが大切です。
蚊アレルギー
一方、まれではありますが極端に激しい虫刺され反応を示す体質の方もいます。
代表的なのが 「蚊刺過敏症(ぶんしかびんしょう)」(蚊アレルギー) と称される症状です。
通常、蚊に刺されても掻かなければ数日で治りますが、蚊刺過敏症の人は 刺された部位がひどく赤く腫れあがり、水ぶくれや潰瘍になってしまいます。
さらに刺された部分がただれるようにかさぶた化し、その傷跡が1か月以上残ることもあります。
加えて全身的な反応(38℃以上の発熱やリンパ節の腫れ、下痢など)を伴うのも特徴です。
この蚊刺過敏症は非常に稀な疾患ですが、特に小児で報告されることが多く、その背景にはEBウイルス感染症が関連しているともいわれています。
もし「蚊に刺されただけなのに高熱が出る」「刺された箇所がひどく腫れて潰瘍状になり治りにくい」などの症状がある場合は、蚊刺過敏症の可能性があるため皮膚科専門医に相談してください。
なお、蚊に限らずハチ刺傷などでも「アナフィラキシー」と呼ばれる重度のアレルギー反応を起こす可能性があります。
アレルギー体質で虫刺されの腫れがひどい方は、抗ヒスタミン薬などの内服であらかじめアレルギー症状を抑えることも検討してください。
虫刺されによるひどい腫れへの対処法(清潔・冷却・外用薬)

刺されたあとの腫れが大きかったり強いかゆみがある場合は、以下のような応急処置を行いましょう。
患部を清潔にする
まず刺されたことに気付いたらすぐ水や石鹸で洗い流してください。
虫刺され部位を清潔に保つことで付着した汚れを除去し、炎症の悪化や細菌感染(二次感染)を防ぎます。
特に水ぶくれができて汁が出ているときは、消毒液を直接つけるより、まず石鹸と水で優しく洗浄するようにします。
患部を冷やす
次に、冷水や氷で患部を冷やすことも、腫れ・痛みを和らげるのに効果的です。
洗浄後、冷たい濡れタオルや氷嚢(氷をビニールに入れタオルで包んだもの)などを患部に当てて10~15分程度冷やしましょう。
冷却することで血管が収縮し、腫れや炎症による熱感・かゆみが軽減されます。
ただし、長時間の氷直接は凍傷の恐れがあるため避け、感覚が鈍くなるほど冷やしすぎないように注意が必要です。
掻かないようにする
強いかゆみがあるとつい掻いてしまいがちですが、絶対に掻きむしらないことが重要です。
爪で皮膚を傷つけると細菌が入り込み、とびひ(伝染性膿痂疹)や深部の皮膚感染(蜂窩織炎)を起こす恐れがあります。
かゆみがつらい場合は、後述の薬剤を使って早めに症状を鎮めるようにしましょう。
市販薬を活用する
虫刺されのかゆみ・腫れに対しては市販の塗り薬(虫刺され用クリーム)を塗るのも有効です。
いわゆるかゆみ止めには、抗ヒスタミン成分(ジフェンヒドラミンなど)やステロイド成分(ヒドロコルチゾンなど)が含まれるものがあります。
抗ヒスタミン薬は痒みの原因となるヒスタミンの作用を抑え、ステロイド外用薬は炎症そのものを鎮めてくれます。
腫れが強い方は抗ヒスタミン+ステロイド配合のクリームを使うと良いでしょう。
塗布後はできるだけ掻かずに済むよう、ガーゼで覆うか絆創膏を貼って保護すると安心です。
なお、かゆみが強くて眠れない場合などには、市販の抗ヒスタミン系のかゆみ止め内服薬(いわゆるアレルギー薬)を服用することも効果的です。
抗ヒスタミン薬の内服は眠気が出ることがあるため、薬局で購入される場合は薬剤師と相談の上、使用上の注意をよく読みましょう。
これらのセルフケアにより多くの場合は時間とともに腫れもひいていきます。
以上の対処をしても腫れや痛みがどんどん悪化する場合や、発熱・広範囲の発赤などが生じた場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
「たかが虫刺され」と油断せず、体がだるい・おかしいといった全身症状がある時も受診が必要です。
病院での治療法(ステロイド外用・内服、抗ヒスタミン薬、抗菌薬など)
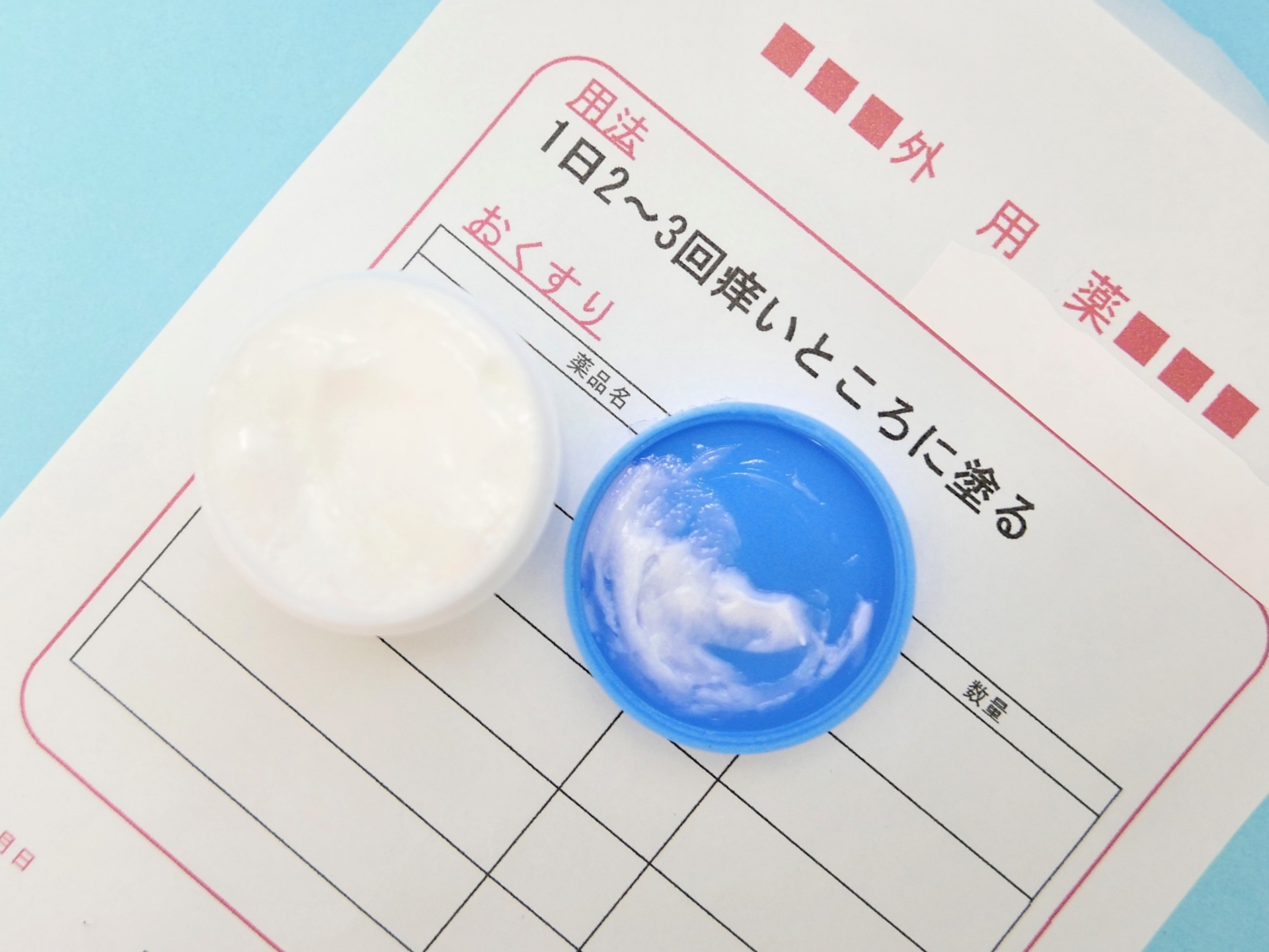
虫刺されによるひどい腫れがなかなか引かない場合や、症状が強い場合には皮膚科で治療を受けることも検討してください。
医療機関では主に次のような治療法がとられます。
ステロイド外用薬(塗り薬)
虫刺され後の強い炎症反応にはステロイド軟膏が最も効果的です。
ステロイドには強力な抗炎症作用があり、赤みや腫れ・かゆみを速やかに鎮めます。
特に遅延型のアレルギー反応で腫れが長引いている場合は、十分な強さのステロイド外用薬を1週間程度塗り続けることでかなり改善します。
病院では患部の状態に応じて強めのステロイド軟膏が処方されます。(例:モメタゾン・ベタメタゾン・ジフルプレドナート等の成分を含む処方薬)
医師の指示のもと適切に使用すれば、これらの薬で腫れ・かゆみは早期に落ち着く可能性が高いでしょう。
抗ヒスタミン薬(内服薬)
かゆみが非常に強い場合や、蕁麻疹体質で反応が出やすい方には、抗ヒスタミン薬の飲み薬が処方されることがあります。
抗ヒスタミン内服薬はアレルギー反応を抑制し、全身的にかゆみを和らげてくれます。
処方される薬には、昔からある鎮静性の抗ヒスタミン薬(d-クロルフェニラミン〔ポララミン〕等)や、眠くなりにくい新しい抗アレルギー薬(フェキソフェナジン〔アレグラ〕、オロパタジン〔アレロック〕等)があります。
ステロイド内服薬
腫れが極めて強く患部が広範囲に及ぶ場合、あるいは全身症状を伴うような場合には、ステロイドの内服(飲み薬)が用いられることもあります。
プレドニゾロン(プレドニン)やデキサメタゾン(リンデロン)といったステロイド剤を数日間内服すると、頑固な炎症も速やかに鎮静化するでしょう。
ただし副作用防止のためにも、医師の指示どおりの用法・用量で短期間だけ服用し、自己判断で途中でやめないことが大切です。
掻き壊しによって傷ができ、そこから細菌感染(二次感染)を起こしてしまった場合には、抗菌薬による治療が必要です。
虫刺されを掻いて皮膚バリアが破れると、黄色ブドウ球菌や連鎖球菌などが入り込み、とびひ(水疱や膿を伴う皮膚感染症)や蜂窩織炎(皮下組織の感染症)になることがあります。
このような合併症が疑われる場合、医師は飲み薬の抗生剤や抗生剤配合の軟膏を処方します。
アナフィラキシーへの対応
ハチ刺されなどでごくまれにアナフィラキシーショックを起こすケースがあります。
(刺された直後から全身の蕁麻疹・顔面のむくみ・息苦しさ・血圧低下などが現れる重篤なアレルギー反応)
このような緊急時には、医療機関でただちにエピネフリンの筋肉注射が行われ、呼吸循環の管理など集中治療が必要となります。
過去にハチに刺されてアナフィラキシーを起こしたことがある人には、自己注射薬のエピペンを携帯してもらい、再度刺された際に速やかに自己注射して命を守る対策も取られます。
いずれにせよ、虫刺されによる症状が皮膚の範囲を超えて全身に及ぶ場合(めまい・息苦しさ・嘔吐・全身の蕁麻疹など)は迷わず救急受診してください。
多くの場合、適切な外用薬の使用で虫刺されの腫れやかゆみは治まります。
医師の指示に従い治療を続ければ、ひどい腫れも1週間程度で改善することが期待できます。
症状が軽快してきても自己判断で薬を中断せず、最後まで使い切るようにしましょう。
関連記事:オンライン診療における処方箋のもらい方をわかりやすく解説
特に注意すべき虫(蚊、ブヨ、ダニ、ノミ、ムカデ、ハチ)
虫刺されと一口にいっても、様々な種類の虫(正確には昆虫やダニなど節足動物)が関与します。
その中でも、腫れやすい・症状が重くなりやすい虫、あるいは刺されないよう特に注意したい虫について解説します。
蚊(カ)
最も身近な吸血虫です。日本にはヒトスジシマカやアカイエカなど約100種類以上の蚊が生息します。
蚊に刺されると、刺された瞬間からかゆみと膨疹を生じる即時型反応と、数時間~翌日にかけて赤く硬い腫れが出現する遅延型反応の両方が現れることがあります。
通常は数時間~数日で治まる軽い症状ですが、前述したようにアレルギー体質の人では刺された箇所がゴルフ球大に腫れることもあります。
掻き壊すととびひなどになる恐れがあるため要注意です。
また蚊はかゆみだけでなく、デング熱や日本脳炎などのウイルス感染症を媒介する場合もあります。
海外渡航時や夏場の山林・沼地では蚊に刺されない対策が特に重要です。
ブヨ(ブユ)
ブヨはブユとも呼ばれる小型の吸血性のハエの仲間で、渓流や山間部に多く生息します。
刺されている最中は痛みを感じにくいですが、半日~翌日経ってから激しいかゆみと赤い腫れが出てくるのが特徴です。
ブヨの唾液には毒素が含まれており、皮膚に強い炎症を起こします。
刺された箇所は直径1cm以上に赤く腫れ上がり、痛みや熱感を伴うこともあります。
症状は通常1~2週間かけて徐々に改善しますが、人によっては1ヶ月以上かゆみ・腫れが続く可能性もゼロではありません。
山間部や渓流で活動する際は肌を露出しないようにし、虫除けスプレーも活用しましょう。
ダニ(マダニ)
ダニは8本足の節足動物(クモの仲間)で、家の中にいるイエダニから野外のマダニまでさまざまな種類がいます。
屋内ではネズミなどに寄生するイエダニが布団や畳に潜み、人間を吸血することがあります。
イエダニに刺されると、腹部や太もも内側など衣服に隠れる柔らかい部分に赤く小さな硬いシコリができ、強いかゆみが数日~1週間続きます。
一方、屋外の草むらに生息するマダニ類に咬まれた場合、皮膚にダニが頭部を埋め込んで吸血するため、気付かずにいると長時間吸いつかれてしまいます。
マダニに刺された部位は赤く盛り上がり、場合によっては中央に噛まれた痕(黒い点)を残すことがあります。
無理に引き剥がすと口器が皮膚内に残って炎症が悪化するため、マダニが食いついて離れない場合は無理せず医療機関で除去してもらってください。
さらにマダニは刺すだけでなく、ライム病や日本紅斑熱、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)などの深刻な感染症を媒介することでも知られます。
野山や草むらに入った後はシャワーで体を洗い、ダニが付着していないかチェックしましょう。
ノミ
ノミはネコノミやイヌノミなどペットに寄生する吸血昆虫ですが、人間も刺されることがあります。
ノミに刺されると、その場では気付きにくいものの1~2日後になってから強いかゆみと赤い発疹が現れるのが典型です。
小さな赤いブツブツが多発し、水ぶくれになることもあります。
特にノミが跳びはねて衣服の隙間から侵入した場合、足首周りや下腿など床に近い部分が集中的に刺される傾向があります。
ノミ刺されも掻き壊すと二次感染しやすいため注意しましょう。
家でペットを飼っている場合、ノミの繁殖を防ぐためペットのノミ駆除や寝具・絨毯のこまめな清掃が重要です。
ムカデ
ムカデは大型の多足類で、暖かい季節になると家屋内や庭先にも侵入してきます。
ムカデに不用意に触れたり踏んだりすると、防衛本能で鋭い顎(毒牙)で咬まれます。
ムカデに咬まれた直後から、その毒液の作用で刺された箇所に激痛が走るでしょう。
患部はビリビリと痺れるような痛みとともにみるみる赤く腫れ上がるのが特徴です。
二つの噛み跡がくっきり残り、強い場合は水ぶくれや内出血を伴うこともあります。
ムカデの毒はタンパク質分解酵素などを含むため、咬まれた直後に熱いお湯(50℃程度)をかけると毒成分を不活化できるといわれています。(応急処置の一つです)
痛みは数時間で徐々に和らぎますが、腫れや違和感は数日~1週間程度残ることがあります。
ムカデに咬まれた場合、市販のステロイド系鎮痛消炎軟膏を塗り、様子を見ることも有効です。
激しい痛みが続く場合や広範囲に腫れが強い場合は受診しましょう。
まれにムカデの咬傷でも全身のじんましんや息苦しさ(アナフィラキシー症状)を生じる人がいるため、気分不良など全身兆候があればすぐ医療機関へ向かってください。
ハチ
ハチ(蜂)は毒針を持つ昆虫で、ミツバチ・アシナガバチ・スズメバチなどが代表です。
ハチに刺されると、針が刺さった瞬間に強烈な痛みを感じ、その後数分以内に刺された部分の皮膚が赤く腫れ上がってきます。
ハチ毒による激しい刺激で周囲は熱感を伴い、かなり大きな腫れとなることも珍しくありません。
通常、この局所反応(刺された部位の腫れ・痛み)は数時間~数日かけて治まります。
ただしハチに関して特に注意すべきはアレルギー反応です。
ハチに複数回刺されているうちに体質的にハチ毒に対する抗体ができてしまい、ある日刺された際に突然全身性のアレルギー(ハチ毒アレルギー)を発症することがあります。
ハチ毒アレルギーになると、刺された直後から刺傷部位以外にもじんましんや唇の腫れ・息苦しさ・嘔吐などのアナフィラキシー症状を起こし、適切な処置をしないと命に関わる危険があります。
過去にハチに刺されて体調不良になったことがある人は、次に刺されたときアナフィラキシーになるリスクがあるため、事前に医療機関で血液検査(ハチ毒抗体検査)を受けておくのも良いでしょう。
また山中や公園でハチに遭遇した際は、刺激しないよう静かにその場から離れましょう。(不用意に手で払ったり大声を出すと攻撃される恐れがあります)
巣に近づかないのは言うまでもありません。
以上のように、それぞれの虫によって刺されたときの症状や注意点が異なります。
腫れ方が特に強い虫としては、ブヨやムカデ・スズメバチなどが挙げられます。
またダニやノミは知らぬ間に何箇所も刺されて症状が遅れて出ることが多いため、「原因不明の痒いブツブツ」ができた場合はこれらを疑ってみる必要があります。
いずれの場合も掻き壊さないことが鉄則です。
症状が長引いたりおかしいと感じたら皮膚科に相談しましょう。
オンライン診療の活用(オンラインメディカルクリニック紹介)

虫刺されによる腫れが心配だけれど忙しくて病院に行けない、近くに皮膚科がない、といった場合はオンライン診療を利用する方法もあります。
近年はスマートフォンやパソコンを使って、自宅にいながら医師の診察を受けられるオンライン診療サービスが普及しています。
オンライン診療ではビデオ通話で医師に患部を見せたり、事前に患部の写真を送ったりすることで診察が可能です。
医師が症状を確認した上で必要な薬を処方し、自宅近くの薬局でその処方箋を受け取ったり、自宅へ配送を依頼したりできるでしょう。
症状を説明する問診や画像の撮影など多少の準備は必要ですが、移動時間もなく待ち時間も少ないため忙しい方にはありがたいですね。
保険適用で受診できるオンラインクリニックも増えてきています。
症状が比較的軽く緊急性はないが専門家のアドバイスが欲しい、といった場合にオンライン診療を活用してみるのも一つの方法でしょう。
ただし、呼吸困難などの緊急症状がある場合は迷わず救急車を呼ぶなど対面診療を受けてください。
まとめ
虫刺されによる腫れがひどいと不安になりますが、その多くはアレルギー反応による一時的なものです。
即時型反応と遅延型反応があり、特にアレルギー体質の方や小さなお子さんでは大きく腫れることがあります。
まずは慌てずに、刺された箇所を洗って清潔にし、冷やして様子を見ることが大切です。
かゆみが強い場合は市販のかゆみ止めなどで早めに対処し、絶対に掻き壊さないようにしましょう。
多くの場合、適切に処置すれば徐々に腫れも引いてきます。
腫れがなかなか治まらない時や、水ぶくれがひどく化膿してしまった場合には皮膚科で相談してください。
ステロイド外用薬や抗ヒスタミン薬の使用でほとんどは改善します。
蜂に刺されて息苦しいなどの全身症状が出た場合は、緊急事態であるため、ためらわず救急車を呼ぶようにしてください。
また虫刺され自体を予防することも重要です。
野外に行くときは長袖・長ズボンを着用して肌の露出を減らしたり、虫除けスプレー(忌避剤)を使ったりといった対策が欠かせません。
室内ではダニやノミ対策として寝具のこまめな洗濯清掃や害虫駆除を行いましょう。
監修医
島村泰輝
- 2012年3月 名古屋市立大学医学部 卒業
- 2014年4月 名古屋市立大学放射線科 入職
- 2015年4月 名古屋市立大学大学院博士課程入学 (専攻:生体防御・総合医学分野)
- 2019年3月 同大学院卒業、博士号取得
- 2019年6月 株式会社エムネス 入職
- 2022年10月 同 Medical Professional Service(医師部門)副本部長
- 2023年7月 オンラインメディカルクリニック開業
愛知県名古屋市出身。遠隔放射線画像診断を行う傍ら、AI開発、メディカル用プロダクト開発を行う。
医療としてはその他にも内科診療、訪問診療にも従事。医療はITでさらに良くなる事を信条として様々な取り組みを行う。
物理的、時間的に医療が届きにくい層に対して医療を届けるべくオンライン診療を中心としたクリニックを開業。今後は各種専門家とともに、遠隔地であっても質の高い医療を提供するサービスを構築していく。