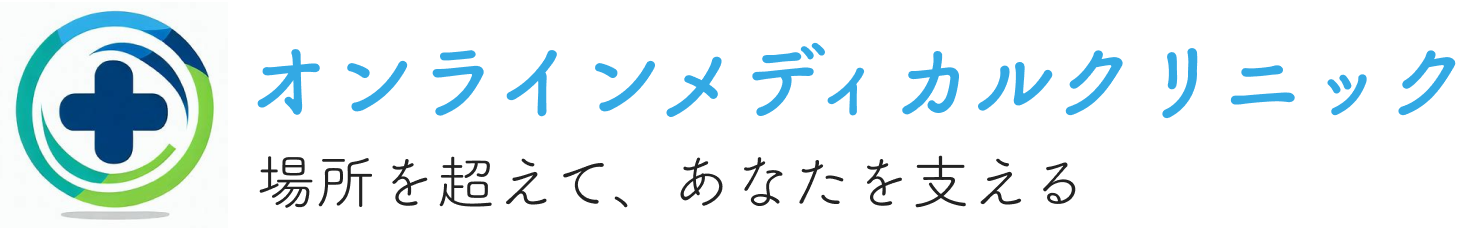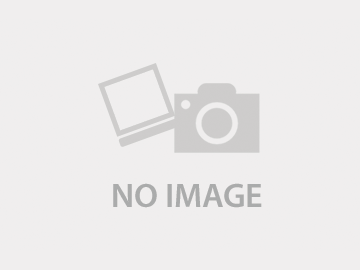病院での待ち時間が長く、負担に感じている人は少なくありません。
実際、病院へのクレームでもっとも多い内容は「待ち時間の長さ」であり、予約を入れたのに長時間待たされた経験を持つ人も多いでしょう。
忙しい人や体調不良の人にとって、長時間待合室で座って待つことは大きなストレスになります。
また、長い待ち時間のせいでイライラが募り、診察を諦めて帰ってしまう患者さんもいるといわれます。
本記事では、病院の待ち時間が長くなる理由や待ち時間を減らす工夫、さらに待ち時間ゼロで診察を受ける方法として注目されるオンライン診療について解説します。
病院の待ち時間が長い理由
病院で待ち時間が長くなってしまう主な理由は以下のとおりです。
患者数が多い
来院する患者さんの数が単純に多いと、その分だけ待ち時間も長くなります。
特に大学病院のような大きな病院では、一日の来院数が多く、一人ひとりにかかる診察・治療時間も長くなりがちです。
患者側も「同じ医療費なら大きい病院で診てもらいたい」という思いから、軽い症状でも大病院に集まりがちで、結果的に外来が混雑して待ち時間が長くなる傾向があります。
また、診察の内容によって診る時間が変わることも、待ち時間を押し延ばす要因です。
高齢の患者さんや症状の重い患者さんほど医師が丁寧に診察するため、一人当たりの診察時間が長くなる傾向があります。
急患対応で順番が前後する
予約をしていても、緊急の対応が必要な患者(急患)が来た場合には、診察の順番が入れ替わることがあります。
小規模なクリニックや小児科でも、症状が重い患者さんを優先するため、後から来た人に先に診察するケースがあり得ます。
これは患者の安全のためには当然ですが、事情を知らない患者さんにとってはストレスにつながります。
そのため、急患対応で順番が前後する場合は、事前に伝えるなどして不満を和らげる工夫も必要です。
検査や処置に時間がかかる
診察中に行われる検査や処置の結果待ちも、待ち時間が長くなる一因です。
たとえば採血検査では、遠心分離や測定装置での分析に30分〜1時間程度かかり、その結果を待って再度診察室で説明を受けるまで順番が進まないことがあります。
また、予約時間に遅れて来院した患者さんがいると順番が前後する場合もあり、予約していても予定通りに進まないケースがあります。
さらに、電話予約の対応など事務作業にスタッフが追われていると、受付や会計が滞り待ち時間に影響することもあります。
以上のように、患者数の多さや診療内容の性質、緊急対応の発生、検査結果待ちなど様々な要因が重なって病院の待ち時間は長くなります。
病院側では予約制の導入や人員配置の工夫など、待ち時間を短縮するための努力が行われています。
次章では、患者側から見た「待ち時間を避けやすいタイミング」について紹介します。
関連記事:ストレスによる頭痛の原因と対策|セルフケアや薬で解消する方法
病院が混雑しやすい時間帯と曜日
「少しでも待ち時間を短くしたい」という場合、病院が混みやすい曜日や時間帯を知っておくと役立ちます。一般的に以下のような傾向があります。
ただし、あくまで一般論であり、地域や病院によって実情は異なるため参考程度にお考えください。
曜日ごとの傾向
もっとも混雑しやすい曜日は月曜日と土曜日だといわれています。
月曜日は週末明けで患者が集中しやすく、土曜日は仕事や学校が休みの人が受診に来るため一週間で最も混み合う傾向があります。
特に休日明けの月曜午前中は非常に混雑し、逆に休み明けではない火曜日は比較的空いていることが多いようです。
多くの医院では水曜か木曜を休診日にしているため、その翌日の午前中(木曜休みなら金曜午前など)もやや混み合います。
一方、火曜日は週の中でも患者数が少なく、どの病院でも一日を通して空いていることが多い狙い目の曜日とされています。
時間帯ごとの傾向
午前の10~11時頃や午後の16~17時頃は患者さんが多く混雑しやすい時間帯です。
一方、朝一番の受付直後や診療終了間際の時間帯は意外と空いている場合があります。
例えば午前診療が始まる直後や、お昼前ギリギリの時間、また午後診療開始直後などは比較的待ち人数が少ないことが多いです。
ただし、病院の立地によってはお昼休み前の時間帯に近隣オフィスの人が駆け込んで混雑するケースもあるため注意が必要です。
夕方の終了間際も駆け込みの患者が少なければ待ち時間は短くなる傾向があります。
季節やタイミングによる混雑
大型連休の前後や年末年始明けは患者が集中し、非常に混雑します。
ゴールデンウィーク、お盆、正月休みの後は、休み中に我慢していた人が一斉に受診するため行列ができるほど混み合うことが多いため要注意です。
また、季節的な流行による混雑もあります。
例えばインフルエンザが流行する冬場や花粉症シーズンの春は、それぞれ内科や耳鼻科が普段より混みやすくなります。
予防接種の時期や感染症の流行期には問い合わせの電話や来院数が増え、結果として待ち時間が長くなる傾向があります。
以上は一般的にいわれる混雑の傾向ですが、繰り返しになりますが実際の混み具合は病院や地域によって異なります。
いつも通っている病院であれば、受付の方に「空いている曜日や時間帯」を聞いてみるのも良いでしょう。
自分のスケジュールと照らし合わせて、できるだけ待ち時間が少なそうな日時を選ぶ工夫ができます。
病院の待ち時間の過ごし方
どうしても避けられない待ち時間を有意義に使う工夫も大切です。
待合室での過ごし方を工夫すれば、ストレスを軽減したり時間を有効活用できます。
以下に、待ち時間の代表的な過ごし方を紹介します。
スマホやタブレットの使用
スマートフォンやタブレットは、病院の待ち時間を潰す強い味方です。
インターネットに接続してニュースやSNSを閲覧したり、動画を視聴したり、ゲームで遊ぶなど様々な方法で暇つぶしができます。
具体的には、「今日の夕飯の献立を考える」「ネットショッピングで日用品を注文する」「電子書籍で本や漫画を読む」など、スマホ一つで多彩なことが可能です。
実際20年以上の通院経験を持つブロガーも、待ち時間には主にスマホで電子書籍を読んだり買い物をしたりして過ごしているといいます。
また、スマホのメモ機能を使って診察時に医師に聞きたいことを整理しておくのもおすすめです。
長い待ち時間を耐えて受診するからには、聞きたいことを事前にメモしておくことで診察を有意義なものにできます。
このようにスマホを有効活用すれば、待っている間に用事を済ませたり情報収集したりと時間を有効に使えるでしょう。
読書をする
スマホ以外の過ごし方として定番なのが読書です。
あらかじめ本や雑誌を持参しておけば、待合室で静かに読書をして過ごせます。
荷物を増やしたくない場合は、小さくて軽い文庫本がおすすめです。
文庫本であれば鞄に入れても負担になりにくく、途中で呼ばれて中断しても栞を挟んでおけば続きは自宅で読むことができます。
最近では電子書籍リーダーを持参して読書を楽しむ人もいます。
本を読むことに集中していれば、待ち時間のイライラも紛れてあっという間に時間が経つでしょう。
仮眠をとる
体調が悪い中での長い待ち時間であれば、思い切って仮眠をとるのも一つの方法です。
特に、仕事や育児で日頃から疲れている人にとっては、待合室で呼ばれるまでのわずかな時間でも休息になるでしょう。
実際、待合室で順番を待ちながら目を閉じて休んでいる患者さんも見受けられます。
仮眠をとる際のコツは、できるだけ診察室の近くの席に座ることです。
何度呼ばれても気づかず眠ってしまうと看護師さんに起こしてもらう手間をかけてしまうため、自分の順番が来たらすぐ気付ける位置で休むようにしましょう。
軽く目を閉じて体を休めれば、その後の診察にも少し余裕を持って臨めるかもしれません。
ただし、呼び出しを聞き逃さないよう注意は必要です。
病院の待ち時間なしで診察を受けるならオンライン診療
「どうしても待ち時間が苦痛だ」「忙しくて病院に行く時間がない」と感じる方は、オンライン診療を検討してみるのも手です。
オンライン診療を利用すれば、自宅や職場からスマホやパソコンを通じて医師の診察が受けられ、病院で長時間待つ必要がなくなります。
ここではオンライン診療とは何か、そのメリットや対応できる症状、利用方法について解説します。
オンライン診療とは
オンライン診療とは、病院に行かなくてもスマートフォンやタブレットのカメラ機能等を使って医師の診察を受けられるサービスのことです。
インターネットを通じて医師とリアルタイムにビデオ通話を行い、症状の相談や診療、処方箋の発行まで行います。
オンライン診療最大のメリットは、待ち時間と通院時間の大幅な短縮にあります。
たとえば地方在住のある患者さんは、オンライン診療を活用して通院にかかっていた時間を3時間から10分程度にまで短縮できたケースも報告されています。
自宅にいながら予約した時間に診察してもらえるため、病院で順番を待つ時間だけでなく往復の移動時間も節約できます。
特に「薬をもらうだけの通院」や「いつもの持病の定期受診」の場合はオンライン診療に切り替えることで、時間的な負担が大きく減るでしょう。
ただし、オンライン診療は通信環境と端末が必要になりますし、対面診療に比べて医師が直接触診や検査をできない制約もあります。
そのため症状によってはオンラインより直接受診が適している場合もありますが、まずは「待ち時間がゼロ」という大きな利点があることを押さえておきましょう。
オンライン診療で対応できる症状
オンライン診療では、比較的軽症のものや経過観察中の慢性疾患など、幅広い科目・症状に対応しています。
具体的には、内科全般(風邪・発熱・頭痛・腹痛・下痢など)、小児科の急な発熱や咳、皮膚科の発疹・かゆみ、アレルギー科の花粉症、精神科のメンタルヘルス相談、生活習慣病の継続治療など、多くの分野でオンライン診療が活用されています。
例えばあるオンライン診療サービスでは、内科・小児科・心療内科(精神科)・皮膚科・アレルギー科・泌尿器科・産婦人科といった科に対応しており、症状でいえば風邪症状から慢性疾患の相談までカバーしています。
一方で、オンライン診療に適さない症状もあります。
骨折や脱臼、ひどい火傷や深い切り傷、重度の感染症など、直接触れて診察・処置をしなければならないケースではオンライン診療では対応できません。
また、胸痛や激しい腹痛など緊急の鑑別が必要な症状もオンラインより救急受診が望ましいでしょう。
多くのオンライン診療サービスや医師側でも「画面越しで診るのが難しい」と判断した場合は対面診療を勧められることがあります。
現在は新型コロナの影響もあり初診からオンライン診療が可能になっていますが、症状によっては途中で対面診療へ切り替わるケースもある点は理解しておきましょう。
オンライン診療の利用方法と流れ
オンライン診療を受けるまでの一般的な流れを紹介します。基本的には次のステップで進みます。
1.サービスの選択と予約
まずオンライン診療に対応した医療機関やプラットフォームを選びます。
専用のスマホアプリやウェブサイトからアカウント登録し、希望する日時に診察予約を行います。
【例】オンラインメディカルクリニックの場合、PCやスマホから簡単に予約可能で、平日夜間も対応しています。
2.事前問診の入力
予約後、診察前に症状や既往歴に関する問診票をオンライン上で入力するケースが多いです。
現在の症状や服用中の薬などを事前に伝えておくことで、当日の診察がスムーズになります。
3.オンライン診察
予約した日時になったら、スマホやパソコンで医師とビデオ通話をつないで診察開始です。
医師から症状や経過について質問を受け、画面越しに患部を見せたりしながら診察が進みます。
対面と違って触診などはできませんが、必要に応じて画面に患部を近づけて見せる、写真を送るといった工夫で情報提供します。
診察自体の所要時間は症状にもよりますが5〜10分程度で、対面の「診察待ち」に比べて非常に短時間で完了します。
4.会計・処方
診察後、医師が電子的に処方箋を発行します。
保険診療の場合はその処方箋が指定した薬局に送付されるので、患者さんは後ほど薬局に行って薬を受け取ります。
オンライン診療サービスによっては、処方箋を自宅に郵送したり、調剤薬局から自宅へ薬を宅配してもらうことも可能です。
場合によっては医師の診察後に薬剤師によるオンライン服薬指導も受けられ、最短当日中に処方薬が宅配されるため薬局で待つ必要もありません。
支払いはクレジットカード決済やオンライン決済で行い、診療代や薬代の自己負担分のほか通信料等(※サービスにより数百円程度)を合わせて精算します。
以上が一般的なオンライン診療の利用フローです。
初診料や薬代以外にかかるシステム利用料はサービスごとに異なりますが、概ね保険診療の場合で数百円程度です。
オンライン診療を利用すれば、自宅や職場に居ながら自分の都合の良い時間に診察を受けられるため、忙しい方や子育て中で外出が難しい方にも適した受診形態と言えるでしょう。
関連記事:オンライン診療を快適に受けるには
オンラインメディカルクリニックでは初診からオンラインで診療
最近ではオンライン診療専門のクリニックも登場しています。
その一つがオンラインメディカルクリニックです。
オンラインメディカルクリニックでは、初診から継続診療まですべてオンラインで行えるのが特徴で、待ち時間は一切ありません。
平日夜20時まで診療対応しており、PC・スマホからいつでも予約可能で、忙しい方でも自分の空いた時間に受診できます。
診察は専用アプリを使って行い、予約から診療までオンライン上で完結します。
診療後は処方箋を患者の希望する薬局に直接送付してくれるため、患者さんはその薬局で薬を受け取るだけです。
(希望すれば処方箋をご自宅に郵送して自分で受け取ることも可能です。)
保険診療に対応しており各種医療証も利用でき、通常の対面診療と同様に健康保険を使った受診ができます。
オンラインメディカルクリニックでは特に漢方内科や一般内科のオンライン診療メニューが充実しており、頭痛・腹痛・高血圧・ニキビ・花粉症など様々な症状に対応しています。
気軽に相談できるチャットサポートもあり、オンラインでも患者が安心して治療を受けられる工夫がなされています。
もしオンライン診療中に「これは直接診た方がいい」と医師が判断した場合は、希望する医療機関での対面診療に速やかに繋げるための調整も行ってもらえるため安心です。
このように、オンライン診療に特化したクリニックを利用すれば、初めての診察から薬の受け取りまで自宅にいながら完結でき、長い待ち時間とは無縁のスムーズな医療体験が可能になります。
関連記事:オンライン診療における処方箋のもらい方をわかりやすく解説
まとめ
病院の待ち時間が長い理由には、患者数の多さや急患対応、検査待ちなど様々な要因があります。
混雑しやすい曜日・時間帯を避けたり、待ち時間中の過ごし方を工夫することで、多少なりともストレスを減らすことができるでしょう。
例えば火曜日の朝一番に受診してみたり、待っている間はスマホで情報収集をする、好きな本を読むなどして有効活用するのがおすすめです。
しかし、それでも長時間の待ち時間がつらい場合は、オンライン診療という選択肢があります。
オンライン診療を利用すれば自宅で待ち時間ゼロの診察が可能で、忙しい人や体調不良で移動が大変な人にとって大きな助けとなります。
オンラインメディカルクリニックのように初診からオンライン対応の医療機関も登場し、医療の受け方はますます多様化しています。
病院で長く待たされてうんざりした経験がある方は、本記事で紹介した対処法をぜひ試してみてください。
ちょっとした工夫や新しいサービスの活用で、「待つ苦痛」を減らし、必要な医療をスムーズに受けられるようになるでしょう。
自分の健康と時間を大切に、賢く受診していきましょう。
監修医
島村泰輝
- 2012年3月 名古屋市立大学医学部 卒業
- 2014年4月 名古屋市立大学放射線科 入職
- 2015年4月 名古屋市立大学大学院博士課程入学 (専攻:生体防御・総合医学分野)
- 2019年3月 同大学院卒業、博士号取得
- 2019年6月 株式会社エムネス 入職
- 2022年10月 同 Medical Professional Service(医師部門)副本部長
- 2023年7月 オンラインメディカルクリニック開業
愛知県名古屋市出身。遠隔放射線画像診断を行う傍ら、AI開発、メディカル用プロダクト開発を行う。
医療としてはその他にも内科診療、訪問診療にも従事。医療はITでさらに良くなる事を信条として様々な取り組みを行う。
物理的、時間的に医療が届きにくい層に対して医療を届けるべくオンライン診療を中心としたクリニックを開業。今後は各種専門家とともに、遠隔地であっても質の高い医療を提供するサービスを構築していく。