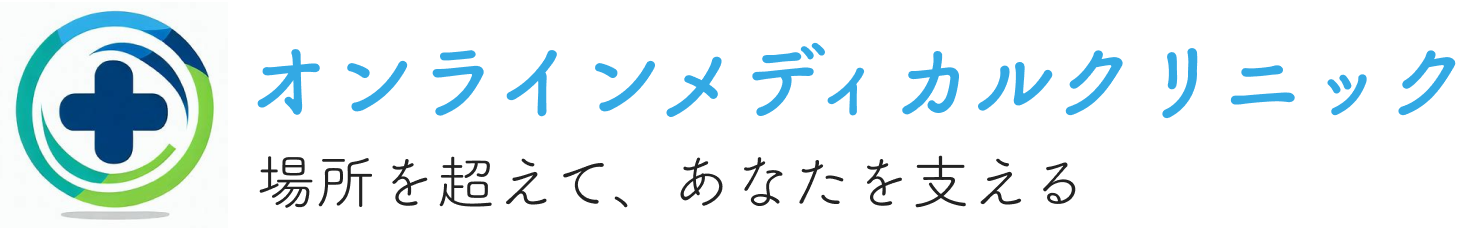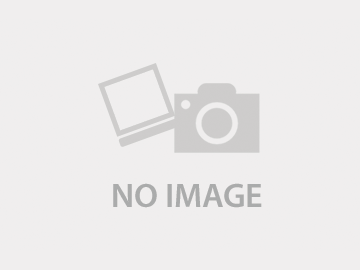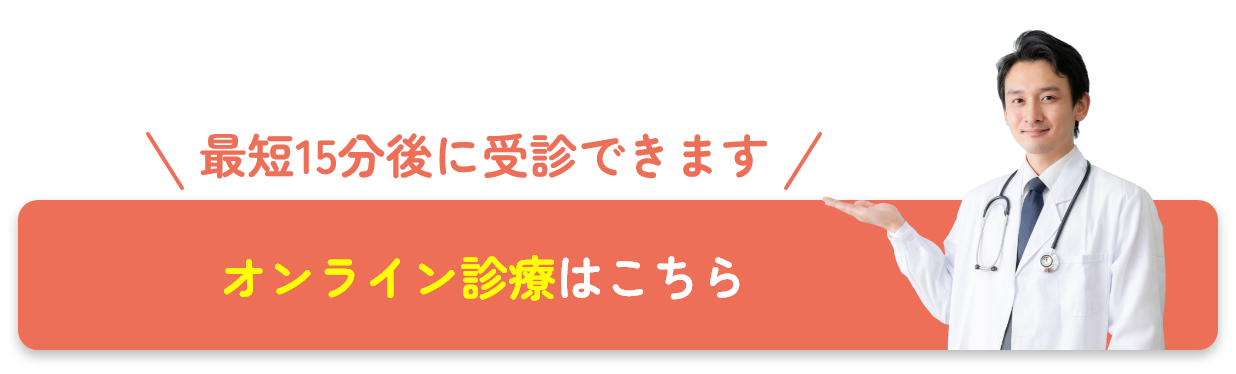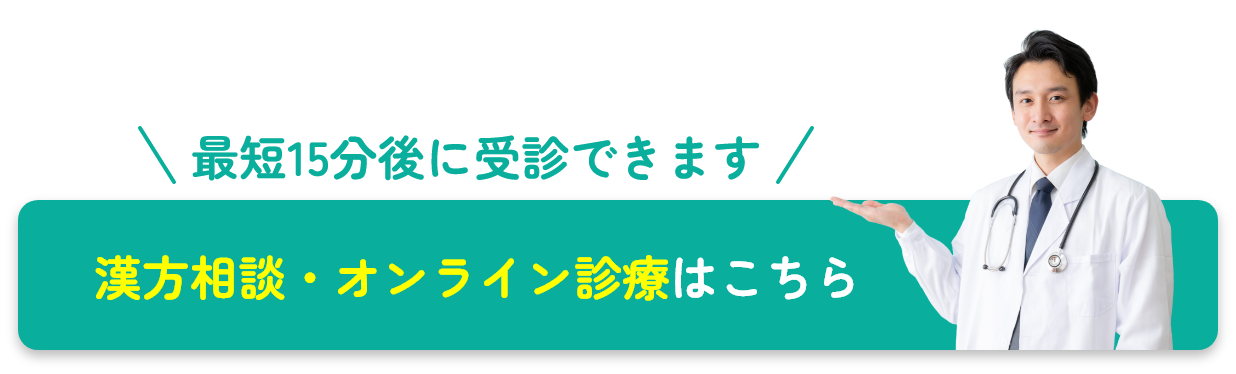アレルギー性鼻炎は季節を問わず多くの人が悩まされる病気です。
ダニや花粉などのアレルゲンに対する免疫の過剰反応によって鼻の粘膜に炎症が起こり、くしゃみ・鼻水・鼻づまりの“三大症状”を引き起こします。
近年患者数が増加傾向にあり、日本では有病率がおよそ4~5割に達するとの報告もあります。
これらの症状が長引くと日常生活に支障をきたすこともあり、現代ではアレルギー性鼻炎は「国民病」とも称されています。
本記事では、アレルギー性鼻炎の症状の特徴や季節性・通年性の違い、他の病気(風邪・副鼻腔炎)との違い、そして症状を和らげるための薬の種類や予防策について具体的に解説します。
ご自身やご家族の症状改善のヒントとして、ぜひ最後までお読みください。
アレルギー性鼻炎とは?
アレルギー性鼻炎とは、花粉やハウスダスト(ダニの死骸やフン、ホコリ)などのアレルゲンが鼻から侵入した際に、体の免疫反応が過剰に働いて起こる鼻の炎症性疾患です。
本来無害な物質に対して免疫が誤って反応してしまうことで鼻粘膜が炎症を起こし、くしゃみ・水様鼻汁(透明なさらさらした鼻水)・鼻閉(鼻づまり)といった症状が引き起こされます。
アレルギー性鼻炎には季節性(特定の季節に花粉で発症するもの、いわゆる花粉症)と通年性(一年を通してダニやホコリで発症するもの)の2タイプがあります。
この病気は年々患者数が増えており、日本では2019年の疫学調査で有病率49.2%と報告されるなど、非常に一般的な疾患です。
症状が長引く場合はQOL(生活の質)が著しく低下し、日常生活や仕事・学業への支障も大きくなります。
アレルギー性鼻炎そのものは命に関わる病気ではありませんが、慢性的な鼻づまりによる睡眠障害や集中力低下を招いたり、喘息や副鼻腔炎などを合併して症状が悪化することもあります。
そのため、アレルゲンの特定と適切な対策・治療によって症状をコントロールすることが大切です。
関連記事:夏バテを即効治すことはできる?つらい症状を軽くする食べ物と飲み物
アレルギー性鼻炎の主な症状
アレルギー性鼻炎では、鼻を中心にさまざまな症状が現れます。
典型的な症状はくしゃみ発作、透明な鼻水、鼻づまりの3つですが、それ以外にも喉や目などに症状が及ぶことがあります。
本章では症状を「鼻症状」「咽頭症状」「その他の症状」に分けて説明します。
鼻症状
アレルギー性鼻炎の鼻症状として最も代表的なのが、繰り返し出るくしゃみ、水のように透明な鼻水(鼻漏)、そして頑固な鼻づまり(鼻閉)です。
アレルゲンに曝露されると発作的に何度もくしゃみが出て、大量のさらさらした鼻水が流れ、鼻粘膜の腫れによって息苦しい鼻づまりを生じます。
これらの症状は特に朝起床時やアレルゲンに触れた直後に強く現れる傾向があります。また、鼻の中のかゆみやムズムズする違和感を伴うこともよくあります。
鼻水は風邪のときにも出ますが、アレルギー性鼻炎ではほとんどが無色透明でさらさらしている点が特徴的です。
一方、風邪などウイルス感染の場合は初期こそ透明でも、症状が進むと白く濁ったり黄色や緑色の粘っこい鼻汁に変化することがあります。
鼻水の性状でもある程度アレルギーかどうかを見分けることができます。
いずれにせよ、透明な鼻水が長く続く場合や、鼻づまりで十分に鼻呼吸ができない状態が続く場合はアレルギー性鼻炎の可能性が高いでしょう。
咽頭症状
喉の症状としては、アレルギー性鼻炎では喉のかゆみやイガイガした違和感が出ることがあります。
特に花粉症の方は目や鼻だけでなく喉の粘膜にもアレルギー反応が及び、喉がむずむずして掻きたくなる感じを訴えることがあります。
また、鼻水が喉に滴り落ちる後鼻漏のために喉が刺激され、乾いた咳が出る場合もあります。
鼻づまりで口呼吸になることで喉が乾燥し、痛みや違和感を生じることもあります。
これらの咽頭症状は風邪の咽頭炎による喉の痛みとは少し異なり、強い痛みよりも「かゆい」「イガイガする」といった感覚が中心です。
ただしアレルギー症状が長引いて粘膜の炎症が強くなると、二次的に咽頭炎や気管支炎を併発して喉の痛みや湿った咳が出てくることもありえます。
喉の症状が強い場合は、アレルギーだけでなく他の感染症の可能性も考えておく必要があります。
その他の症状
アレルギー性鼻炎では鼻と喉以外にも様々な付随症状が現れることがあります。
代表的なのは目のかゆみ・涙目・充血で、アレルギー性結膜炎を合併している状態です。
特に花粉症では約7~8割の患者で目の症状(目のかゆみ・異物感・充血・涙)が見られるとされ、鼻症状とともに目の不快感に悩まされることが多いです。
また耳のかゆみや耳閉感(耳がこもる感じ)も起こることがあり、これはアレルギーによる耳管(中耳と喉をつなぐ管)の機能障害によるものです。
全身的な症状としては、頭が重い感じ(頭重感)や集中力の低下、倦怠感を訴える人もいます。
鼻づまりによる睡眠不足や酸素不足が原因で頭痛が生じるケースもあります。
さらに、慢性的な口呼吸によって喉が乾燥するといびきや睡眠の質の低下につながり、日中の疲労感を感じやすくなることもあります。
アレルギー症状が強い季節には鼻・目・喉以外にもこのような不調が出現し、日常生活の質が損なわれることがあります。
以上のように、アレルギー性鼻炎の症状は鼻の三大症状を中心に多岐にわたります。
ただ、症状の出方や程度は個人差が大きく、花粉症シーズンだけつらい人もいれば一年中軽い症状が続く人もいます。
次の章では、季節性(花粉症)と通年性のアレルギー性鼻炎の違いについて詳しく見てみましょう。
アレルギー性鼻炎の季節性と通年性の違い
一口にアレルギー性鼻炎と言っても、その発症時期や原因アレルゲンによって2つのタイプに分類されます。
季節性アレルギー性鼻炎と通年性アレルギー性鼻炎です。
それぞれ何が原因で起こり、どのような特徴があるのかを解説します。
季節性アレルギー性鼻炎
季節性アレルギー性鼻炎とは、特定の季節にだけ症状が現れるタイプのアレルギー性鼻炎です。
一般には花粉症と呼ばれており、その名のとおり花粉が主な原因になります。
日本で代表的なのは春先のスギ花粉症で、スギ花粉は2~4月頃に飛散し、その時期にくしゃみ・鼻水・鼻づまり・目のかゆみなどの症状が集中して起こります。
スギ以外にもヒノキ花粉(3~5月)、ブタクサやヨモギなど秋の雑草花粉(8~9月)でも季節性の鼻炎症状が出ます。
要するに、花粉が飛ぶ季節にだけアレルギー性鼻炎を発症するのが季節性タイプです。
季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)の症状は、前述の三大症状に加えて目の痒みや充血、喉や皮膚の痒みなど多彩になりやすいことが知られています。
大量の花粉を吸い込むことで鼻以外の粘膜や皮膚にもアレルギー反応が起こり、目の充血・涙目や肌荒れを伴うケースもあります。
症状が出る期間は花粉の飛散時期に限定され、例えばスギ花粉症なら例年2月から4月頃まで症状が続き、その後は治まります。
ただし、飛散量の多い年は症状が長引いたり、複数の花粉(スギとヒノキ、あるいはイネ科とブタクサなど)に反応する場合は春と秋の二季節に症状が出ることもあります。
通年性アレルギー性鼻炎
通年性アレルギー性鼻炎とは、一年中いつでも症状が現れるタイプのアレルギー性鼻炎です。
その主な原因はダニ(ハウスダスト)や室内塵で、これらのアレルゲンは季節に関係なく家庭内に存在するため、通年にわたって鼻炎症状を引き起こします。
ダニは温度・湿度の高い環境で繁殖しやすく、特に日本では夏から初秋(8~9月)にダニ数が増えるためその時期に症状悪化しやすいと言われます。
しかし基本的には年間を通してアレルゲンにさらされる可能性があるため、季節に関係なく慢性的な鼻炎に悩まされるのが通年性タイプの特徴です。
通年性アレルギー性鼻炎の症状は、ほこりっぽい部屋に入った時や布団を干した時などに発作的にくしゃみや鼻水が出るといった形で現れることが多いです。
季節性に比べると症状はやや持続的で慢性副鼻腔炎に移行しやすいとも言われますが、実際には季節性・通年性で症状自体に大きな差はありません。
ただ、ダニやホコリが原因の場合は目の症状や皮膚症状は比較的少なく、主に鼻症状(くしゃみ・水様鼻汁・鼻づまり)が中心になります。
また季節性のように「この時期だけつらい」というより、一年の中で常に軽い症状が続くか、あるいは環境の変化(大掃除や引っ越し等で埃を舞い上げた時など)で一時的に悪化するという経過をとることが多いです。
季節性と通年性はいわば原因と発症時期の違いであり、同じ人が季節性と通年性の両方の要因(例えば花粉とハウスダスト両方)にアレルギーを持つ場合もあります。
その場合は季節を問わず年中症状があり、さらに花粉シーズンに症状が悪化するということも起こります。
いずれにしても、何に対するアレルギーなのかを調べておくことで、原因物質を避ける工夫や適切な治療の選択につながります。
アレルギー性鼻炎と他の病気の違い
くしゃみや鼻水・鼻づまりといった鼻炎症状は、風邪(急性鼻炎)や副鼻腔炎など他の病気でもみられるため、アレルギー性鼻炎との区別が重要です。
ここではアレルギー性鼻炎・風邪・副鼻腔炎の三者について、原因や症状の違いを比較します。
まず原因の違いですが、アレルギー性鼻炎は上記のように花粉やダニなどのアレルゲンが引き金となる免疫反応です。
それに対し風邪は主にウイルス感染(ライノウイルスやコロナウイルスなど)によって起こり、副鼻腔炎は多くが細菌感染(しばしば風邪がこじれて細菌二次感染したもの)によって起こります。
したがってアレルギー性鼻炎は「本来無害なものに対する過剰な免疫反応」であるのに対し、副鼻腔炎は「病原体に対する必要な免疫反応」の側面があり、治療方針も大きく異なります。
次に症状や経過の違いです。
風邪や副鼻腔炎でも鼻水・鼻づまりは出ますが、アレルギー性鼻炎の鼻水は透明でさらさらしているのが通常です。
風邪の場合、初期は水っぽくても数日で白濁や黄色に色づいた粘性の鼻汁に変化することが多く、副鼻腔炎では膿の混じった濃い黄色~緑色のドロッとした鼻汁が長期間続くのが典型です。
また発熱に関しても、アレルギー性鼻炎では基本的に熱は出ません。
風邪では軽い発熱を伴うことがあり、副鼻腔炎でも慢性期は微熱程度ですが急性期には熱っぽさを感じることがあります。
症状の持続期間にも差があり、アレルギー性鼻炎はアレルゲンが存在する限り何週間も症状が続く傾向があります。
これに対し一般的な風邪症状は数日~1週間程度で改善し、副鼻腔炎は治療しないと数週間~数か月と長引くことが多いです。
以上のポイントをまとめた比較表を示します。
| 症状・特徴 | アレルギー性鼻炎 | 風邪 | 副鼻腔炎 |
| 発症のきっかけ | アレルゲンの吸入(花粉・ダニ・ハウスダスト) | ウイルス感染 | 細菌感染が多い(風邪のこじれ) |
| 発症時期 | 特定の季節に集中/年中(通年性) | 年中いつでも(季節関係なし) | 風邪の後に続発することが多い |
| 主な鼻症状 | 透明でさらさらした鼻水、鼻づまり、くしゃみ | 鼻水、鼻づまり、くしゃみ(※ウイルス性鼻炎では鼻水が粘調になることも) | 粘り気のある膿性の鼻水、鼻づまり、嗅覚低下 |
| 発熱の有無 | ほとんどなし | 軽度の発熱を伴う場合あり | 場合により軽い発熱 |
| 症状の持続期間 | アレルゲン暴露中は長期間続く(数週間~) | 数日~1週間程度で改善する | 長引くことが多い(数週間~慢性化) |
※上記は一般的な違いを示したものです。個人差や例外もあるため、症状が長引く場合は自己判断せず専門医に相談してください。
アレルギー性鼻炎の鼻汁はほぼ無色透明で、風邪や副鼻腔炎では黄色~緑色に濁った鼻汁が出やすいという違いがあります。
またアレルギーでは発熱しない点も大きな相違です。
症状が2週間以上続く場合や、鼻汁が膿のようになってきた場合は副鼻腔炎への移行が疑われますので、耳鼻咽喉科を受診して適切な治療を受けることが望ましいでしょう。
関連記事:風邪のときの適切な過ごし方
アレルギー性鼻炎の薬の種類と選び方
アレルギー性鼻炎の症状を和らげるために、薬物療法がよく行われます。
症状の程度(軽症~重症)や型(くしゃみ・鼻水型 or 鼻づまり型)に応じて適切な薬を選択・併用することが大切です。
ここでは主な薬の種類と、それぞれの特徴や選び方のポイントを解説します。
症状に合った薬を使うことで日常生活の快適さを取り戻しましょう。
抗ヒスタミン薬
抗ヒスタミン薬はアレルギー性鼻炎の治療で最も基本となる薬です。
ヒスタミンというアレルギー症状の原因物質の作用をブロックし、くしゃみや鼻水、鼻づまり、目のかゆみなど幅広い症状を緩和します。
即効性があり、症状が出ている間の対症療法として有用です。
飲み薬(経口薬)が主流ですが、アレルギー用の点鼻薬・点眼薬にも抗ヒスタミン成分が含まれるものがあります。
抗ヒスタミン薬には多数の種類がありますが、大きく第一世代と第二世代に分類されます。
第一世代(古いタイプ)は即効性がありますが眠気などの副作用が強めであり、現在主に使われる第二世代は副作用が抑えられています。
市販薬にも抗ヒスタミン成分を含むものが多く、ドラッグストアで購入可能な内服薬(例:フェキソフェナジン〔アレグラ®〕、エピナスチン〔アレジオン®〕など)もあります。
眠気の出にくい成分は運転や仕事中でも使用しやすいため、車の運転者や機械作業に従事する方には第二世代の中でも特に非鎮静性の薬が選ばれます。
一方、眠気がある程度出ても即効性を重視したい場合や夜間の症状に使う場合は眠気のある薬を選ぶこともあります。
抗ヒスタミン薬を選択する際は、眠気の強さと効果持続時間を確認しましょう。
初めて使う方や日中に活動する方は眠くなりにくい薬がおすすめです。
また1日1回で済むタイプか、食事の影響を受けるかなども考慮します。
症状が軽い場合は市販薬で様子を見る手もありますが、症状が強かったり長引く場合は処方薬も含めて医師に相談すると良いでしょう。
ステロイド点鼻薬
ステロイド点鼻薬(鼻噴霧用ステロイド)は、鼻粘膜の炎症を直接抑える強力な抗炎症薬です。
ステロイド(副腎皮質ステロイド)には炎症やアレルギー反応を鎮める作用があり、鼻にスプレーすることで鼻水・鼻づまり・くしゃみなど様々な症状を改善してくれます。
点鼻薬として使用する場合の全身への吸収はごくわずかで、副作用も少ないのが特徴です。
ステロイド点鼻薬は即効性では抗ヒスタミン薬に劣るものの、継続使用で高い効果を発揮します。
実際、アレルギー性鼻炎の治療で最も有効とされる薬剤はステロイド点鼻薬であり、単独でも症状を大きく緩和できるとのエビデンスがあります。
特に鼻づまりがひどい場合や中等症~重症の鼻炎では第一選択となることが多いです。
現在、日本で使用できる点鼻ステロイド薬はいくつか種類があり、1日1回で良いものやパウダータイプのものなど剤型も様々です。
効果には大差ないため、使いやすさ(噴霧回数や感触)で選ぶと良いでしょう。
ステロイド点鼻薬は症状が出ている間、毎日続けて使用することが重要です。
症状が軽減しても飛散期が終わるまでは継続した方が効果的で、花粉飛散の2週間ほど前から使い始めておく「初期療法」が推奨される場合もあります。
即効性がない分、「効いているのか分からない」と途中でやめてしまわないよう注意してください。
正しく使えば子どもから大人まで安全に使えるお薬です。
点鼻のコツとして、スプレー後は軽く鼻をすすって薬液を行き渡らせ、噴霧後しばらくは鼻を強くかまないようにすると効果的です。
血管収縮薬(鼻づまり改善薬)
血管収縮薬とは、鼻粘膜の血管を収縮させて鼻づまりを一時的に解消する薬です。
点鼻用の市販薬によく含まれており、ナファゾリン、オキシメタゾリン、テトラヒドロゾリンなどの成分があります。
鼻にスプレーすると数分でスーッと通るようになり、即効で息苦しさを改善してくれるため、ひどい鼻づまり時には非常にありがたい薬です。
しかし効果は一時的であり、長期間・頻回に使うと効果が落ちてくる点に注意が必要です。
血管収縮薬を連用すると、鼻粘膜の血管が薬に慣れてしまい、切れると余計に拡張してリバウンド(薬剤性鼻炎)を起こすことがあります。
具体的には、最初は1滴で効いていたのが次第に効かなくなり、より多く頻繁に使わないと詰まるようになります。
こうなると悪循環で鼻粘膜が慢性的に腫れ、薬が効かない強い鼻づまりに陥ってしまいます。
このため、血管収縮薬の点鼻は連続使用は数日以内にとどめ、長期の使用は避けることが鉄則です。
血管収縮薬は即効性があるため、就寝前やここ一番で鼻を通したい時にスポット的に使うのがおすすめです。
慢性的な鼻づまりには先述のステロイド点鼻薬やロイコトリエン拮抗薬で根本的に炎症を抑える方が安全です。
どうしても使いたい場合は医師に相談し、処方薬として出される血管収縮薬配合剤(例:抗ヒスタミンとの合剤である「ディレグラ®」など)を用いる方法もあります。
市販の点鼻薬を自己判断で乱用することは避け、使用回数や期間を守るようにしましょう。
ロイコトリエン受容体拮抗薬
ロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRAと略されます)は、アレルギー反応で放出されるロイコトリエンという物質の作用を阻害する飲み薬です。
ロイコトリエンは気道粘膜の血管透過性を高めて腫れ(鼻づまり)を引き起こす物質であり、この薬を内服すると鼻粘膜のむくみが取れて鼻づまりに高い効果を示します。
抗ヒスタミン薬では十分に改善しない頑固な鼻づまりに対して有用で、実際に「鼻閉型」のアレルギー性鼻炎に適するとされています。
ロイコトリエン拮抗薬の代表例はモンテルカスト(商品名シングレア®など)やプランルカスト(オノン®)で、いずれも処方箋が必要です。
効果が現れるまで数日~1週間ほど要するため即効性はありませんが、毎日服用することで鼻づまりを全体的に改善し、夜間の鼻閉による睡眠障害の軽減にも役立ちます。
また気管支喘息にも適応がある薬で、喘息とアレルギー性鼻炎を両方お持ちの方には一石二鳥の効果が期待できます。
実際、喘息患者の多くに鼻炎の合併が見られるため、両疾患を併せ持つ場合はロイコトリエン拮抗薬がしばしば選択されます。
ロイコトリエン拮抗薬は主に鼻づまり対策として、抗ヒスタミン薬でくしゃみ・鼻水を抑えつつ併用するケースが多いです。
単独でも効果がありますが、特に花粉症のピーク時などは抗ヒスタミン薬+LTRAの併用で相乗効果が期待できます。
眠気の副作用はほとんどなく、1日1回の服用で済む薬が多いので、長期管理薬として使いやすいのも利点です。
注意点として、重症のアレルギー性鼻炎ではこれだけでは不十分なことも多いため、症状に応じて他の薬とも組み合わせて治療計画を立てましょう。
漢方薬
アレルギー性鼻炎の治療には、漢方薬が補助的に使われることもあります。
漢方薬は即効性こそ西洋薬に劣りますが、体質から改善を図るアプローチで、西洋薬が使いにくい軽症例や妊娠中の患者さんなどにも用いられます。
アレルギー性鼻炎に効果が期待できる漢方処方はいくつかありますが、中でも有名なのは小青竜湯(しょうせいりゅうとう)です。
小青竜湯は水っぽい鼻水が出る風邪や鼻炎によく使われ、透明で大量の鼻水を伴うアレルギー性鼻炎に適しているとされています。
実際、身体を温めて水分代謝を整えることで鼻水を鎮める作用があり、花粉症シーズンに小青竜湯を服用すると症状が軽減したとの報告もあります。
その他、葛根湯加川芎辛夷(かっこんとうかせんきゅうしんい)や辛夷清肺湯(しんいせいはいとう)など鼻炎に用いる処方もあり、症状や体質に合わせて処方が選択されます。
例えば、鼻づまりが主体で冷えのぼせがあるタイプには葛根湯加川芎辛夷、膿性鼻汁を伴う慢性副鼻腔炎を合併するようなタイプには辛夷清肺湯、といった使い分けがなされます。
漢方薬は患者個々人の「証(体質・症状の傾向)」に合致したものを選ぶ必要があるため、自己判断での選択は難しいことがあります。
漢方に詳しい医師に相談し、現在の症状や体質に合った処方を見つけてもらうことが大切です。
西洋薬と併用することで相乗効果が得られる場合もありますが、重症の症状を漢方のみで抑えるのは困難です。
あくまで補助療法として位置付け、必要に応じて西洋薬と組み合わせながら症状緩和を目指すと良いでしょう。
その他の治療薬
上記以外にも、アレルギー性鼻炎の治療にはいくつかの薬剤カテゴリーがあります。
肥満細胞安定化薬(ケミカルメディエーター遊離抑制薬)
クロモグリク酸ナトリウム(インタール®点鼻薬)など、アレルギー反応の初期に肥満細胞から放出されるヒスタミンなどの化学伝達物質の遊離を抑える薬です。
即効性はありませんが、予防的に使用することで鼻水・くしゃみ・目のかゆみを抑える効果があります。
症状が出る前から毎日点鼻しておくことで発症を軽くする目的で使われます。
抗コリン薬(抗ムスカリン薬)点鼻
鼻の過剰な分泌を抑える作用があり、水様性の鼻水がひどい時に用います。
日本ではイプラトロピウム臭化物(商品名ナゾネックス®ミストなど)が知られています。
こちらも鼻水専用の対症療法で、鼻づまりやくしゃみには効きません。
経口ステロイド薬
重症の花粉症などで症状がどうしようもなく辛い場合に、短期間だけ内服のステロイドを用いることがあります。
強力に全身のアレルギー反応を鎮めますが、副作用の問題から基本的には数日間の頓用に留めます。
長期連用は副腎抑制など重大な副作用を招くため避けます。
抗IgE抗体(生物学的製剤)
非常に重症のアレルギー性鼻炎に対して、ごく最近登場した治療法です。
オマリズマブ(商品名ゾレア®)という注射薬があり、IgE抗体に結合してアレルギー反応そのものを抑える作用があります。
ただし適応となるのは通常の薬物治療で効果不十分な最重症例で、且つスギ花粉に対するIgE値や体重など細かい条件を満たす必要があります。
費用も高額になるため、現状では限られた患者さんにのみ行われる特殊な治療です。
アレルゲン免疫療法(減感作療法)
唯一、アレルギー性鼻炎の根本治療に位置付けられる方法です。
スギやダニのアレルゲンエキスを少量から体内に取り込み、体をアレルゲンに慣れさせる治療法で、舌下錠を用いる方法(舌下免疫療法)が一般的です。
効果発現までに少なくとも数か月、3~5年間の継続治療が推奨されますが、終了後も薬が不要なほど症状が軽減する効果が期待できます。
実際、免疫療法を3年以上続けることで症状スコアや薬の使用量が有意に減少し、治療中止後も効果が持続したとの報告があります。
免疫療法は根治的なアプローチですが、治療開始時にアナフィラキシーなどのリスクがあるため初回は医療機関での投与・経過観察が必須です。
また効果には個人差があり、全員に有効とは限りません。
それでも現在の医療では貴重な選択肢であり、スギ花粉症やダニアレルギー性鼻炎で重症の方には検討されます。
なお、オンライン診察では処方できない薬になります。
薬選び全体のポイント
アレルギー性鼻炎の薬物治療では、症状タイプ(くしゃみ・鼻水主体か鼻づまり主体か)や重症度によって薬を組み合わせるのが一般的です。
例えば「くしゃみ・鼻水がひどい軽症例」ではまず抗ヒスタミン薬単独、「鼻づまりが強い中等症例」では抗ヒスタミン+ステロイド点鼻、「最重症例」では抗ヒスタミン+ステロイド点鼻+LTRA、といった具合です。
症状が落ち着いてきたら薬を減らし、シーズンオフには休薬することもあります。
また、予防的にシーズン前から薬を開始する「初期療法」も有効です。
いずれにせよ自己判断で市販薬だけで済ませず、症状が辛い場合は耳鼻科やアレルギー科を受診して自分に合った治療プランを立ててもらうことをおすすめします。
アレルギー性鼻炎の症状を予防するためにできること
アレルギー性鼻炎は、日頃の環境整備や生活習慣の工夫によって症状の発現・悪化をかなり防ぐことができます。
薬に頼りきりになる前に、まずは身の回りでできる予防策を実践してみましょう。
ここでは「室内環境の整備」「花粉・ハウスダスト対策」「日常生活での注意点」の観点から、具体的な予防策を紹介します。
室内環境を整える
アレルゲンへの曝露を減らすことがアレルギー性鼻炎の予防の基本です。
室内では主にダニやホコリ(ハウスダスト)への対策が重要になります。
掃除・換気
室内のホコリを溜めないよう、こまめな掃除機掛けや拭き掃除を習慣にしましょう。
掃除機はできればHEPAフィルター付きのものを使い、舞い上がったホコリが落ち着く就寝前ではなく日中に行うのがポイントです。
また適度な換気も大切ですが、花粉シーズンは窓を全開にすると大量の花粉が入り込む恐れがあります。
花粉の多い時期は窓を10cmほど開ける程度にし、レースカーテン越しに換気するだけでも花粉の侵入量を大幅に減らせます。
寝具のケア
布団や枕にはダニやその死骸・フンが蓄積しやすいため、防ダニカバーで覆ったり定期的に洗濯・乾燥させることが効果的です。
シーツや枕カバーは週1回以上、60℃以上の高温水で洗濯するとダニの除去に有効です。
晴れた日に布団を干す場合も、叩いてホコリを舞い上げないよう注意し、取り込んだ後は表面の花粉やホコリを掃除機で吸い取るとよいでしょう。
湿度管理
ダニは高温多湿を好むため、室内の湿度を50%前後に保つことで繁殖を抑えられます。
梅雨時や夏場は除湿器・エアコンを活用してください。
逆に冬場は暖房で空気が乾燥しすぎると鼻の粘膜が刺激を受けやすくなるため、適度な加湿(湿度40~60%)を心がけ、喉や鼻を潤すようにしましょう。
その他
カーペットやソファなどの布製家具はダニの温床になりやすいため、可能であればフローリングや革張り製品に替えるのも一案です。
カーテンやぬいぐるみなど洗えるものは定期的に洗濯しましょう。
またペットを室内で飼っている場合、その毛やフケもアレルゲンになるので、寝室に入れない・こまめにシャンプーするなどの対策が必要です。
空気清浄機は補助的な手段として有用ですが、掃除など基本対策の代わりにはならないことに留意してください。
花粉やハウスダストの対策
屋外の花粉や室内のハウスダストに直接触れない・吸い込まない工夫も重要です。
花粉対策
花粉シーズンにはできるだけ花粉を避ける行動をとりましょう。
天気予報で花粉飛散量をチェックし、飛散の多い日は不要不急の外出を控えるのがベストです。
外出する場合はマスクやメガネを着用し、帽子をかぶって髪や顔への付着を減らします。
服装はウールやフリース素材だと花粉が付きやすいので、ツルツルした素材の上着を選ぶと良いでしょう。
帰宅時には玄関前で衣服や髪をよく払い、室内に花粉を持ち込まないようにします。
洗顔やうがい、鼻をかむなどして鼻や喉に付着した花粉も洗い流しましょう。
また、洗濯物や布団はできるだけ部屋干し・室内干しにして、花粉の付着を防ぐことも大切です。
ハウスダスト対策
ダニやホコリに対しては先述の室内掃除に加え、埃っぽい場所でのマスク着用も有効です。
掃除や布団を扱う際にはマスクや場合によってはゴーグルを着用し、自分がアレルゲンを舞い上げて吸い込まないよう注意します。
またエアコンや空気清浄機のフィルターを定期的に清掃・交換することも忘れずに行いましょう。
エアコン内部にカビが繁殖するとカビ胞子がアレルゲンとなるため、オフシーズン前後には専門業者によるエアコン清掃も検討すると安心です。
鼻洗浄の習慣
花粉やハウスダストが粘膜に付着したままだと症状が持続・悪化しやすいです。
市販の生理食塩水などで定期的に鼻うがい(鼻洗浄)をすることで、鼻腔内のアレルゲンを洗い流すことができます。
特に外出後や掃除後などは鼻腔内に花粉・ホコリが入り込んでいるため、優しく鼻洗浄をすると効果的です。
鼻うがい用の洗浄器具や粉末(食塩と重曹の配合剤)が市販されているので、それらを利用すると簡便でしょう。
正しい方法で行えば痛みもほとんどなく、鼻づまり軽減にも役立ちます。
日常生活での注意点
日常の生活習慣を整えることも、アレルギー性鼻炎の症状予防・緩和に寄与します。
規則正しい生活
十分な睡眠とバランスの良い食事をとり、体の免疫機能が正常に働くよう心がけましょう。
寝不足や不規則な生活は免疫のバランスを崩し、アレルギー反応が過敏になりやすいと指摘されています。
特に花粉シーズン中は早寝を意識して体調を整えることが大切です。
体調管理
風邪をひかないように注意することも重要です。
鼻の粘膜がウイルス感染でダメージを受けるとバリア機能が低下し、アレルゲンの侵入を許して症状が悪化する悪循環があります。
外出後の手洗い・うがいを励行し、流行期にはマスク着用など基本的な感染対策をすることが、間接的に花粉症状の悪化防止につながります。
嗜好品を控える
飲酒や喫煙はできるだけ控えましょう。
アルコールは鼻粘膜の血管拡張を招き鼻づまりを悪化させますし、喫煙は気道の炎症を強め免疫を刺激します。
花粉症シーズンだけでも節酒・禁煙を心がけると症状緩和に役立ちます。
ストレスを溜めない
精神的ストレスや過労も免疫バランスに影響すると言われます。
適度にリラックスする時間を設け、ストレスコントロールに努めましょう。趣味や入浴などでリフレッシュすることも大切です。
栄養摂取
抗アレルギー作用が期待される栄養素もあります。
例えばビタミンDは免疫調整に関与し、過剰な免疫反応を抑える働きがあるため、ビタミンD不足の人では補充により花粉症状が和らぐ可能性が示唆されています。
日光浴や魚類・キノコ類の摂取でビタミンDを十分補給し、必要に応じてサプリメントも検討すると良いでしょう。
ただし特定の食品やサプリだけで劇的に治るものではないので、あくまで補助的に考えてください。
以上のような生活上の工夫を積み重ねることで、アレルギー性鼻炎の症状はかなりコントロールしやすくなります。
特に花粉症の方はシーズン前から予防策を講じておくことが肝心です。
初期療法として飛散開始2週間前から抗アレルギー薬を飲み始めておくと発症を遅らせたり軽減できるという報告もあります。
早め早めの対策で「備えあれば憂いなし」を心がけましょう。
関連記事:花粉症で鼻水が止まらない!そんな時はオンライン診療がおすすめ
オンラインメディカルクリニックではアレルギー性鼻炎の薬の処方が可能
忙しくて病院に行く時間がない方や、花粉症シーズンに外出するのがつらい方には、オンライン診療の活用がおすすめです。
オンラインメディカルクリニックでは、花粉症を含むアレルギー性鼻炎に対してオンライン診療を行っており、スマホやパソコンを使って自宅にいながら医師の診察を受けることができます。
ビデオ通話を通じて症状や困っていることを伝えれば、当院の経験豊富な医師があなたの症状に合わせて適切な薬を処方します。
処方された薬はご自宅まで配送することも可能なため大変便利なサービスです。
実際にオンライン診療で処方可能な薬には、前述した第二世代抗ヒスタミン薬やステロイド点鼻薬、ロイコトリエン受容体拮抗薬、漢方薬など、アレルギー性鼻炎の標準的な治療薬が含まれます。
医師が問診で症状のタイプや重さを評価し、それに適した薬や組み合わせを提案してくれます。
例えば「鼻水とくしゃみがひどいが眠気の少ない薬が欲しい」といった希望も遠慮なく伝えてください。
オンラインで処方された薬は最短翌日には自宅に届くため、花粉症のピーク時でも外出せずに治療を継続できます。
オンライン診療のメリットは、自宅や職場からスマホ一つで受診できる手軽さに加え、対面診療と比べ待ち時間が少なく済む点にもあります。
特に花粉症シーズンは耳鼻科が混み合う傾向にありますが、オンラインなら隙間時間で受診可能です。
また、コロナ禍以降は「密な待合室に行かなくて済む」「マスクや眼鏡で花粉対策をしたまま診療を受けられる」といった利点も再評価されています。
オンライン初診では重症度や既往歴によって処方できる薬に制限がある場合もあります。
症状によっては対面診察や検査が必要と判断されることもありますので、その際は医師の指示に従ってください。
また、花粉症の舌下免疫療法など一部の治療はオンラインで開始できません。
しかし一般的な薬物療法であればオンライン診療で十分対応可能です。
まずは気軽にオンラインメディカルクリニックに相談し、つらい鼻炎症状を我慢しすぎないようにしましょう。
まとめ
アレルギー性鼻炎(花粉症を含む)は、現代人の約半数が患うともいわれる非常に一般的なアレルギー疾患です。
花粉やダニなどのアレルゲンに対する免疫反応が過敏になることで、くしゃみ・水様鼻汁・鼻閉といった症状が引き起こされ、日常生活の質(QOL)を著しく低下させます。
症状は季節性(花粉症)と通年性に分かれ、季節性では春や秋の花粉飛散期に集中して症状が出るのに対し、通年性では一年を通してじわじわと症状が続く傾向があります。
それぞれ原因は異なりますが、症状そのものは共通する部分も多く、透明なさらさら鼻水や発作的なくしゃみ、頑固な鼻づまりが主な悩みとなります。
風邪や副鼻腔炎との違いを簡単に振り返ると、アレルギー性鼻炎はアレルゲン暴露で急に発症し、発熱は伴わず、鼻水は透明である点がポイントでした。
一方、風邪・副鼻腔炎では感染がきっかけで徐々に症状が出現し、発熱を伴うこともあって、鼻汁が膿性に変化し長引くことが多いです。
これらの違いを念頭に置きつつ、症状が長引く場合や悪化している場合は早めに耳鼻科を受診して適切な診断を受けることが重要です。
治療に関しては、抗ヒスタミン薬・ステロイド点鼻薬を中心に症状や重症度に応じて薬を組み合わせることになります。
抗ヒスタミン薬はくしゃみや鼻水を素早く抑え、ステロイド点鼻は鼻粘膜の炎症を鎮めて鼻づまりまで含め症状全般に高い効果を発揮します。
症状やライフスタイルに合わせて眠くなりにくい薬を選ぶ、点鼻薬を毎日継続するなど工夫していきましょう。
症状が軽減しない場合にはロイコトリエン拮抗薬や漢方薬の追加、専門的治療としてアレルゲン免疫療法の検討もあり得ます。
近年は生物学的製剤による治療も選択肢に加わりつつあり、アレルギー性鼻炎の治療法はさらに発展しています。
しかし何より大切なのは、アレルゲンを避ける生活上の対策です。
日頃から部屋の掃除・換気を行い、花粉飛散時にはマスクやメガネで防御して、自己防衛することが症状予防の基本になります。
規則正しい生活で免疫バランスを整えることも忘れないようにしましょう。
こうした取り組みにより症状を最小限に抑えつつ、必要なときには薬を上手に利用して快適さを取り戻すことが可能です。
もし「市販薬を試したけどイマイチ効かない」「病院に行く時間がない」という方は、オンライン診療も活用しながら早めに医療機関へ相談してみてください。
適切な薬物治療を受ければ、アレルギー性鼻炎によるつらい症状は必ずコントロールできます花粉やハウスダストとうまく付き合いながら、日常生活への影響を減らしていきましょう。
症状に悩む方は、本記事の内容を参考にぜひ今日から対策を実践してみてください。
そして必要に応じて専門医の力も借りながら、快適な毎日を取り戻しましょう。お大事にしてください。