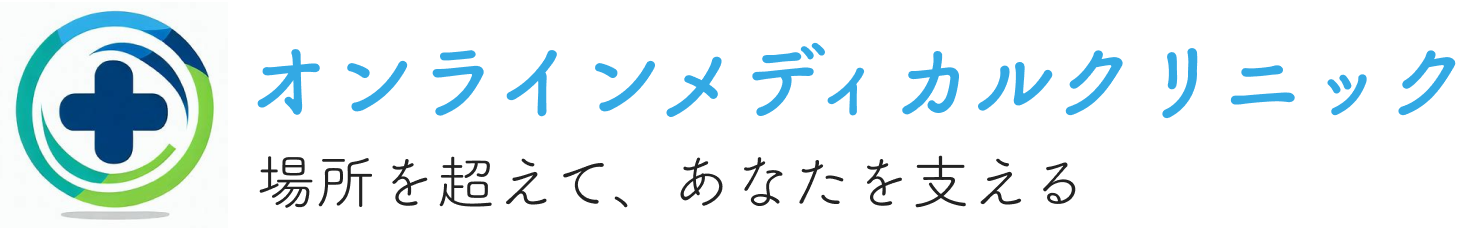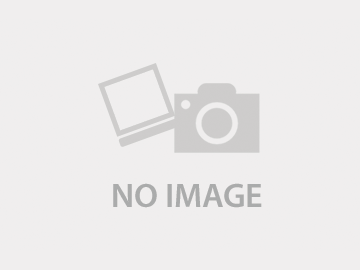現代人の多くは「なんとなく不調」を抱えがちです。
例えば、慢性的な肩こりや疲労感、生理痛、夜中に突然起こる脚のつり(こむら返り)など、病院に行くほどではないけれど日常生活の質(QOL)を下げる不調があります。
実は、こうした不調に漢方薬が力を発揮することがあります。漢方は体全体のバランスを整え、根本から体調を改善する伝統医学です。
その中でも芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)は、筋肉のけいれんや痛みに速効性がある処方として古くから知られ、現代でも脚のつりや生理痛など様々な症状に用いられています。
本記事では芍薬甘草湯の基本と効果、具体的な適応症状、服用時の注意点を解説します。
芍薬甘草湯とは

芍薬甘草湯は、漢代の中国医学書『傷寒論(しょうかんろん)』にも記載されている古典的な漢方薬です。
処方名のとおり、生薬の芍薬(シャクヤク)と甘草(カンゾウ)の2つだけで構成されるシンプルな処方で、その歴史は1,800年以上にもなります。
古来より筋肉の急なけいれんやこわばりを和らげる薬として重宝され、特に足がつる(こむら返り)症状に使われてきました。
芍薬甘草湯は即効性が高く、一服すると足腰が立たないほどだった人が杖を捨てて歩けるようになる、とまでいわれたことから「去杖湯(きょじょうとう)」という別名もあります。
つまり、それほど速やかに筋肉の痛みを取ってくれる処方という意味です。
名前の由来からも分かるように、芍薬甘草湯は昔から筋肉の痙攣による痛みに対する“漢方の鎮痛剤”として親しまれてきました。
関連記事:ストレスによる食欲不振の原因とリスク【オンライン診療と漢方でできる改善策】
成分と作用機序
芍薬甘草湯の成分は芍薬(ボタン科のシャクヤクの根)と甘草(マメ科のカンゾウの根茎)だけです。それぞれが持つ薬理作用が組み合わさり、筋肉のこわばりや痛みを鎮めます。
まず芍薬に含まれる主要成分ペオニフロリンには、筋肉の過度な収縮を抑える働きがあります。
その結果、鎮痛・鎮静作用や筋肉弛緩作用を発揮し、筋肉のこりや身体の痛み、手足の引きつり、胃のけいれんなどを和らげます。
簡単に言えば、芍薬が筋肉をリラックスさせ痛みを落ち着かせる役割を担っているのです。
また芍薬には血行を促進する作用もあり、筋肉への血流を良くすることでこわばりを取る効果も期待できます。
一方の甘草に含まれるグリチルリチン酸などの成分には、炎症を鎮め痛みを和らげる作用があります。
甘草は「百薬の長」とも呼ばれ、さまざまな漢方処方の調和薬(ブレンドのバランスを取る薬)として使われますが、芍薬甘草湯では鎮痛・鎮痙の主役の一つです。
甘草自体にも筋肉の緊張を緩める効果があり、急な痛みや痙攣を鎮める働きがあります。
現代医学的な研究でも、甘草由来の成分イソリクイリチゲニンに筋肉(特に平滑筋)の痙攣を抑え、痛みを軽減する効果が確認されています。
例えばラットの子宮を用いた実験では、イソリクイリチゲニンが子宮平滑筋の過剰な収縮を穏やかに抑制し、鎮痛効果を示したとの報告があります。
つまり甘草は芍薬とともに筋肉の興奮をしずめ、痛みを素早く取るのに重要な役割を果たしているのです。
このように芍薬甘草湯は、芍薬が筋肉を弛緩させ、甘草が痛みと痙攣を抑えるという二者の協調効果で、骨格筋から平滑筋まで幅広い筋肉のこわばりによる痛みに対応します。
漢方の基本的な考え方では、芍薬甘草湯は不足した「気」と「血」を補い、筋肉の急な痙攣を鎮める処方とされています。
気血を補う=体力や血の巡りを改善することで、筋肉に栄養と潤いを与え、けいれんを起こしにくくすると解釈されます。
難しい理論はともかく、「筋肉を緩めて痛みを取る二つの生薬がギュッと詰まった漢方薬」というイメージを持っていただければ分かりやすいでしょう。
適応症状と使用シーン

芍薬甘草湯の適応症状は、急な筋肉のけいれんを伴う痛み全般です。
処方解説書によると、体力や年齢にかかわらず使うことができ、「こむら返り」(ふくらはぎがつること)、筋肉の痙攣、腹痛、腰痛といった症状に幅広く適応するとされています。
ここでは具体的な使用シーンをいくつか紹介しましょう。
脚のつり(こむら返り)
芍薬甘草湯と聞いてまず連想されるのが、この症状です。夜中にふくらはぎが急に攣って飛び起きた経験のある方も多いのではないでしょうか。
実際、とある報告では成人の60%以上が夜間の足のつりを経験しており、高齢になるほど起こりやすいとも言われます。
芍薬甘草湯は、まさにこのような足がつる急な痛みへの第一選択薬として古くから用いられてきました。高齢で足がつりやすい方や、マラソンなど運動中によく脚が攣る方が予防的に服用しているケースも見られます。
実際に、芍薬甘草湯を持ち歩いておき、ふくらはぎが「ピクッ」と怪しい感じがしたらすぐ服用する、といった使い方をしている方もいます。
速やかに筋肉をゆるめ、痛みを止めてくれるので、就寝中のこむら返り対策に非常に心強い味方になってくれます。
生理痛(月経痛)
下腹部がキリキリと痛む生理痛にも芍薬甘草湯は役立つ場合があります。
特に生理時に脚がつるような症状を伴う方や、下腹部の筋肉が硬直して起こるようなお腹のこわばりを伴う生理痛に効果があるとされています。
芍薬と甘草には子宮の過度な収縮を和らげる作用があり、実際に子宮の動きを抑えて生理痛を改善する効果が報告されています。
即効性がある漢方なので、生理が始まって痛みが出てから頓服しても効きますが、つらい月経痛を予防する目的で用いることもあります。
腹痛・胃痛
お腹が急に「キューッ」とつるように痛む経験はありませんか?
ストレスや冷えなどで胃腸の筋肉がけいれんを起こすと、刺すような腹痛が生じることがあります。
芍薬甘草湯はこうした筋肉の痙攣を伴う腹痛にも有効です。
原因がはっきりしない急な胃痛や、お腹のハリを伴う腹痛などに頓服的に用いると、胃腸の緊張を和らげて痛みを鎮めてくれます。
便秘や下痢など消化器症状がなく、単純にお腹の筋肉のけいれんが原因と思われる腹痛であれば試してみる価値があるでしょう。
腰痛や肩こりに伴う筋肉の張り
芍薬甘草湯は基本的に急性の痛みに用いる処方ですが、慢性的な肩こりや腰痛の場面でも、症状によっては効果が期待できます。
例えば、ぎっくり腰のように腰の筋肉がガチガチに張って痛む時や、肩や首筋の筋肉が緊張して辛い時に、一時的に筋肉のこわばりをほぐす目的で使われることがあります。
肩こりそのものの根治薬ではありませんが、肩の筋肉を弛緩させる作用があるため症状緩和に役立つとされています。
実際に「肩こりに効く漢方」として市販薬の広告に芍薬甘草湯が挙げられることもあります。
ただし慢性的な肩こり・腰痛の場合は原因体質が様々ですので、芍薬甘草湯だけでなく他の漢方処方(例えば血行を良くする当帰四逆加呉茱萸生姜湯や、冷えによる腰痛に八味地黄丸など)を検討した方が良い場合もあります。
肩こりや腰痛に芍薬甘草湯を使う際は、筋肉の緊張が痛みの主因になっているケースに限り、有効な対症療法となるでしょう。
以上のように、芍薬甘草湯は脚のつり、筋肉痛、生理痛、腹痛、腰痛、肩こりなど幅広いシーンで「筋肉のけいれんや緊張に伴う痛み」を和らげるために使われています。
即効性があり、症状の出始めに素早く対処できる点が大きな魅力です。
ただし、後述するように長期連用は向かない薬でもありますので、「ここぞ」という時の頓服薬として上手に取り入れるのがポイントです。
芍薬甘草湯とエビデンス
近年では芍薬甘草湯の有効性についても科学的な研究が進んでいます。ここでは、そのエビデンスをいくつか紹介しましょう。
まず臨床研究の観点では、芍薬甘草湯の筋けいれんに対する効果がいくつかのランダム化比較試験(RCT)で検討されており、2019年にはそれらをまとめたシステマティックレビューが発表されています。1
このレビューでは、肝硬変患者や腰部脊柱管狭窄症患者を対象とした3つのRCTが分析され、メタアナリシスには至らなかったものの、芍薬甘草湯は肝硬変や脊柱管狭窄症に伴う筋肉の痙攣に対して有効性を示す傾向が報告されました。
例えば、肝硬変患者のこむら返りに対する試験ではプラセボより改善率が高く、腰部脊柱管狭窄症の筋けいれん痛では筋弛緩薬(エペリゾン塩酸塩)より有効であったとの結果が示されています。
(ただし統計的有意差には至っておらず症例数のさらなる蓄積が望まれます)
著者らは「現在のエビデンスは限定的ではあるが、芍薬甘草湯は肝硬変や脊柱管狭窄症患者の筋けいれん緩和に有用である可能性が示唆される」と結論付けています。
エビデンスの質としては今後さらなる大規模試験が必要ですが、少なくとも「筋肉のけいれんを和らげる漢方薬」として臨床的妥当性のあることが科学的にも裏付けられつつあります。
また透析患者の足のつりに対する有効性も報告があります。
腎不全で透析を受けている患者さんは足がつりやすいのですが、芍薬甘草湯6gを4週間服用した予備的試験では、5人中2人で完全に足のつりが消失し、他の2人でもつる頻度が有意に減少、痛みの程度も軽くなったとの結果が得られています。2
しかもこの期間中、副作用の発現は認められず安全に投与できています。
動物実験でも、ラットの横隔膜の筋収縮モデルにおいて芍薬甘草湯エキスが筋収縮力を低下させる(筋弛緩的に作用する)ことが示されており、研究者らは「芍薬甘草湯の投与は透析患者の筋けいれん予防に安全で有効な治療となりうる」と述べています。
このように臨床試験や基礎研究の双方から、芍薬甘草湯が筋肉の痙攣性疼痛を軽減する効果が示されています。
さらに生理痛に対する科学的根拠も少しご紹介します。
前述のとおり、甘草に含まれるイソリクイリチゲニンは実験で子宮の収縮を抑える作用が確認されています。3 加えて、芍薬の有効成分ペオニフロリンにも平滑筋(子宮や消化管)のけいれんを鎮める作用が報告されています。
歴史的に「芍薬甘草湯は月経痛の漢方薬」として何千年も使われてきたこと自体が一種のエビデンスですが、現代の薬理研究もその経験知を裏付けています。
実臨床でも、鎮痛剤では改善しにくい生理痛に対し芍薬甘草湯を併用して症状緩和が得られたケース報告などがあり、体質に合えば有効な選択肢となり得ます。
このように、芍薬甘草湯は長年の臨床経験に支えられた処方ですが、近年は科学的データも蓄積されつつあります。
もちろん漢方薬ですので効果には個人差がありますが、「筋肉のけいれん痛を抑える」という点については、一定の再現性が確認され始めているといえるでしょう。
エビデンスを踏まえつつ、患者さん一人ひとりの症状・体質に合わせて適切に使えば、高い満足度が得られる漢方薬と言えます。
関連記事:低気圧による頭痛の対策法|痛み止めやコーヒーは本当に効果がある?
服用方法と注意点

芍薬甘草湯は効果が早い分、使い方にもコツがあります。ここでは正しい服用方法と安全に使うための注意点を説明します。
服用方法(タイミングと量)
芍薬甘草湯は基本的に症状が出た時にその都度飲む「頓服」で用います。典型的には、足がつった瞬間や生理痛が始まった時などに1回分を服用します。
市販薬では1回1包(エキス顆粒2.5g程度)を1日2~3回までという用法が多いですが、実際には症状に合わせて1回の服用で十分なことがほとんどです。
ただし症状が強い場合、医師の判断で1回2包まで飲むこともあります。頓服するときはなるべくお湯で溶いて温かくして飲むと効果的ですが、水でも構いません。
また、夜間に足がつりやすい方は寝る前に予防的に1包服用する方法もあります。
例えば「毎晩寝る前に1包飲んでおくと、こむら返りが起きにくくなった」という報告もあります。
ただし、このような予防的連用は後述の注意点を踏まえて行う必要があります。
長期連用は要相談
芍薬甘草湯は基本的に症状のある時だけにとどめる使い方が多いです。
なので1ヶ月以上の長期にわたる服用や、1日に規定以上の量を飲み続ける場合は副作用のリスクを考慮する必要があります。
適応症状自体が一過性の痛みであるため、症状が治まったら服用は中止します。
慢性的なこむら返りであっても、起こるタイミング(夜間だけ等)が分かっている場合はその前に飲むようにし、症状がない日は飲まないようにします。
特に市販薬を自己判断で長期間飲み続けることは避け、症状が頻発するようなら医師に相談して根本原因の精査や別の治療を検討しましょう。
偽アルドステロン症に注意
芍薬甘草湯最大の注意点は、甘草に由来する副作用です。
甘草含有成分を長く大量に摂取すると、体内でホルモンのアルドステロン作用が強まったような状態になることがあります。
これを偽アルドステロン症といい、具体的には血圧上昇、低カリウム血症(血中カリウム低下)、ナトリウム・水分の貯留、浮腫(むくみ)、体重増加などの症状が現れます。
さらに低カリウム状態が進むと力が入らない、筋肉が痛む(ミオパシー)といった症状も出ることがあります。
これは重篤な副作用ですが、適量・適期間であれば滅多に起こりません。とはいえ特に注意が必要なのは、他の甘草含有製剤との併用です。
例えば、芍薬甘草湯を飲んでいるのにさらに葛根湯や他の漢方薬を重ねて服用すると、甘草の重複により偽アルドステロン症のリスクが高まります。
市販薬で芍薬甘草湯を買う場合も、併用中のサプリや漢方薬に甘草が含まれていないか確認しましょう。
また、持病で高血圧や心臓病、腎臓病がある方、利尿剤を飲んでいる方などは低カリウム血症に陥りやすいため、芍薬甘草湯の服用は主治医とよく相談することが大切です。
その他の副作用や注意事項
上記以外では、まれに食欲不振・吐き気などの消化器症状や発疹などが起こることがありますが、頻度は高くありません。
妊娠中・授乳中の服用については、芍薬甘草湯には妊婦に禁忌の生薬(例えば流産を引き起こす恐れのあるもの)は含まれていないため、必要と判断されれば妊娠中でも使用可能です。
実際、妊婦さんのこむら返り対策に処方されるケースもあります。
とはいえ妊娠中は何であれ自己判断で薬を飲むべきではありませんから、必ず産科医に相談のうえで使用してください。
授乳中も大きな問題は生じませんが、心配な場合は授乳直後に服用して次の授乳まで少し時間を空ける、といった工夫もできます。
いずれにせよ、安全に使うためには用法用量を守り、何か異常を感じたらすぐ専門家に相談することが重要です。
以上の点を守れば、芍薬甘草湯は比較的副作用の少ない安全性の高い漢方薬です。
日本では一般用医薬品(第2類医薬品)として薬局で購入することもできますが、症状や体質に合った使い方をするためには、できれば漢方に詳しい医師や薬剤師に相談して処方してもらうのが理想的です。
オンライン診療と漢方
忙しい現代人にとって、漢方の専門医療機関に足を運ぶのはハードルが高いかもしれません。
しかし最近ではオンライン診療を通じて漢方薬の相談・処方を受けることも可能になっています。
オンライン診療の利点は、まず地理的な制約を受けずに全国どこからでも専門医にアクセスできることです。
例えば近所に漢方を処方できる医師がいなくても、自宅からスマホやパソコン越しに相談ができます。
また予約から診察までネット上で完結するため、仕事や育児で忙しい方でも自分の都合に合わせて柔軟に受診時間を調整できます。
さらに処方された漢方薬は自宅に郵送してもらえるサービスもあり、薬局に出向く手間も省けます。
これは慢性的な痛みや体質改善のために漢方薬を継続利用したい場合にも大きなメリットです。
特に芍薬甘草湯のように「症状が出たときにすぐ飲みたい薬」を常備するには、オンライン診療で処方を受けておくと安心でしょう。
もちろん対面診療に比べ制約はありますが、医師と直接会話しながら症状を伝えられますし、プライバシー保護も配慮されています。
遠方に住んでいる方や忙しくて病院に行けない方でも、オンラインの漢方診療を活用すれば適切な漢方薬治療にアクセスできます。
上手に活用して、賢く健康管理を行いましょう。
まとめ
芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)は、古くから伝わる筋肉のけいれん性の痛みを抑える漢方薬です。
芍薬と甘草という2つの生薬の相乗効果で、脚のつり、生理痛、腹痛、腰痛、肩こりなど様々な「急な痛み」に速やかに作用します。
現代の研究でもその筋肉弛緩・鎮痛効果が裏付けられつつあり、上手に使えばつらい症状の緩和に大いに役立ちます。
一方で、甘草由来の偽アルドステロン症など副作用のリスクも理解しておく必要があります。
ポイントは症状が出た時の頓服薬として正しく使うことです。適切に服用すれば副作用は稀で、安全性の高いお薬です。
「なんとなく調子が悪いけど病院に行くほどでもない」そんな時こそ、漢方の出番かもしれません。
芍薬甘草湯のように即効性のある漢方薬を上手に活用すれば、つらい肩こりや脚のつり、生理痛などを乗り越え、日々を快適に過ごす手助けになります。
ただし自己判断での使用が不安な場合は、無理に我慢せず専門家に相談してください。最近はオンライン診療で気軽に漢方相談ができる環境も整っています。
信頼できる医療機関とつながりながら、芍薬甘草湯をはじめとする漢方薬を賢く取り入れて、毎日の健康管理に役立ててください。
自分の体質や症状に合った使い方さえ守れば、芍薬甘草湯はきっと強い味方になってくれるでしょう。
監修医
島村泰輝
- 2012年3月 名古屋市立大学医学部 卒業
- 2014年4月 名古屋市立大学放射線科 入職
- 2015年4月 名古屋市立大学大学院博士課程入学 (専攻:生体防御・総合医学分野)
- 2019年3月 同大学院卒業、博士号取得
- 2019年6月 株式会社エムネス 入職
- 2022年10月 同 Medical Professional Service(医師部門)副本部長
- 2023年7月 オンラインメディカルクリニック開業
愛知県名古屋市出身。遠隔放射線画像診断を行う傍ら、AI開発、メディカル用プロダクト開発を行う。
医療としてはその他にも内科診療、訪問診療にも従事。医療はITでさらに良くなる事を信条として様々な取り組みを行う。
物理的、時間的に医療が届きにくい層に対して医療を届けるべくオンライン診療を中心としたクリニックを開業。今後は各種専門家とともに、遠隔地であっても質の高い医療を提供するサービスを構築していく。