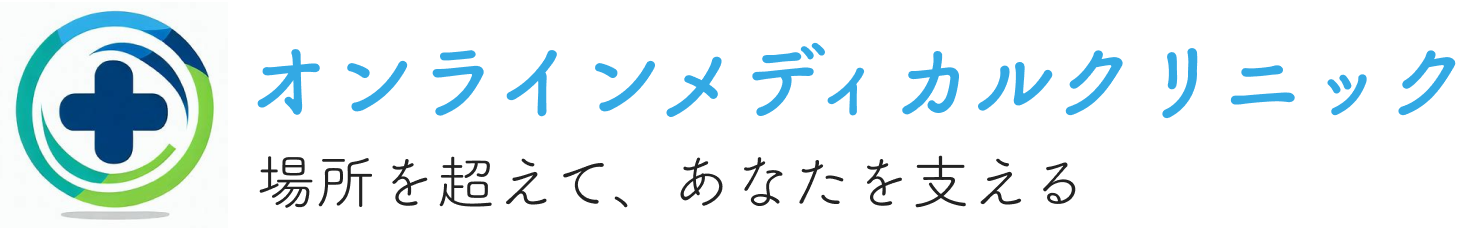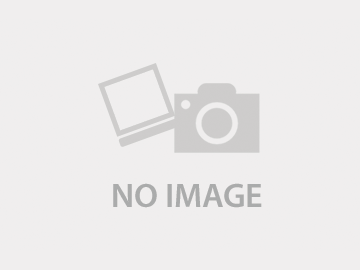近年は異常気象とも呼ばれるほど暑い季節が続き、熱中症で体調を崩す方も少なくありません。
生活環境を見直し涼しい部屋で過ごすことはもちろん、熱中症になってしまったときの対策にも目を向けておきましょう。
本記事では、熱中症に漢方薬は有効なのかどうか、症状別におすすめの処方をご紹介します。
熱中症に漢方薬は有効?
熱中症は高温多湿の環境で体温調節機能が破綻し、体温が異常上昇する状態です。
重症化すれば命に関わるため、基本は適切な水分・塩分補給と身体を冷やす応急処置が最優先となります。
一方で、日本の漢方医学には、熱を冷ます「清熱剤」と呼ばれる処方が古くから存在し、熱中症の予防や治療の補助に用いると有効であるとされています。
例えば代表的な処方の清暑益気湯(せいしょえっきとう)は、発汗を抑えて胃腸機能を改善し、気力・体力を回復させる効果があり、熱中症による頭痛なども和らげるとされます。
近年では漢方薬が熱中症の予防・症状緩和に有効であるとの研究報告も増えており、清暑益気湯のほか白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう)や生脈散(しょうみゃくさん)、五苓散(ごれいさん)など複数の漢方処方で有効性が確認されています。
ただし漢方はあくまで補完的手段であり、重度の熱中症では速やかな救急対応(冷却・点滴など)が不可欠です。
漢方薬は熱中症の諸症状に対して患者個々の体質に合わせた幅広いアプローチを可能にしますが、自己判断での使用は避け、専門の医師や薬剤師の指導のもとで適切に取り入れることが重要です。
次章では、熱中症の症状パターン別に用いられる代表的な漢方薬6種類について、効果や使い方を解説します。
関連記事:虫刺されで腫れがひどくなる原因とは?正しい対処法と治療法
症状別におすすめされる漢方薬の解説

熱中症の症状や体質に応じて、以下のような漢方薬が用いられることがあります。
各処方の特徴と、どのような症状に適しているかを見ていきましょう。
清暑益気湯 ― 熱中症の前後に現れる「汗による脱水と夏バテのだるさ」を一挙に立て直す処方
適した症状
炎天下で長時間過ごしたあと、汗が止まらず体はぐったり、食欲は落ち、下痢や軽いめまいが出る――そんな“夏バテ+軽度の熱中症”が同時に襲う場面に向いています。
水分を補給しても疲労感が抜けない・脈が細く力なく感じる・息切れが早い、といった「気(エネルギー)も津液(体の水)も尽きた」状態が典型です。
暑気あたりで寝込むほどではなくても、翌日に持ち越す倦怠感を素早く回復させたい人に選択されます。
処方の特徴
清暑益気湯は、石膏など強い冷やし薬を使わずに熱を鎮めつつ、人参・黄耆が枯渇した気を補い、麦門冬と五味子が失われた体液を生む――“清熱”と“益気生津”を同時に行うブレンドです。
大量発汗で乾いた体内にやさしく潤いを戻し、弱った胃腸を整えて食欲を呼び戻します。
これにより、脱水による血液の濃縮や循環不全を改善しながら、夏バテ特有の無気力感までケアできるのが最大の長所です。
飲んだ後は「じわじわ体力が戻って汗が落ち着く」感覚が得られやすく、猛暑日の屋外作業やスポーツ後、または熱中症からの回復期に“もうひと押し”で体を楽にしたいときに重宝されます。
五苓散(ごれいさん) – 水分バランスを整える代表処方

適した症状
初期の脱水症状(喉の渇き、頭痛、めまい、尿量減少など)や、汗をかいた後の倦怠感などに。
暑い日に水分補給しているのに吐き気や頭痛、喉の渇きを起こしやすい人に有効です。
処方の特徴
体内の「余分な水」を排出しつつ必要な水分は巡らせるという、利水剤の代表的な漢方薬です。
五苓散を服用すると、必要な部分に水分を行き渡らせて体液バランスを整え、症状を改善してくれます。
例えば熱中症予防にこまめに水分をとっても、体内で水分が停滞する(水毒)タイプの人は、かえって吐き気や頭痛を起こしがちですが、五苓散がそのような水分アンバランスを是正してくれます。
さらに五苓散は急性の胃腸障害(吐き気・嘔吐・下痢)にも効果があり、胃腸に水分がたまってチャポチャポしているような不快感も改善します。
暑さで食欲がないときの胃もたれ解消にも有用です。
比較的体力の有無を問わず使いやすく、脱水の初期対応としても広く用いられる処方です。
実際、高齢者が猛暑日に屋外作業をする際、作業前に五苓散を服用して予防する方法も紹介されています。
胃苓湯(いれいとう) – 五苓散+平胃散で胃腸症状に対応
適した症状
熱中症の初期に軽い胃腸症状(食欲不振や下痢)を伴う場合や、水分摂取の不足・偏りによる体調不良のとき。
特に冷たい飲み物ばかり摂って胃もたれし、軟便・下痢ぎみの人に向きます。
処方の特徴
胃苓湯は五苓散に平胃散(へいいさん)を合わせた処方です。
平胃散は胃腸の働きを高めて消化吸収を促し、胃にもたまった水分(湿)を捌く処方です。
五苓散の利水効果と相まって、胃苓湯は消化管のぜん動運動を促進し、水分の吸収を高めつつ、余分な水滞を除去する作用があります。
その結果、必要な水分を血中に取り込み、脱水を改善するのに役立ちます。
例えば日頃あまり水分をとらず胃腸が弱い人、あるいは逆に冷たい飲み物を摂りすぎて下痢しがちな人では、体に必要な水分がうまく吸収されず余分な水だけ滞ってしまい、熱中症にかかりやすい傾向があります。
そうしたタイプに胃苓湯は適しています。
実際、五苓散で初期対応をした後、軽い食欲不振や下痢が残る場合に胃苓湯へ切り替えるケースもあります。
胃苓湯は夏の急性胃腸炎や「夏バテによる下痢」にも応用される便利な処方です。
白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう) – 強い熱と喉の渇きに

適した症状
炎天下で体が火照って大量に汗をかき、激しい口渇があるような場合に。
熱が体にこもっている感じで、顔が赤くほてっているようなケースに第一選択されます。
一般的には比較的体力のある人向けです。
処方の特徴
白虎加人参湯は、石膏(せっこう)や知母(ちも)といった強力な清熱薬で体内のこもった熱を冷まし、人参(高麗人参)の補気作用で胃腸の機能を立て直しつつ、粳米(こうべい)の働きで喉の渇きを改善する処方です。
激しい発熱や口渇に対する代表的な清熱剤・生津剤(熱を冷まし津液〈しんえき:体液〉を増やす薬)であり、高熱を伴う脱水状態に用いると体の余分な熱を冷まし、不足した水分を補給する効果があります。
実際に、熱中症で発汗過多により生じた口渇・高体温に白虎加人参湯を投与した臨床試験では、症状の改善に有効であったことが報告されています。
また、炎暑で末梢血管が拡張し脳への血流が低下して起こる立ちくらみ(熱失神)にも効果的とされています。
なお、白虎加人参湯は清熱作用が強い反面、胃腸の弱い人には冷え症状を悪化させる可能性があります。
比較的体力のある方向けの処方ですので、服用にあたっては専門家に体質の適否を判断してもらうことが望ましいでしょう。
竹葉石膏湯(ちくようせっこうとう) – 熱を冷まし潤いを与える
適した症状
白虎加人参湯と同様に強い口渇や発熱後の脱水に用いますが、体力がない方でも使いやすい処方です。
熱中症の症状の中でも、息苦しさや咳があり粘膜の乾燥が目立つようなケースに特に効果を発揮します。
例えば熱中症後期の微熱が残る状態や、熱中症から回復する途中で喉の渇き・乾いた咳が続くような場合に適しています。
軽度~中等度の脱水状態で潤い不足(陰虚)の傾向が見られる人向けといえます。
処方の特徴
竹葉石膏湯は、石膏・竹葉(ちくよう:淡竹葉)による清熱作用と、人参・麦門冬(ばくもんどう)による気陰(エネルギーと体液)補充作用をあわせ持つ処方です。
白虎加人参湯がより深部の熱を冷ますのに対し、竹葉石膏湯は表面化した熱を冷ましつつ、津液の消耗を補う点に優れています。
すなわち高熱で乾いてしまった喉や粘膜を潤し、奪われた水分を補給して衰えた体力を回復させる働きがあります。
実際、「夏場の熱中症や口渇を訴える各種疾患にも使われる」と説明されており、軽いめまいや立ちくらみなどの軽度の熱中症にも効果があるとの報告があります。
比較的体力のない高齢者や小児にも応用しやすく、最近では7歳から高齢者まで服用できる竹葉石膏湯のゼリー製剤も市販されています。
白虎加人参湯と同様に胃腸を冷やす成分(石膏)を含むため、胃腸が冷えやすい人では下痢に注意しつつ使用します。
生脈散(しょうみゃくさん) – 汗のかきすぎによる気力低下に
適した症状
酷暑下で大量の汗をかいた後の脱力感やめまい、脈の弱まりに使われます。熱中症の予防や回復期の体力低下に用いられます。
特に高齢者で暑さにより脈が細く弱くなっている場合や、汗をかきすぎて疲労困憊している場合に効果的です。
熱中症のみならず、夏場の食欲不振・倦怠感(いわゆる夏バテ)全般にも応用されます。
処方の特徴
生脈散は人参(高麗人参)、麦門冬、五味子(ごみし)の3つの生薬からなるシンプルな処方です。
「麦味参」(ばくみさん)という顆粒製剤名でも市販されており、中国では点滴が熱中症対策に使われるほどポピュラーです。
その作用は、汗で失われた体液とエネルギーを同時に補うことにあります。
五味子の収れん作用によってナトリウムなどの電解質喪失を防ぎ、麦門冬で身体に潤いを与え、人参で消耗した気力(体力)を立て直します。
この組み合わせは、漢方で「酸甘化陰(さんかんかいん)」といい、酸味+甘味で体の陰(潤い)を生むという古来の知恵です。
五味子(酸味)に麦門冬・人参(甘味)を加えることで、効率よく全身の潤いを増やしつつ心肺機能を助ける働きがあります。
その結果、血液の粘度上昇を防いで心臓を守る効果も期待できます。
生脈散は暑気あたりでグッタリしたときの回復ドリンク的な漢方ともいえ、熱中症の初期~中期予防、治療後の体力回復に広く用いられています。
芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう) – 痙攣(こむら返り)への速効薬

適した症状
筋肉のけいれん・こむら返り(足がつる)や筋肉痛に効果を発揮します。
熱中症の典型症状である筋肉の硬直や痛み(熱痙攣)は発汗による電解質の乱れで生じますが、芍薬甘草湯はそれを素早く緩和します。
特に夜間、脱水が進んだ際に突然起こる足のつりなどに有用で、頓服薬として広く知られています。
暑い夜にエアコンが切れて寝汗をかき、明け方に足がつるような場合の予防にも適しています。
処方の特徴
芍薬(しゃくやく)と甘草(かんぞう)の2味のみからなる単純な処方ですが、即効性があり「筋肉の漢方鎮痙剤」とも呼ばれます。
芍薬の持つ鎮痛作用と、甘草(グリチルリチン)の鎮痙作用が合わさり、骨格筋・平滑筋のどちらの痙攣にも効果を示します。
熱中症によるこむら返りはもちろん、運動中の筋けいれんや月経痛、胃腸の痙攣性疼痛など幅広い急性疼痛に頓用されます。
即効薬ゆえに、市販薬(第2類医薬品)としても入手可能で、漢方を知らない方でも「夜間の足つり予防に寝る前1包」といった使い方で愛用されています。
注意点として、甘草に含まれるグリチルリチンを大量・長期間摂取すると、稀に浮腫・血圧上昇・低カリウム血症といった偽アルドステロン症を招くことがあるため、長期服用する場合は医師との相談が望ましいです。
関連記事:抑肝散とは?現代人の「なんとなく不調」に効く漢方薬の効果
漢方薬の服用上の注意点

漢方薬だからといって必ず安全とは限らないため、以下のポイントに注意しましょう。
自己判断で長期連用しない
漢方薬にも副作用はあり得ます。
体質に合わない場合、下痢・発疹・むくみなどの症状が現れることがあります。
特に甘草を多く含む処方(例: 芍薬甘草湯・防己黄耆湯など)は、長期間の過量服用で偽アルドステロン症による高血圧・低カリウム血症を招く恐れがあるため注意が必要です。
基本的に症状が改善したら漫然と飲み続けず、一旦中止するか専門医に相談しましょう。
他の薬との併用
西洋薬と漢方薬の併用は一般に可能ですが、治療方針がぶれる恐れがあるため担当医に必ず報告してください。
例えば利尿剤やステロイド剤を服用中の方が甘草含有漢方を併用すると低カリウム血症を悪化させるケースがあります。
また、重症の熱中症では漢方よりも迅速な救急処置が優先されるため、漢方は補助的に位置づけましょう。
服用のタイミング
漢方薬は食前または食間(食後2時間ほど空けて)に飲むのが原則です。
胃腸が弱い人は食後でも構いません。
また熱中症予防目的で服用する場合、症状が出る前に早めに飲むことが肝心です。
例えば炎天下で活動する前に五苓散を服用しておくと、水分代謝が整い熱中症を起こしにくくなるとされています。
一方、症状が出てからではこまめな水分・塩分補給と冷却が第一で、漢方薬はそれら基本対応と併用する形で取り入れましょう。
体質・症状に合わせる
漢方薬は人それぞれの証(体質や症状パターン)に適合するかが重要です。
例えば冷え性で胃腸が弱い人に石膏などの体を冷やす漢方を使うと下痢しやすくなるなど、副作用の出方も体質次第です。
自己判断が難しい場合は、漢方に詳しい医師・薬剤師に相談し、自分の体質に合った処方を選んでもらうようにしましょう。
熱中症の主な症状(Ⅰ〜Ⅲ度の分類)

熱中症は症状の重さによりⅠ度(軽症)・Ⅱ度(中等症)・Ⅲ度(重症)の3段階に分類されます。それぞれの特徴を簡単にまとめます。
Ⅰ度(軽度)
いわゆる熱失神・熱けいれんの段階。
意識ははっきりしています。
この段階で適切に対処すれば、多くは軽快します。
Ⅱ度(中等度)
熱疲労の段階とも呼ばれます。
判断力や集中力の低下が見られることもあります。
体温は正常〜やや上昇(38〜39℃前後)することが多いです。
自力で水分補給が難しい場合は医療機関で点滴加療が必要になります。
Ⅲ度(重度)
熱射病の状態です。
ショック症状(血圧低下や臓器不全)を伴うこともあります。
この段階では緊急入院が必要で、適切な処置が遅れると脳や多臓器障害・後遺症につながり、場合によっては死亡するリスクがあります。
一刻も早く救急車を呼び、徹底した体温管理と集中治療を受ける必要があります。
熱中症かな?と思ったら、この分類でいう何度に当たるかを判断し、Ⅱ度以上または自力で水分が摂れない場合は迷わず医療機関へ搬送してください。
特にⅢ度は命に関わる緊急事態です。
普段から暑さを避け、水分・塩分補給と休息を心がけることで、Ⅰ度の段階から予防・対処することが大切です。
関連記事:日焼け後のケアはいつ何をするべき?正しい対処法とやってはいけないNGケア
オンラインメディカルクリニックにおけるパーソナル漢方の紹介
近年ではオンラインで漢方について相談し、医師の診察によって処方が受けられるサービスも登場しています。
自宅にいながら相談でき、診療後も気軽にフォローアップの相談が可能という手軽さが特長です。
忙しくて受診の時間がない方や、近くに漢方の相談先がない方にとって、こうしたオンライン漢方は新しい選択肢となりつつあります。
例えば熱中症対策で漢方を試したい場合でも、オンライン診療で医師に体調や既往症を伝えれば、症状に合った処方を郵送で受け取ることができます。
オンライン診療では対面に比べ制限もありますが、適切に利用すれば猛暑を乗り切るセルフケアの一環として漢方薬を活用することも可能でしょう。
ただしオンラインであっても医療行為ですので、症状が重いと判断されれば対面受診を勧められる点には留意が必要です。
まとめ
猛暑が続く昨今、熱中症への備えは命を守る上で不可欠です。
漢方薬は水分代謝の調整や胃腸機能のサポート、体力の回復など熱中症の症状緩和に役立つ側面を持っています。
五苓散・白虎加人参湯・生脈散など、症状別に伝統的に用いられてきた処方には一定のエビデンスも蓄積されつつあり、上手に活用すれば予防と早期対応の心強い味方となるでしょう。
一方で、漢方だけに頼るのは禁物です。
特に重度の熱中症(Ⅲ度)は緊急治療が最優先であり、漢方薬はあくまで補完療法であることを忘れてはいけません。
大切なのは、日頃から基本の熱中症対策(暑さを避ける・こまめな水分塩分補給・十分な休息)を徹底することです。
その上で、「どうも体質的に夏に弱い」「汗のかき方にクセがある」と感じる場合は、漢方の力を借りるのも一策です。
今回ご紹介した漢方薬はいずれも比較的メジャーな処方ですが、実際の適応は人それぞれ異なります。
興味のある方は、信頼できる医療機関や薬局で自身の体質に合った漢方相談をしてみてください。
正しい知識と備えで、暑い季節を安全に、そして健やかに乗り切りましょう。
監修医
島村泰輝
- 2012年3月 名古屋市立大学医学部 卒業
- 2014年4月 名古屋市立大学放射線科 入職
- 2015年4月 名古屋市立大学大学院博士課程入学 (専攻:生体防御・総合医学分野)
- 2019年3月 同大学院卒業、博士号取得
- 2019年6月 株式会社エムネス 入職
- 2022年10月 同 Medical Professional Service(医師部門)副本部長
- 2023年7月 オンラインメディカルクリニック開業
愛知県名古屋市出身。遠隔放射線画像診断を行う傍ら、AI開発、メディカル用プロダクト開発を行う。
医療としてはその他にも内科診療、訪問診療にも従事。医療はITでさらに良くなる事を信条として様々な取り組みを行う。
物理的、時間的に医療が届きにくい層に対して医療を届けるべくオンライン診療を中心としたクリニックを開業。今後は各種専門家とともに、遠隔地であっても質の高い医療を提供するサービスを構築していく。