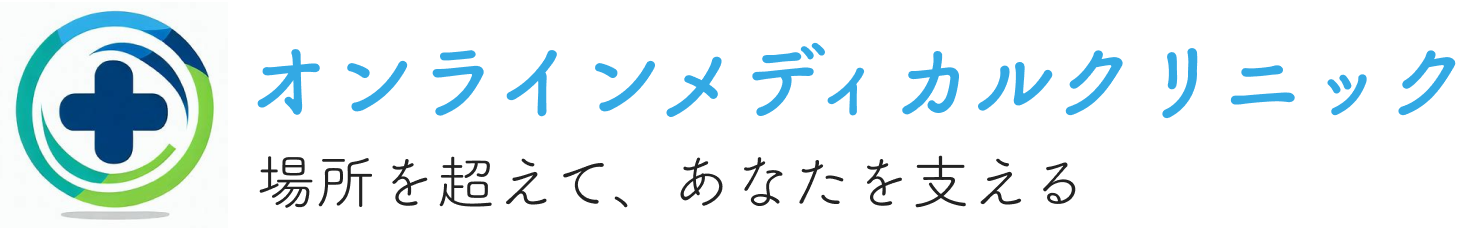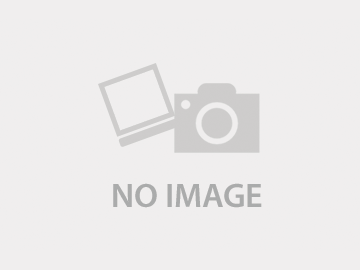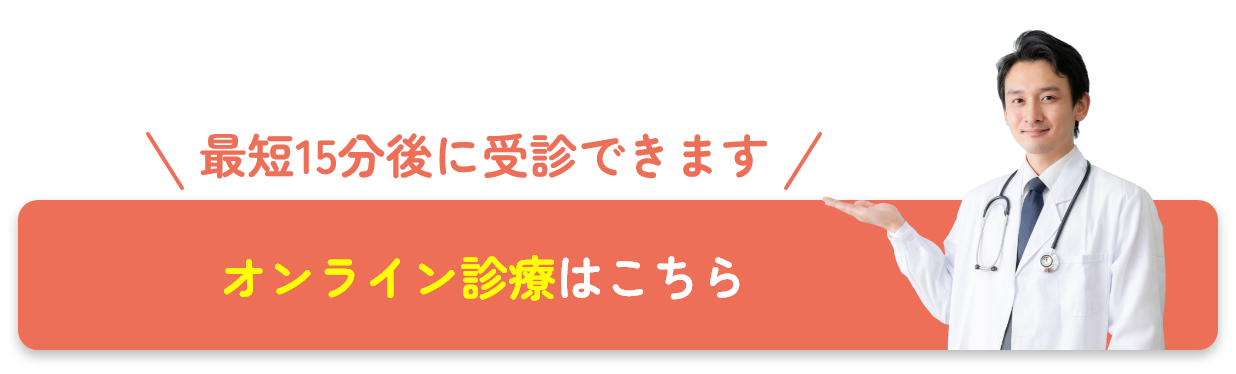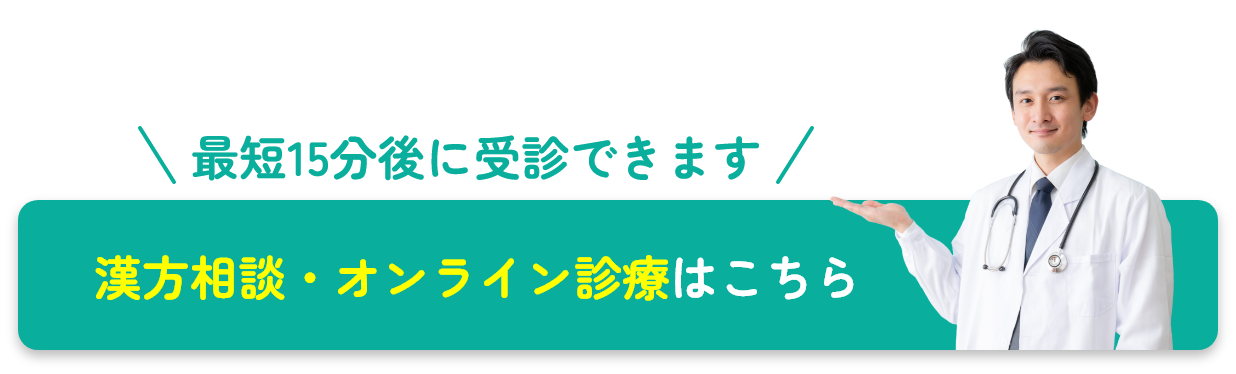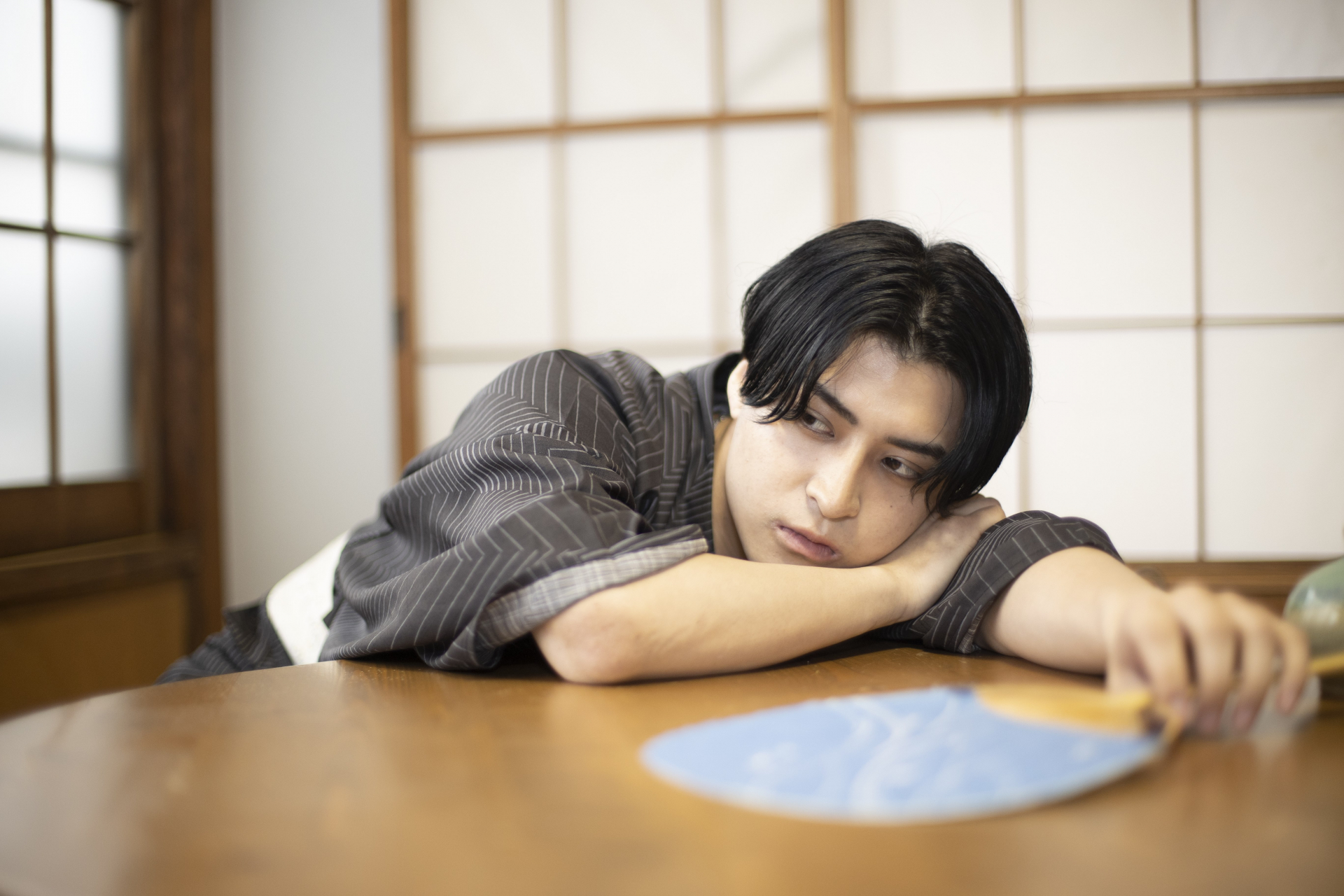
夏の厳しい暑さや高い湿度の中では、自律神経のバランスが乱れやすく、体のだるさや食欲低下など様々な不調が現れます。
こうした夏バテは単なる疲労ではなく、 胃腸の弱りや水分・栄養不足、睡眠不足などが重なって起こることが多く、特に日本の蒸し暑い夏は体への負担が大きくなりがちです。
本記事では、夏バテに効果的とされる主な漢方薬を紹介し漢方で夏バテを解消するメリットや注意点について解説します。
夏バテに効果的とされる主な漢方薬

夏バテの症状改善に古くから用いられてきた代表的な漢方薬を紹介します。
夏バテといっても、症状や体質によって適する処方が異なります。
「気」を補って全身の疲労回復を図るもの、余分な熱や湿気を除いて胃腸機能を助けるものなど、それぞれ特徴があります。
それでは、夏バテによく使われる主な漢方薬を見ていきましょう。
補中益気湯(ほちゅうえっきとう)
補中益気湯は、夏バテ・夏やせの代表的な漢方薬です。
名前の通り「中(お腹)を補い、気を益す」作用があり、全身の倦怠感や食欲不振・寝汗をかきやすいなどの「気虚(エネルギー不足)」の改善に適しています。
暑さで疲れが抜けず食欲が落ち、体重が減少するような場合に第一選択として処方されることが多く、特に産後や体力が落ちた方の夏バテに有効とされます。
実際に熱中症の急性期が過ぎ、強い疲労感と食欲不振による夏やせが見られる段階では、補中益気湯を使うと良いとされています。
エアコンの効いた室内にいても倦怠感が抜けないような虚弱なケースにも効果的です。
補中益気湯には黄耆(おうぎ)や人参など気力・体力を補う生薬が含まれ、胃腸の働きを高めて「元気の源」である消化吸収力を底上げします。
暑気あたり(熱疲労)に対する効果も古くから知られており、夏場に早めに服用することで夏バテ予防にも役立ちます。
近年の研究では補中益気湯の投与によって慢性疲労モデルのマウスの運動量低下が改善したとの報告や、高齢者で低下していた免疫細胞(T細胞・NK細胞)の数が回復したという報告もあり、疲労回復・体力増強や自律神経の調整に有用な可能性が示唆されています。
清暑益気湯(せいしょえっきとう)
清暑益気湯はその名に「清暑(暑さをさます)」「益気(気を益す)」とある通り、暑さで消耗した体力を回復させる夏バテ専用ともいえる処方です
効能効果に「暑気あたり、暑さによる食欲不振・下痢・全身倦怠、夏やせ」と記載されており、高温多湿の環境で汗をかき過ぎた後の口渇・食欲低下・倦怠感などが続く場合に用いられます。
補中益気湯では改善しきれない下痢・軟便を伴うケースや、ほてり・のぼせ感がある場合に清暑益気湯が適することがあります。
補中益気湯が効かず軟便が見られる夏バテ症状の方に清暑益気湯へ切り替えて奏効した例も報告されています。
清暑益気湯の特徴は、補中益気湯をベースに生脈散(人参・麦門冬・五味子)という処方を加えた点で、暑さで失われた気と津液(体液)を同時に補える点が魅力的です。
具体的には、人参や白朮・陳皮で胃腸の働きを高め食欲を増進し、麦門冬や五味子で汗による乾きを潤しつつ、黄耆で気力を補い、余分な熱を取り去る効果があります。
つまり「元気を補い」「汗で失われた水分を補充し」「こもった熱を冷まし」「胃腸を助ける」の4つの作用で、夏バテ症状に対し効率的に対処する処方といえます。
六君子湯(りっくんしとう)
六君子湯は胃腸が弱く食欲不振になりがちな人の体力を補う漢方薬です。
比較的体力が低下し胃腸機能も落ちている方で、食欲不振やみぞおちのつかえ感・手足の冷えといった症状を認める場合によく用いられます。
夏場は冷たい飲み物を摂り過ぎて胃が冷えてしまい胃もたれや食欲低下を起こすことがありますが、六君子湯はまさに「食欲がない」「胃が重い」という夏バテに適した処方です。
六君子湯の処方は、胃腸を元気づける四君子湯(人参・白朮・茯苓・甘草)に陳皮や半夏などを加えた形になっており、胃の働きを整えて胃もたれや嘔気を改善しつつ、消化吸収力を高める作用があります。
高齢者の少食・食欲不振にもよく使われ、食事量を増やして栄養状態を改善することで夏バテや夏やせの予防に寄与します。
実験的には、六君子湯が胃のグレリン(食欲増進ホルモン)分泌を促すことで食欲を高める作用があることも明らかにされています。
胃腸の調子が落ちているタイプの夏バテには、六君子湯で消化器を立て直すことが期待できます。
柴胡桂枝湯(さいこけいしとう)
柴胡桂枝湯は、「小柴胡湯」と「桂枝湯」という二つの処方を合わせた構成で、古典『傷寒論』『金匱要略』にも記載がある歴史ある漢方薬です。
こじれた風邪や胃腸炎が長引いている時の基本薬とされ、発熱・悪寒や頭痛、吐き気などを伴う症状によく用いられます。
夏バテとの関連でいえば、夏風邪が長引いて胃腸に不調が残っている場合や、微熱が続いて食欲不振があるようなケースに適しています。
具体的には、皮膚に自然な汗が出ていて、吐き気や食欲不振がある人に向く処方と解説されます。
柴胡桂枝湯には、柴胡や黄芩による炎症を鎮める作用と桂枝や生姜による発汗・血行促進作用が組み合わさっており、さらに人参や甘草で胃腸を助ける働きも期待できます。
そのため軽い発熱や消化不良を伴うような夏バテに用いることで、自律神経の乱れを整えつつ胃腸の負担を和らげ、症状改善を図ります。
例えば、「エアコンで冷えたところに外の暑さが加わって微熱っぽくだるい」「胃がむかつき食欲がない」といった場合に、体力があまり無い人でも使いやすい穏やかな処方です。
その他の処方
上記の他にも、夏バテの症状や体質に応じて様々な漢方薬が使われます。
例えば、 五苓散(ごれいさん)は体内の水分バランスを整え、むくみ・めまいや下痢、吐き気など水分代謝の乱れによる暑気あたりに効果的で、特に小児の熱中症予防にも用いられます。
また、全身のエネルギーと血の両方を補う十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)は、皮膚の乾燥や貧血傾向を伴うような重度の夏バテ・夏やせに処方されることがあります。
このように症状に応じた処方選択が可能なのも漢方の強みです。
関連記事:夏バテを即効治すことはできる?つらい症状を軽くする食べ物と飲み物
夏バテ解消に漢方がおすすめされる理由

では、夏バテ対策としてなぜ漢方が勧められるのでしょうか。
他の栄養ドリンクや西洋薬とは異なる、漢方ならではのメリットに着目して解説します。
体質や症状に合わせて処方できる
漢方薬は「病名」ではなく「症状」や「証(しょう)=その人固有の体質や状態」に合わせて薬を選ぶのが基本です。
そのため、同じ夏バテでも人によって処方が変わります。
他の人に効いたからといって自分にも効くとは限らないのが漢方の考え方であり、一人ひとりの体質・体力・症状の現れ方を総合的に見て最も適した漢方薬を処方することが大切です。
例えば、「汗をかきすぎて脱水気味で胃腸も弱っている夏バテ」には清暑益気湯を、「とにかく疲労感が強く食欲不振の夏バテ」には補中益気湯を、といった具合にオーダーメイドの処方選択が可能です。
そのため漢方なら、自分の夏バテ症状にぴったり合った治療が期待できます。
自律神経や消化機能を整える働き
夏バテの主な原因は自律神経の乱れと胃腸の機能低下にあると考えられます。
漢方薬には、乱れた自律神経のバランスを整えたり、弱った消化機能を改善したりする働きを持つものが多くあります。
例えば、補中益気湯はストレスによる自律神経失調を改善し、心身のストレス耐性を高める作用があるとされ、実験ではストレス下のマウスで免疫機能低下を抑制した結果が報告されています。
六君子湯や補中益気湯は胃腸の蠕動運動を改善し、消化吸収を助けることで食欲不振や胃もたれを軽減する効果が期待できます。
漢方は体全体の調和をとる医学です。
夏バテで乱れがちな自律神経・消化器系の機能を穏やかに立て直し、根本から体調を整える点が漢方の大きな強みです。
根本的な体質改善を目指せる
漢方治療は、現在出ている症状を抑えるだけでなく、その背景にある体質そのものを改善していく「本治(ほんち)」の考え方があります。
夏バテしやすい人は、漢方的に見ると「気虚」(エネルギー不足)や「陰虚」(潤い不足)など体質的な弱点を抱えている場合が多いとされます。
漢方薬を用いてこうした体質を補正しておけば、将来夏バテになりにくい体を作ることにもつながります。
実際、漢方服用により胃腸が丈夫になった結果、夏場も食欲が落ちにくくなったり、疲れにくくなったりするケースがあります。
漢方は即効性のある対症療法だけでなく、“体質から強くする”根本療法でもあるため、夏バテを繰り返す方にこそおすすめです。
もちろん、現在つらい症状(倦怠感や食欲不振など)を取ることも大事であるため、漢方に加えて西洋薬を合わせて使い、本治(体質改善)と標治(症状緩和)を併用しながら総合的にアプローチします。
夏バテ対策に漢方を選ぶときの注意点

夏バテに漢方薬を使う場合、効果を十分に得るためにもいくつか注意すべきポイントがあります。
市販薬と処方薬の違いや、適切な薬剤選択の重要性、服用時の相談事項などを確認しておきましょう。
市販薬と処方薬の違いを知る
漢方薬には病院で医師が処方する医療用漢方薬と、ドラッグストア等で買える一般用漢方薬(市販薬)があります。
両者の大きな違いは有効成分の含有量(濃度)と入手経路(医師の診断があるか否か)です。
一般用漢方薬は、医療用(処方薬)の満量処方のだいたい50~80%程度の生薬成分量で作られており、「○○エキス(3/4量)」などと表示されていることがあります。
一方、医療用漢方製剤は基本的に満量処方(100%)で有効成分が含まれています。
このため、同じ名前の漢方薬でも市販薬はマイルドで軽い症状向き、処方薬はしっかり目に効かせたい場合向きといえます。
また、医療用は医師の診察と処方箋が必要ですが、保険適用で経済的負担を抑えつつ、専門的な指導の下で使えるといった利点があります。
一方、市販薬は手軽に入手できる反面全ての判断を自分で行う必要があるため、効果が不十分な場合や長引く場合は医療機関を受診した方が安全です。
症状に合うかどうかを見極める
前述のように、漢方薬は症状や体質に合っていないと十分な効果を発揮しません。
夏バテと感じても、その症状の出方は人によって様々です。
たとえば「食欲がなくて冷え症」の人と「汗をかき過ぎて脱水気味」の人とでは適する処方が違います。
自己判断で漢方薬を選ぶ際は、自分の症状にその薬の適応が合っているかをよく確認しましょう。
漢方薬の説明書には「○○の傾向がある人の△△(症状)に効果がある」といった記載がありますので参考にしてください。
また、「他の人に効いたから自分にも効くとは限らない」という点も肝に銘じましょう。
もし自分で判断が難しい場合は、無理に市販薬に頼らず、専門家に相談した方が結果的に早く改善することも多いです。
漢方の効果を最大限に得るには、今の自分の状態にマッチした処方を選ぶことが何より重要です。
使用前に専門家に相談する
漢方薬の選択や飲み方に迷ったら、必ず医師や薬剤師など専門家に相談しましょう。
特に、初めて漢方を試す方や持病のある方や妊娠中・授乳中の方などの場合、自己判断での服用は避けるべきです。
医師であればその人の体質・症状(証)を診断した上で適切な処方を決めることができるほか、薬剤師や登録販売者も漢方薬の基礎知識があるため、店頭で相談すれば市販漢方薬選びのアドバイスをもらえます。
漢方薬は一般に副作用が少ないと思われがちですが、全くないわけではなく、生薬によっては注意すべきものもあります。
例えば甘草(かんぞう)という生薬はむくみや血圧上昇などを起こすことがあり、既に高血圧の薬を飲んでいる場合など注意が必要です。
専門家に相談することで、体質や併用薬のチェックもしてもらえるため安心です。
夏バテに効く漢方を上手に取り入れるためにも、「自分に合った漢方薬はどれか?」ぜひプロの意見を仰いでください。
服用中の薬との飲み合わせを確認する
西洋薬を含め、現在服用中の薬がある方は漢方薬との相互作用に注意が必要です。
漢方薬だから安全ということはなく、成分によっては西洋薬と作用が重複したり、効果を増強・減弱させたりする可能性があります。
実際、複数の薬を同時に飲むと、一方の効き目が思ったように出なかったり、逆に強く出過ぎたりといった予期せぬ現象(相互作用)が起こることがあります。
特に別々の病院で処方された薬や、市販薬と処方薬を自分の判断で併用するのは絶対に避けてください。
夏バテで漢方薬を追加したい場合も、必ず主治医または薬剤師に相談し、飲み合わせの確認をすることが大切です。
例えば、鎮痛剤や睡眠薬を飲んでいる方が漢方を併用する際、それぞれに鎮静作用のある生薬が入っていると眠気が強く出過ぎるかもしれません。
また持病の薬との兼ね合いで漢方の選択肢が絞られる場合もあります。
専門家に伝える際は、サプリメントも含め、今飲んでいるものを全てリストアップすると良いでしょう。
安心・安全に漢方を活用するために、飲み合わせのチェックは怠らないようにしてください。
関連記事:熱中症に漢方薬は有効?症状別のおすすめ処方と注意点を解説
夏バテ対策で子どもや高齢者に漢方を使用できる?

夏バテは子どもからお年寄りまで幅広い年代で起こり得ます。
以下では、子ども・高齢者それぞれの場合について、漢方を服用する際のポイントを解説します。
子どもに漢方薬を使う場合のポイント
漢方薬は小児科領域でもしばしば使われており、子どもにも適切な用量を守れば使用可能です。
むしろ西洋薬よりマイルドで副作用が少ないため、小児にとって安心なケースもあります。
夏バテ気味の子どもには、まずは生活リズムの改善や食事指導が基本ですが、どうしても食欲不振や夏の疲れが強いとき、漢方薬が助けになることがあります。
例えば五苓散(ごれいさん)は暑気あたりによる脱水症状に効果があり、 特に子どもの夏バテに有効とされています。
汗っかきでのどの渇きを訴え、尿が少ないようなときに五苓散を用いると水分バランスが整い元気を取り戻しやすくなります。
ほかにも胃腸が弱く夏に下痢しやすい子には小建中湯(しょうけんちゅうとう)などが体力強化に使われることがあります。
子どもへの漢方の注意点としては、大人より体重当たりの用量を少なく調整する必要があること、粉薬の風味に慣れない場合があることが挙げられます。
甘く飲みやすい漢方(例:小建中湯や黄耆建中湯)から試す、オブラートに包む、ジュースに混ぜる等の工夫で服用しやすくできます。
また市販の小児用漢方薬もありますが、できれば小児科医や薬剤師に相談して処方してもらう方が安心です。
子どもは代謝が良く薬の効きも早い反面、急に症状が悪化しやすいので改善しないときはすぐ受診するようにしましょう。
高齢者に漢方薬を使う場合のポイント
高齢者は暑さによる脱水や食欲低下で夏バテになりやすい一方、持病で多くの薬を飲んでいたり臓器機能が低下していたりすることが多く、漢方の使い方にもコツがあります。
基本的には高齢者も漢方薬を使用できますが、体力に応じた処方選択と用量調整が重要です。
例えば、同じ夏バテでも高齢の方には補中益気湯より清暑益気湯の方が合う、といったケースがあります。
清暑益気湯は補中益気湯に生脈散を加えているため、より体力の落ちた高齢者の夏バテ状態に適するよう工夫された処方ともいえます。
高齢者の夏バテでは、まず六君子湯がよく使われます。
六君子湯は食欲増進効果があり、特に少食で栄養不足になりがちな高齢者の夏バテ予防に役立ちます。
グレリンという食欲ホルモンを介して食欲を高める作用が確認されており、食事療法の補完として有用です。
さらに症状が進んで貧血気味・皮膚乾燥も見られる場合は十全大補湯といった強めの補剤を使うこともあります。
一方で、高齢者は腎機能などが落ちているため、生薬の分解や排泄に時間がかかることがあります。
少量から開始して様子を見る、副作用(例えば甘草によるむくみや血圧上昇)に注意する、といった配慮が必要です。
もちろん、多剤併用による相互作用にも注意しましょう。
食事や生活習慣でできる漢方的セルフケア

夏バテを防ぐには、漢方薬だけでなく日々の生活養生も欠かせません。
漢方的な視点で生活習慣を整えることで、夏バテになりにくい体をつくるセルフケアが可能です。
ここでは、すぐに実践できる5つのポイントを紹介します。
生活リズムを整える
夏休みや連日の暑さで生活リズムが乱れると、自律神経が不調をきたし夏バテに繋がります。
規則正しい生活を心がけ、夜更かしや朝寝坊を避けましょう。
朝はできるだけ決まった時間に起きて朝日を浴び、夜も一定の時間になったら寝る習慣をつけると体内時計が整います。
適度な運動(朝の涼しい時間の散歩など)は生活リズムの調整に役立ち、暑さへの順応力も高めます。
漢方では「早寝早起き」を養生の基本とし、夜更かしは気血の消耗を招くと考えます。
休日も含めリズムが大きく崩れないよう意識してみてください。
生活リズムの安定は自律神経の安定につながり、夏バテしにくい体質作りの第一歩です。
栄養バランスの取れた食事
夏バテ予防・解消には食事の質が極めて重要です。
暑くて食欲がなくても、3食きちんと食べて胃腸に栄養と水分を入れておくことが大切だとされています。
特に朝食を抜かないことで、一日のエネルギーと体内時計のリセットができます。
食事内容は、タンパク質・ビタミン・ミネラルをバランスよく摂りましょう。
汗で流れ出るカリウムやマグネシウムは野菜や海藻・豆類から補給できます。
漢方的には、胃腸を労わるため冷たい飲食を摂りすぎないこともポイントです。
冷たいビールやアイスばかりでは胃腸が冷えて働きが低下し、栄養吸収も悪くなります。
なるべく常温~温かい食べ物・飲み物を摂り、胃に優しい消化の良いもの(お粥、うどん、茹で野菜、スープなど)を選ぶと良いでしょう。
睡眠をしっかりとる
十分な睡眠は夏バテ回復の基本です。
人間は寝ている間に体を修復しエネルギーを蓄えますが、夏の夜は暑さで寝苦しく睡眠不足に陥りがちです。
睡眠不足は自律神経の乱れを招き、さらに夏バテを悪化させてしまうでしょう。
対策として、寝室の温度・湿度を快適に保つことから始めます。
エアコンのタイマー設定や扇風機の併用で、室温は約27〜28℃前後、湿度は50~60%程度に保つのが目安です。(暑くて眠れない場合は無理に我慢せず冷房を適度に使ってください)
また就寝前に熱いお風呂は避け、ぬるめの湯に浸かって深部体温を下げると寝付きが良くなります。
夜更かしをせず、毎日6~8時間程度の睡眠時間を確保しましょう。
漢方では「昼は陽・夜は陰」として、夜の睡眠で体の陰(潤いと安静)を養うと考えます。
真夏でも質の良い睡眠がとれるよう環境を整え、体と自律神経をしっかり休ませることが夏バテ回復には不可欠です。
身体を冷やし過ぎない
現代の夏はエアコンなしでは過ごせませんが、冷やし過ぎには要注意です。
長時間強い冷房の中にいると、外気との温度差で自律神経が乱れるだけでなく、体そのものも冷えてしまいます。
冷えは漢方で「万病の元」とされ、夏でも下半身や内臓を冷やすと消化機能が落ちたり抵抗力が下がったりします。
対策として、エアコンの設定温度は25~28℃程度を目安にし、直接冷風が体に当たらないようにしましょう。
オフィスや電車で冷える場合は、上着やひざ掛け、腹巻きなどで調節し、首・お腹・足首など冷えやすい部分を守る工夫をします。
また冷たい飲み物やアイスの摂りすぎも体の内側から冷やしますのでほどほどに。
生姜入りの温かいお茶やスープは体を内側から温める効果があるのでおすすめです。
暑い時こそ「冷やし過ぎない」ことを意識し、適度に汗をかいて体温調節する力を維持しましょう。
特に女性や高齢者は冷房による、いわゆる「クーラー病(冷房病)」になりやすいので、温活グッズや入浴で体を温める習慣も取り入れてください。
こまめな水分補給
暑い夏において水分とミネラルのこまめな補給は基本中の基本です。
人はのどが渇いたと感じる時には既に軽い脱水状態に陥っていることがあります。
大量に汗をかいた後で一度に水を飲んでも、体が吸収しきれず尿として出てしまうため、少量を頻回に摂るのがポイントです。
目安としては「1時間にコップ1~2杯(約200mlずつ)」程度を意識すると良いでしょう。
特に屋外で活動するときや運動時は、経口補水液やスポーツドリンクで塩分も補給すると効果的です。
普段の食事から水分をとることも重要で、汁物や果物など水分を多く含む食品を活用しましょう。
関連記事:食欲不振のタイプ別おすすめ漢方|効果的な飲み方や受診の目安を解説
漢方薬の処方ならオンラインメディカルクリニックにご相談ください

夏バテ対策に漢方薬の力を借りたいと思ったら、ぜひオンラインメディカルクリニックにご相談ください。
オンラインメディカルクリニックでは医師と漢方薬剤師がタッグを組み、患者さん一人ひとりの体質・症状を詳しく伺った上で数ある漢方薬の中から最適な処方を選び出します。
対面の受診が難しい方でも、スマートフォンやパソコンを使って自宅から気軽に診療を受けられます。
「パーソナル漢方」とは、オンライン診療を通じてオーダーメイドの漢方薬治療を提供するサービスです。
夏バテによる倦怠感や食欲不振といった症状はもちろん、冷え症やストレス、不眠など患者さんのさまざまなお悩みに合わせて漢方薬を処方できます。
さらに処方された漢方薬はご自宅まで直接お届けすることも可能です。
忙しくてクリニックに行く時間がない方、近くに漢方に詳しい医療機関がない方でも、オンラインメディカルクリニックなら待ち時間ゼロで専門的な漢方治療が受けられます。
当クリニックは保険診療にも対応し、薬剤師との緊密な連携により安全で質の高い医療を提供しています。
夏バテに苦しんでいる方、「漢方を試してみたいけど何を選べばいいか分からない」という方は、ぜひオンラインメディカルクリニックのパーソナル漢方でお気軽にご相談ください。
あなたの体質に合わせた漢方薬で、この夏の不調を乗り切るお手伝いをいたします。
まとめ
夏バテは日本の夏に多くの人が陥りがちな体調不良ですが、漢方という頼もしい味方を活用することで根本からの改善が期待できます。
今回解説したように、市販漢方と処方漢方の違いや使用時のポイントを踏まえ、ぜひ専門家の助言を得ながら安全にご活用ください。
さらに、漢方の考えに基づいた日頃の生活養生(早寝早起き、バランスの良い食事、適度な水分補給など)は夏バテしにくい体を作る基本です。
漢方薬の力と生活習慣の見直しを組み合わせることで、相乗効果で夏バテを予防・改善していきましょう。