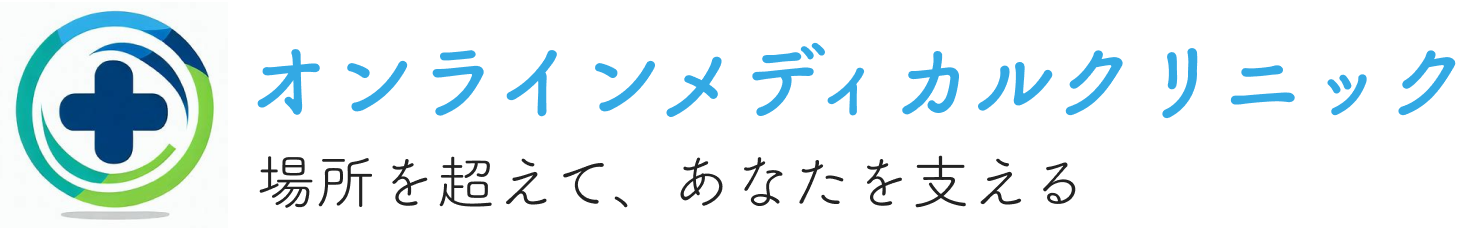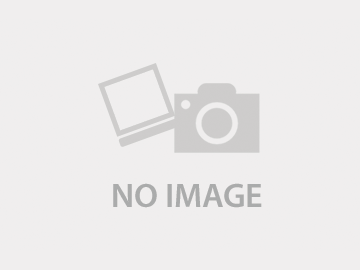現代のストレス社会では、イライラや不安、不眠などの症状に漢方薬が用いられることも増えています。
その中でも「抑肝散(よくかんさん)」「抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)」「柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)」の3つは、いずれも神経の高ぶりを鎮める効果で知られる漢方処方です。
しかし、それぞれの処方が適する「証(しょう)」―すなわち体質や症状のパターンには微妙な違いがあります。
本記事ではこれら3つの漢方の特徴と適応する証の違いを解説します。
学術的な知見も交えつつ、どのような体質・症状の方にそれぞれが合っているのかを詳しく見ていきましょう。
最後にオンライン診療で漢方薬を処方してもらうメリットについても触れます。
漢方における「証」とは何か?

「証(しょう)」とは、漢方医学で治療方針を決めるための体質・症状の総合的なパターンのことです。
西洋医学の病名とは異なり、患者さん一人ひとりの体力(虚実)や冷え・熱感、症状の現れ方などを総合して「○○の証」と判断します。
漢方薬はこの証に基づいて選択され、同じ不眠でも体質によって処方が変わるのはそのためです。
では、「抑肝散」「抑肝散加陳皮半夏」「柴胡加竜骨牡蛎湯」の3処方について、それぞれどのような証に合うのかを詳しく見ていきましょう。
関連記事:ストレスによる頭痛の原因と対策|セルフケアや薬で解消する方法
抑肝散(よくかんさん)の証:神経過敏だが体力は虚弱なタイプ

まずは抑肝散です。
抑肝散は江戸時代に小児のひきつけ(痙攣)を治す処方として考案された経緯があり、本来は子供の神経症状に対する薬でした。
現在では大人にも広く用いられ、不安や興奮、イライラを鎮める代表的な漢方薬として知られています。
抑肝散が適応となる症状は、公式には「虚弱な体質で神経が高ぶるものの神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症」などとされています。
つまり体質が弱く細身で、顔色が悪いような人が、ちょっとした刺激でイライラしたり不眠になったりするようなイメージのケースです。
小児の夜泣き(夜驚症)や疳の虫(神経過敏でかんしゃくを起こしやすい子)にも効果があります。
抑肝散が合う体質(証)は、一言で言えば「血が不足して神経がとげとげした状態」です。
漢方的には「肝血不足による肝の亢進」とも表現され、イライラや怒りっぽさ、不安感など神経症状が目立ちます。
具体的には神経が細かくて興奮しやすい人、ストレスで筋肉が緊張しやすい人、些細なことで怒りっぽくなる人などが該当します。
漢方の古典的表現では「肝気が張っている」状態とも言えます。
抑肝散には鎮静・鎮痙作用のある生薬(釣藤鈎や柴胡など)が含まれ、神経の高ぶりやそれに伴う筋肉のこわばりを和らげます。
そのため、不安神経症の患者さんに用いると落ち込みや怒りによる興奮発作を抑える効果が期待できます。
実際、認知症の周辺症状(BPSD)にも有効との研究報告があり、比較的安全に高齢者にも使える穏やかな処方です。
ただし、抑肝散は消化器系を調整する生薬が少ないため、胃腸の弱い方ではまれに食欲不振や胃の不快感、吐き気などが生じることがあります。
実際、添付文書でも「著しく胃腸の虚弱な患者、食欲不振・悪心・嘔吐のある患者」への慎重投与が記載されています。
そうした胃腸症状を伴うケースでは、次に述べる抑肝散加陳皮半夏の方が適しています。
抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)の証:ストレスに弱く胃腸虚弱なタイプ
抑肝散加陳皮半夏は、その名の通り抑肝散に陳皮(ちんぴ)と半夏(はんげ)という2つの生薬を加えた処方です。
追加された陳皮・半夏は、ともに胃腸の機能を助け痰湿(たんしつ:消化器における水分代謝の滞り)を取り除く作用があります。
そのため、抑肝散では胃にもたれてしまうような人でも、吐き気や腹部膨満感を抑えて服用しやすくしているのが特徴です。
抑肝散加陳皮半夏が適応となる症状は、基本的には抑肝散と同様に神経の高ぶりによるイライラ、不安、不眠ですが、そこに胃腸症状が加わる点が特徴です。
具体的にはストレスがかかると胃が痛くなったり吐き気がしたりする、あるいはお腹が張る、食欲がないといった症状を併発する場合に適しています。
例えば受験生や仕事でプレッシャーの多い中間管理職が、緊張で朝に腹痛や頭痛を起こすようなケースに応用されます。
イライラしやすく貧乏ゆすりやチックが見られるけれど、同時に胃弱であるようなタイプです。
抑肝散加陳皮半夏が合う体質(証)は、抑肝散の証に「気虚・血虚」すなわちエネルギー不足・血の栄養不足が加わり、ストレスへの抵抗力が低下した状態と説明されています。
その結果、軽い精神的刺激や肉体的刺激にも過敏に反応して自律神経が乱れやすいとされています。
言い換えると、体力があまり無く、胃腸が弱い人がストレスでイライラ・怒りっぽさなどの精神症状と消化器症状を起こしている状態に適合します。
漢方では抑肝散加陳皮半夏の証について「肝気が高ぶって発散できず、気が鬱滞して胃にも影響した状態」と表現することもあります。
抑肝散加陳皮半夏は、実際の臨床でもうつ症状が長引いて胃腸障害を併発している方によく使われます。
イライラ感や易怒性、筋肉のこわばりなど抑肝散証の精神神経症状に加えて、食欲低下や消化不良といった症状がある場合にこの処方が選択されます。
まとめると、「神経が高ぶりやすくイライラするけれど、胃腸が弱く体力がない人」が抑肝散加陳皮半夏のターゲットです。
ストレスで胃痛や吐き気まで起こしてしまうような繊細な方に向いていると言えるでしょう。
関連記事:抑肝散とは?現代人の「なんとなく不調」に効く漢方薬の効果
柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)の証:比較的体力があり精神的昂ぶりが強いタイプ
最後に柴胡加竜骨牡蛎湯です。名前に含まれる柴胡(さいこ)は小柴胡湯などでも有名な生薬、竜骨(りゅうこつ)と牡蛎(ぼれい)は動物由来の鎮静薬(化石化した骨や貝殻)です。
この処方は、中国の古典『傷寒論』に由来し、もともと精神錯乱や不眠、動悸などを伴う重い神経症状を治すために考案されました。
処方構成としては小柴胡湯という漢方の基本方剤に、鎮静作用の強い竜骨・牡蛎や緩下薬の大黄などを加味した形になっており、心身両面に強めの作用を持つのが特徴です。
柴胡加竜骨牡蛎湯が適応となる症状は、抑うつ、不安、不眠、動悸など精神神経症状が幅広く含まれます。
さらに特徴的なのが、のぼせ(顔面紅潮やほてり)や便秘、胸や腹部の圧迫感など、興奮に伴う身体症状も見られる点です。
典型的には動悸が激しく、寝付きが悪いような不安神経症に使われますが、その他にも高ぶりすぎて怒りやすい躁状態や軽い精神錯乱、てんかん発作後の精神不安定などにも昔から用いられてきました。
柴胡加竜骨牡蛎湯が合う体質(証)は、「比較的体力が充実していて、精神的な昂ぶりが強い人」と表現できます。
漢方医学的には少陽病から陽明病に近づく中間証とも言われ、簡単に言えば小柴胡湯証(中程度の体力で胸脇苦満=胸の張りがある)と大柴胡湯証(体力が充実し便秘やのぼせを伴う)の中間くらいのイメージです。
具体的な特徴として、みぞおちからおへそにかけて動悸(心臓の鼓動)を感じるという独特の症状があります。
これは漢方でいう「心下悸(しんかき)」と呼ばれる症状で、柴胡加竜骨牡蛎湯の重要な目安です。
加えて、神経が過敏で些細なことに動揺しやすいが、同時に体力はある程度あり、顔や上半身に熱感を持ちやすいといった傾向があります。
極端な虚証(ひ弱な人)には向かず、どちらかといえばがっしりした人や若年〜中年でエネルギーのある人に使われます。
柴胡加竜骨牡蛎湯には、精神面を安定させる竜骨・牡蛎のほか、余分な「熱」や老廃物を発散・排泄させる大黄や茯苓などが含まれます。
そのため、ストレスで生じる動悸や便秘、のぼせ、イライラといった身体・メンタル両面の症状を一挙に改善する効果が期待できます。
実際、「漢方の中では効果が強い薬」であり「虚弱な方には向かないが、比較的体力のある方で神経過敏による動悸・不眠が強いときに使われる」と解説されています。
3つの漢方処方の証の違いまとめ

ここまで抑肝散、抑肝散加陳皮半夏、柴胡加竜骨牡蛎湯のそれぞれについて見てきました。証の違いを簡単にまとめます。
抑肝散:「神経過敏だが虚弱体質」の人向け。
- イライラや不安、不眠など精神症状が中心
- 体力はあまり無く、血の不足による神経過敏
- 胃腸症状は伴わないか軽度
例:疲れやすく肩こりしやすい虚弱な人が、些細なことで興奮し不眠になる場合。
抑肝散加陳皮半夏:「神経過敏かつ胃腸虚弱」の人向け
- 基本的な精神症状は抑肝散と同じ+消化器症状(胃もたれ・吐き気など)
- 体力がより低下し、気虚・血虚が見られる
- ストレスで胃痛・食欲不振などが起こりやすい。
例:緊張するとすぐお腹を壊したり吐き気がする繊細な人が、イライラ・不安で睡眠も不安定な場合。
柴胡加竜骨牡蛎湯:「神経過敏だが体力充実」の人向け
- 不安・不眠など精神症状+動悸・便秘・のぼせ等の身体症状も顕著
- 中間証~やや実証寄りで、熱感・興奮が強い
- お腹に脈打つ感じがあることも。
例:ストレスで興奮状態になり、胸がドキドキして眠れず、便秘や顔のほてりまで伴うような場合。
以上のように、似たような「イライラ、不眠」に使われる漢方薬でも、患者さんの体質や随伴症状によって使い分けられているのです。
それぞれの特徴を把握することで、「自分にはどれが合いそうか?」の目安になりますが、最終的な判断は専門の医師に任せるようにしてください。
オンライン診療で漢方薬を処方してもらうメリット
忙しい現代人にとって、漢方の専門医にかかるためにわざわざ受診するのはハードルが高いかもしれません。
そのような場合、オンライン診療を活用するのも一つの方法です。オンライン診療には次のようなメリットがあります。
遠方の専門医にかかれる
居住地の近くに漢方に詳しい医師がいなくても、オンラインで全国の医療機関から診察を受けられます。
通院の負担軽減・感染リスク低減
自宅で診察が完結するため、移動時間や待ち時間がありません。また病院に行かないことで他の人から病気をもらう心配も減らせます。
処方薬を自宅で受け取れる
オンライン診療後の処方箋は、郵送されたり連携薬局から自宅に薬が配送されたりすることもあります。
仕事や育児で忙しい方でも、家にいながら必要な漢方薬を入手できるのは大きな利点です。
このようにオンライン診療を使えば、時間や距離の制約を減らして漢方治療を受けることが可能です。
ただし、初診からオンライン診療が可能かどうかはクリニックによって異なる場合がありますし、保険適用に関するルールも変わることがあります。
利用したい場合は各医療機関の情報を確認し、医師の指示に従ってください。
関連記事:ストレスによる食欲不振の原因とリスク:オンライン診療と漢方でできる改善策
関連記事:民間救急車とは?消防救急車との違いや利用が検討されるケース|よつば民救
まとめ
抑肝散、抑肝散加陳皮半夏、柴胡加竜骨牡蛎湯の3つの漢方について、それぞれ適する「証」(体質・症状)の違いを解説しました。
簡単に言えば、抑肝散は虚弱な神経過敏タイプ、抑肝散加陳皮半夏は虚弱+胃腸症状タイプ、柴胡加竜骨牡蛎湯は比較的体力があり興奮症状も強いタイプに使われます。
漢方ではこのように処方ごとに適した証が細かく設定されています。自己判断での服用は避け、症状に悩む場合は専門医に相談してみましょう。
オンライン診療も活用しつつ、自分の体質に合った漢方治療で不調の改善を目指してください。
監修医
島村泰輝
- 2012年3月 名古屋市立大学医学部 卒業
- 2014年4月 名古屋市立大学放射線科 入職
- 2015年4月 名古屋市立大学大学院博士課程入学 (専攻:生体防御・総合医学分野)
- 2019年3月 同大学院卒業、博士号取得
- 2019年6月 株式会社エムネス 入職
- 2022年10月 同 Medical Professional Service(医師部門)副本部長
- 2023年7月 オンラインメディカルクリニック開業
愛知県名古屋市出身。遠隔放射線画像診断を行う傍ら、AI開発、メディカル用プロダクト開発を行う。
医療としてはその他にも内科診療、訪問診療にも従事。医療はITでさらに良くなる事を信条として様々な取り組みを行う。
物理的、時間的に医療が届きにくい層に対して医療を届けるべくオンライン診療を中心としたクリニックを開業。今後は各種専門家とともに、遠隔地であっても質の高い医療を提供するサービスを構築していく。