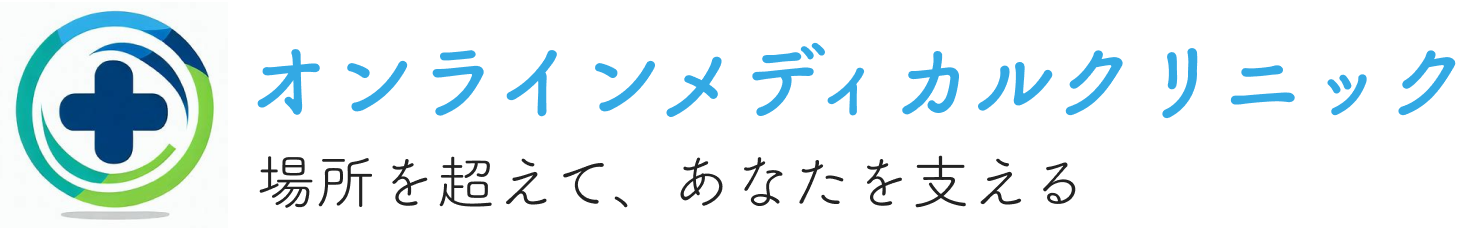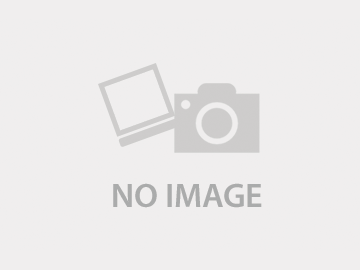毎年の健康診断で受け取る結果表には、「A判定」「B判定」「C判定(要経過観察)」「D判定(要精密検査)」「E判定(要治療)」などの文字が並んでいます。
初めてこれらの判定を目にしたとき、どう対応すればよいのか迷ってしまう方も多いでしょう。
この記事では、健康診断の判定の意味をしっかりと理解し、それぞれの判定が出た場合に具体的にどのような行動をとるべきなのか、詳しく解説していきます。
健康診断の判定(A~E)の具体的な意味

健康診断の判定は、自分の健康状態を客観的に把握するための重要な指標です。それぞれの判定が示す内容は以下の通りです。
| 判定 | 意味 | 対応目安 |
| A | 正常(異常なし) | 日常生活を維持し、年に一度の健康診断で経過を観察 |
| B | 軽度異常(経過観察) | 生活習慣の改善で十分対応可能なレベル。次回の健康診断までに改善を目指す |
| C | 要経過観察 | 放置すると悪化するリスクあり。
半年〜1年後の再検査を行い、積極的な生活改善が必要 |
| D | 要精密検査・要治療 | 早急に医療機関を受診し、より詳しい検査で病気の有無を明確にする必要がある状態あるいは明らかな病状があり、治療が必要な状態。
直ちに医師の指示に従い治療を開始または継続する状態。 |
| E | 治療中 | 既知の病変に対して医療機関で治療を行っているもの |
健康診断の結果は健康管理の重要なヒントです。特に「C判定」以上が出た場合には、放置せず適切な行動を取ることが大切です。
関連記事:ストレスによる頭痛の原因と対策|セルフケアや薬で解消する方法
B判定・C判定が出たときは
「軽度異常」「要経過観察」といったB判定やC判定の場合は、比較的軽度の状態ではありますが、決して油断はできません。
特にC判定では、「まだ大丈夫」と放置してしまうと、将来的に生活習慣病などのリスクが大きくなります。
具体的には以下の行動を取るとよいでしょう。
• 健診結果に記載されている再検査のタイミング(半年〜1年後)を守り、再検査を受ける
• 定期的に自宅で血圧、血糖値、体重を測定し記録することで改善の経過を把握する
• 食生活を改善し、塩分・脂質・糖質を控えるなど具体的な目標を立てて取り組む
• ウォーキングなど適度な運動を習慣化し、ストレスや疲労を溜め込まない生活を意識する
この段階での早めの対応が、将来的に大きな病気を未然に防ぐ重要なポイントになります。
放置するとD判定、E判定の状態になっていくことがあるため、少しでも良いのでできる事をはじめて行きましょう。
D判定の場合は迅速な対応が必要!

D判定を受けたら、放置することは絶対に避けなければなりません。
症状が出ていない場合でも重大な病気が潜んでいる可能性があるため、以下の対応を推奨します。
• 結果が届いたらすぐに、一般内科や専門医(循環器内科、内分泌代謝内科、消化器内科など)を受診
• 会社の健康保険組合などが提供する二次検診制度を積極的に利用して、精密検査を速やかに行う
精密検査によって病気の早期発見・早期治療が可能になり、健康リスクを大きく低減できます。症状が無い状態で見つけ、かつ早めに治療を開始することが大事です。
関連記事:寒暖差アレルギーで咳が止まらない原因とは?セルフチェックと治療薬で対策
健康診断でよく指摘される異常値とそのリスク
健康診断で指摘されやすい異常項目には以下のようなものがあります。具体的な数値と放置した場合のリスクを把握しておきましょう。
| 項目 | 異常値の目安 | 放置した場合のリスク | 適切な診療科 |
| 血圧 | 160/100 mmHg以上 | 脳卒中・心筋梗塞 | 一般内科・循環器内科 |
| LDLコレステロール | 160 mg/dL以上 | 動脈硬化、心筋梗塞 | 一般内科・循環器内科 |
| 血糖(空腹時) | 126 mg/dL以上、HbA1c 6.5%以上 | 糖尿病・腎障害・網膜症 | 内分泌代謝内科・一般内科 |
| 肝機能(AST・ALT・γ-GTP) | 基準値の2倍以上 | 肝硬変・肝臓がん | 消化器内科 |
| 中性脂肪 | 300 mg/dL以上 | 動脈硬化、虚血性心疾患 | 一般内科・循環器内科 |
これらはいずれも症状が無い事が多いです。例えば高血圧は放置すると脳卒中を起こすことがあり、命が危険になることもあります。
異常値が示されたら、適切な診療科を受診し、詳しい検査と治療を受けましょう。
日常生活でできる健康改善の具体策

健康診断で指摘を受けた場合、日常生活の見直しが非常に有効です。具体的には以下のポイントを実践してみるのも良いでしょう。
• 食生活の見直し:減塩(1日6g未満)、野菜・魚・大豆製品を中心にバランスよく摂取
• 運動習慣の確立:週3回以上の有酸素運動(ウォーキングやジョギングなど)を行う
• 禁煙・節酒:喫煙をやめ、飲酒は適量に抑える
• 睡眠とストレス管理:7時間以上の良質な睡眠を確保し、趣味などで適度にストレスを発散
具体的な目標や対応の仕方は医師と相談するのもおすすめです。
杓子定規な対応ではなく、その他の項目や実際の体調、生活や仕事の内容などを考慮して何を重点的に行うか、どのように改善していくのが良いかを話し合うことができます。
忙しい方こそオンライン診療の活用を
最近はスマホなどを使ったオンライン診療が普及しています。
忙しくてなかなか病院に行けない方は、オンライン診療で医師と手軽に相談できます。
• C判定で再検査の前に不安を感じたとき
• 生活習慣の改善方法についてアドバイスが欲しいとき
ただし胸痛や激しい息切れなどの症状は、直接病院を受診してください。
健康診断の結果を正しく理解し、適切に行動することが健康への第一歩です。
小さな異常でも軽視せず、積極的に健康管理に取り組んでいきましょう。
監修医
島村泰輝
- 2012年3月 名古屋市立大学医学部 卒業
- 2014年4月 名古屋市立大学放射線科 入職
- 2015年4月 名古屋市立大学大学院博士課程入学 (専攻:生体防御・総合医学分野)
- 2019年3月 同大学院卒業、博士号取得
- 2019年6月 株式会社エムネス 入職
- 2022年10月 同 Medical Professional Service(医師部門)副本部長
- 2023年7月 オンラインメディカルクリニック開業
愛知県名古屋市出身。遠隔放射線画像診断を行う傍ら、AI開発、メディカル用プロダクト開発を行う。
医療としてはその他にも内科診療、訪問診療にも従事。医療はITでさらに良くなる事を信条として様々な取り組みを行う。
物理的、時間的に医療が届きにくい層に対して医療を届けるべくオンライン診療を中心としたクリニックを開業。今後は各種専門家とともに、遠隔地であっても質の高い医療を提供するサービスを構築していく。