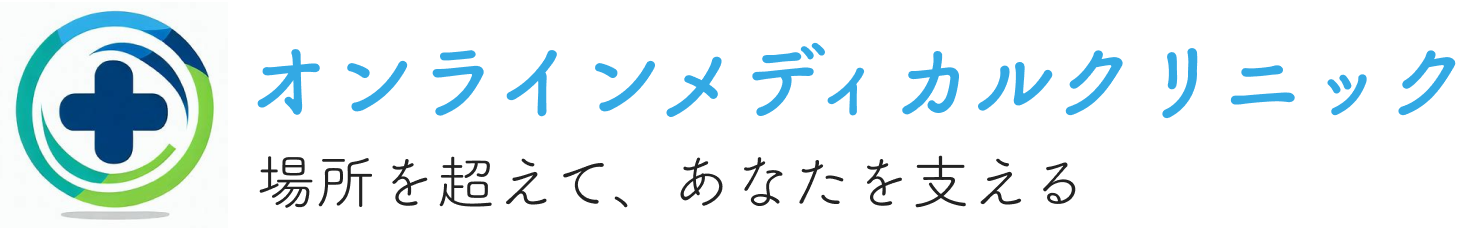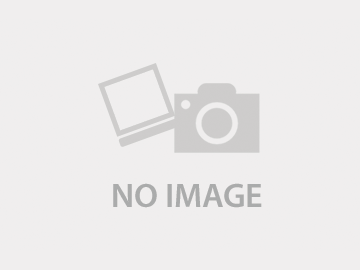夏の暑さや湿気によって「夏バテ」を起こすと、全身のだるさや食欲不振といった症状が現れます。
即効で完治させることは難しいものの、生活の工夫や食事の改善によって症状が軽くなる可能性があります。
本記事では夏バテの原因や症状をはじめ、日常の中でできる予防策や受診の目安までをわかりやすくご紹介します。
夏バテとは?

夏バテとは、高温多湿な夏の環境に体が対応できず、自律神経が乱れるために起こる体調不良のことです。
主な症状は体のだるさや疲れやすさ・食欲の低下などで、頭痛・めまい・立ちくらみ、イライラ感など多様な症状が現れます。
単に暑さが厳しいときはもちろん、屋外と室内を出入りしたときの温度差や、汗によってミネラル不足になること、夜の寝苦しさによる睡眠不足などが影響することもあるでしょう。
夏バテを放置してしまうと、免疫力の低下によって夏風邪を引いたり、脱水症状を起こして体調不良が長引いたりする可能性もあります。
リンナイ株式会社の調査によれば、日本の夏では約8割の人が夏バテを経験するともいわれており、早めの対策が重要といえます。
引用元:リンナイ株式会社. 全国20~69歳の男女400人に聞いた「夏のお風呂事情」
夏バテを即効治すことはできる?
結論からいえば、夏バテを即効で治すことはできません。
体力の消耗や自律神経の乱れが原因となるため、一瞬で完全に元通りになるわけではなく、適切な対処によって徐々に症状を緩和させる必要があります。
これからご紹介するいくつかの対策を試し、回復を早めて症状を和らげる工夫を行いましょう。
栄養のあるものを摂る
夏バテで弱った身体には、エネルギー補給が有効です。
特にビタミンB1やクエン酸は疲労回復を手助けする効果があるため、豚肉・トマト・ウナギ・レモン・梅干しなどを積極的に摂取しましょう。
食欲がないときは、温かい味噌汁を飲むだけでも栄養補給になります。
軽い運動やストレッチ
適度な運動は血行を促進し、自律神経のはたらきを整える効果があります。
激しい運動は却って体調不良を招いてしまうため、負担のかかりにくいストレッチや体操を中心に行いましょう。
ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる
夏は暑さからシャワーで済ませてしまいがちですが、38~39℃程度のお湯に浸かることで、副交感神経が優位になりリラックスにつながります。
湯船に浸かって身体を温めることで、睡眠の質も向上しやすくなります。
ツボ押し・マッサージ
足裏のツボを刺激すると血行が良くなり、自律神経を整えるのに役立つとされています。
例えば足裏中央の「湧泉(ゆうせん)」は全身のだるさに、足首内側の「三陰交(さんいんこう)」は冷え症に効くといわれています。
専門知識がない方でも、気持ちいいと思える程度のマッサージをするだけで、血行が促進されスッキリできるでしょう。
関連記事:熱中症に漢方薬は有効?症状別のおすすめ処方と注意点を解説
夏バテを改善する食べ物と飲み物

夏バテになってしまったときは、食事と飲み物を工夫して体調を整えることが重要です。
続いては、食欲がないときでも食べやすいおすすめの食材や、夏バテ対策に効果的な飲み物を紹介します。
食欲がない時におすすめの食材
夏バテで食欲が落ちているときは、無理にたくさん食べようとせず、少量でも栄養が摂れるものを取り入れることが大切です。
酸味のある食べ物で食欲増進
梅干しやレモン・お酢を使った料理などの酸っぱいものは、唾液や胃液の分泌を促し、落ちた食欲を増進させてくれます。
特に梅干しは手軽に取り入れやすく、1粒食べるだけでも夏バテ対策になります。
レモンやオレンジなどの柑橘類も、クエン酸を豊富に含む上、さっぱりしているので喉を通りやすいでしょう。
香味野菜や適度なスパイスを活用
食欲がない時でも、ショウガや大葉・ミョウガといった香味野菜は食欲を刺激してくれます。
冷たいそうめんしか喉を通らないときも、刻みネギや生姜などの薬味をたっぷり乗せると風味が増し、同時に栄養も摂取できます。
カレー粉のスパイスも効果的で、香りを嗅いだだけでお腹が空いてくることもあるでしょう。
ただし、唐辛子など香辛料の摂り過ぎは却って胃に負担がかかるため、適度に利用することが大切です。
消化に良く栄養価の高いタンパク質
食欲がないときも、体力維持のためにタンパク質の摂取が欠かせません。
脂身の少ないささみ肉や白身魚・豆腐などは、食べやすく消化も良いタンパク源です。
高タンパク・低脂肪の代表的な食材として、かまぼこやちくわなどの練り物もおすすめです。
冷たいものばかり・単調な食事は避ける
食欲がないと、ついそうめんやアイスといった冷たいものだけで食事を済ませてしまいがちです。
しかし同じものばかり食べていると栄養が偏り、却って夏バテを長引かせてしまうでしょう。
できるだけ主菜・副菜を組み合わせ、栄養バランスを意識した食事を心がけることが大切です。
夏バテ対策に効果的な飲み物

続いて、夏バテの症状を和らげるために効果的な飲み物を紹介します。
ただ水を飲むだけでなく、以下のような飲み物を上手に取り入れ、効率的な水分補給を目指しましょう。
水・ミネラルウォーター
夏バテ予防の基本はやはり水分補給です。
特にミネラル分を含む天然水(硬水)には、疲労感の改善に効果的なナトリウムやマグネシウムが豊富に含まれています。
汗で失われる水分・ミネラルを補うため、まずはこまめに水を飲む習慣をつけましょう。
オレンジジュース
100%オレンジジュースには、クエン酸が豊富に含まれています。
クエン酸には疲れのもととなる乳酸を分解するはたらきがあり、筋肉疲労の回復に効果的です。
ビタミンCも摂れるため、夏の栄養・水分補給にはピッタリの飲み物といえるでしょう。
ただし市販のオレンジジュースは糖分も多いため、飲み過ぎには注意が必要です。
アセロラジュース
アセロラは「ビタミンCの王様」と呼ばれており、フルーツの中でも随一のビタミンC量を含みます。
強い抗酸化作用を持つアントシアニンやポリフェノールも豊富に含まれており、紫外線の強い夏には積極的に摂取したい飲み物の一つです。
疲労回復はもちろん美肌効果も期待できるため、休憩時の一杯に取り入れてみるとよいでしょう。
トマトジュース
夏野菜の代表であるトマトには、抗酸化力の強い「リコピン」が含まれています。
活性酸素の発生を抑えて老化予防に役立つほか、トマトに含まれるクエン酸が食欲増進や疲労回復にも効果を発揮します。
甘酒(冷やし甘酒)
「甘酒は冬のもの」というイメージがありますが、実は江戸時代から夏の風物詩として親しまれ、暑気払いに効果的といわれていました。
麹から作られる甘酒にはブドウ糖や必須アミノ酸・ビタミンB群・食物繊維などが豊富に含まれ、その栄養価の高さから「飲む点滴」とも呼ばれます。
夏場は甘酒を冷やし、食欲がないときの栄養補給として利用するのもよいでしょう。
なお、大量に汗をかいた場合は、水に加えて塩分も補給できるスポーツドリンクや経口補水液(ORS)が有効です。
普段の水分補給には薄めのスポーツドリンクや麦茶等で十分ですが、脱水症状が疑われる場合は経口補水液を利用するとよいでしょう。
経口補水液はゆっくり飲むことが推奨されており、スプーンで飲んでいるようなイメージで飲むと効率的です。
夏バテで避けるべき食べ物と飲み物

夏バテのときに摂らない方が良いものや、症状を悪化させてしまう恐れのある食べ物・飲み物をご紹介します。
避けるべき食べ物
脂っこい料理
唐揚げ・とんかつなど油分の多い揚げ物は、夏バテで弱っている胃腸に大きな負担がかかります。
消化不良を起こしやすくなるため、症状がつらい間は避けましょう。
脂身の多い肉類やこってりした食事
スタミナをつけるために焼肉やうなぎをガッツリ食べるのも、夏バテの間は逆効果です。
こうした食品には脂質が多く含まれるため、胃腸が弱っている間は消化しきれず負担がかかってしまうでしょう。
どうしても肉類を食べたい場合は、脂肪分の少ないヒレ肉やささみなどを選び、少量から様子を見ることをおすすめします。
冷たいもの・甘いものの過剰摂取
アイスクリームやかき氷などの冷たいデザートは非常に魅力的ですが、体を冷やしすぎると胃腸の働きが低下し、夏バテが悪化することがあります。
また清涼飲料水や菓子類など糖分の多いものを摂り過ぎると、血糖の乱高下によってだるさを感じることもあります。
避けるべき飲み物
キンキンに冷えた飲み物(飲み過ぎ)
暑いと氷いっぱいのジュースやビールを飲みたくなりますが、冷たい飲み物の一気飲み・大量摂取は厳禁です。
胃腸が冷えて消化酵素の働きが弱まり、腹痛・下痢・消化不良を招くでしょう。
内臓の冷えは夏バテを悪化させる一因にもなるため、冷たいドリンクは一気に飲まず、常温に近い水をこまめに摂る方が賢明です。
アルコール類
アルコールには強い利尿作用があり、体内の水分が一気に失われます。
お酒だけを飲んでいると脱水症状を招き、夏バテどころか熱中症につながる危険もあります。
飲酒する際は必ず同量の水を一緒に飲む(チェイサーをとる)ようにし、体内の水分バランスを保つようにしましょう。
カフェインを含む飲み物
コーヒーや緑茶・エナジードリンクなどに含まれるカフェインも、利尿作用があり、水分補給には適していません。
これらは飲んだ分だけ体から水が出て行ってしまうため、水分摂取量にカウントしないようにしましょう。
糖分の多い清涼飲料・牛乳(大量に)
炭酸飲料や市販のスポーツドリンク・フルーツジュースなどの糖分が多い飲み物を飲み過ぎると、浸透圧の関係で脱水を招く恐れがあります。
牛乳も脂肪分が多いため、大量に飲むと消化不良を起こす可能性があるでしょう。
いずれも適量を意識し、飲み過ぎないことが大切です。
関連記事:イライラを和らげる漢方3選──抑肝散・抑肝散加陳皮半夏・柴胡加竜骨牡蛎湯の違いを解説
夏バテ対策に役立つ生活習慣

夏バテを防ぐためには、日々の生活習慣を整えることが大切です。
続いては夏バテ予防・改善に役立つ習慣として、睡眠・入浴・運動のポイントをご紹介します。
質の良い睡眠
夏バテ改善・予防の基本は十分な睡眠と休息です。
寝苦しい熱帯夜によって睡眠不足になると、自律神経の回復が妨げられ、疲労が蓄積してしまいます。
質の良い睡眠を確保するため、以下の点に気を付けましょう。
就寝環境を整える
室温は高すぎても低すぎても熟睡の妨げになります。
エアコンの設定温度は28℃前後を目安にし、タイマーや扇風機も活用して寝室を快適に保ちましょう。
室内と外気の温度差が5℃以上ある環境では夏バテになりやすいため、冷房の効きすぎにも注意が必要です。
生活リズムを規則正しく
夜更かしや寝不足が続くと体内時計が乱れ、睡眠の質も低下します。
平日も休日もなるべく毎日同じ時間に寝起きするよう心がけ、生活のリズムを整えましょう。
寝る前のスマホ・飲酒を控えたり、就寝前に温かいものを摂ったりといった工夫も大切です。
やむを得ず入眠時間が不規則になる方は、起床時間を揃えることでも体内リズムが整いやすくなります。
眠りやすくする工夫
就寝の2~3時間前に入浴をして体温を上げておくと、その後体温が下がる過程で入眠しやすくなります。
寝具を通気性の良い麻素材に変える、冷感シーツや冷却マットを利用するなど、少しの工夫で眠りの快適さが変わります。
湯船につかる習慣
前述のとおり、入浴(湯船につかること)は夏バテ対策に有効な習慣です。
暑い夏はついシャワーだけで済ませてしまいがちですが、それでは体の芯まで温まらず、自律神経のバランスを崩しやすくなります。
夏でもできれば39~40℃程度のお湯を溜め、首まで10~15分浸かるようにしましょう。
適度な運動で暑さに強い体づくり
無理なく汗ばむ程度の運動を継続して行い、暑さへの順応力を高めることが大切です。
普段あまり汗をかかないと、いざという時にうまく汗をかけずに熱を逃せません。
汗をかくトレーニング=「暑熱順化」に取り組み、普段から汗をかきやすい身体へ整えておくとよいでしょう。
方法としては、週に3~4回のペースでウォーキングや軽いジョギングを行い、身体を動かす習慣をつけるのがおすすめです。
1回の運動は30分程度ですが、発汗量や血流が増え、暑い環境でも体温調節がスムーズにできる身体に近づけます。
夏場は朝や夕方の涼しい時間を選び、直射日光を避けることも大切です。
夏バテで病院を受診すべき目安
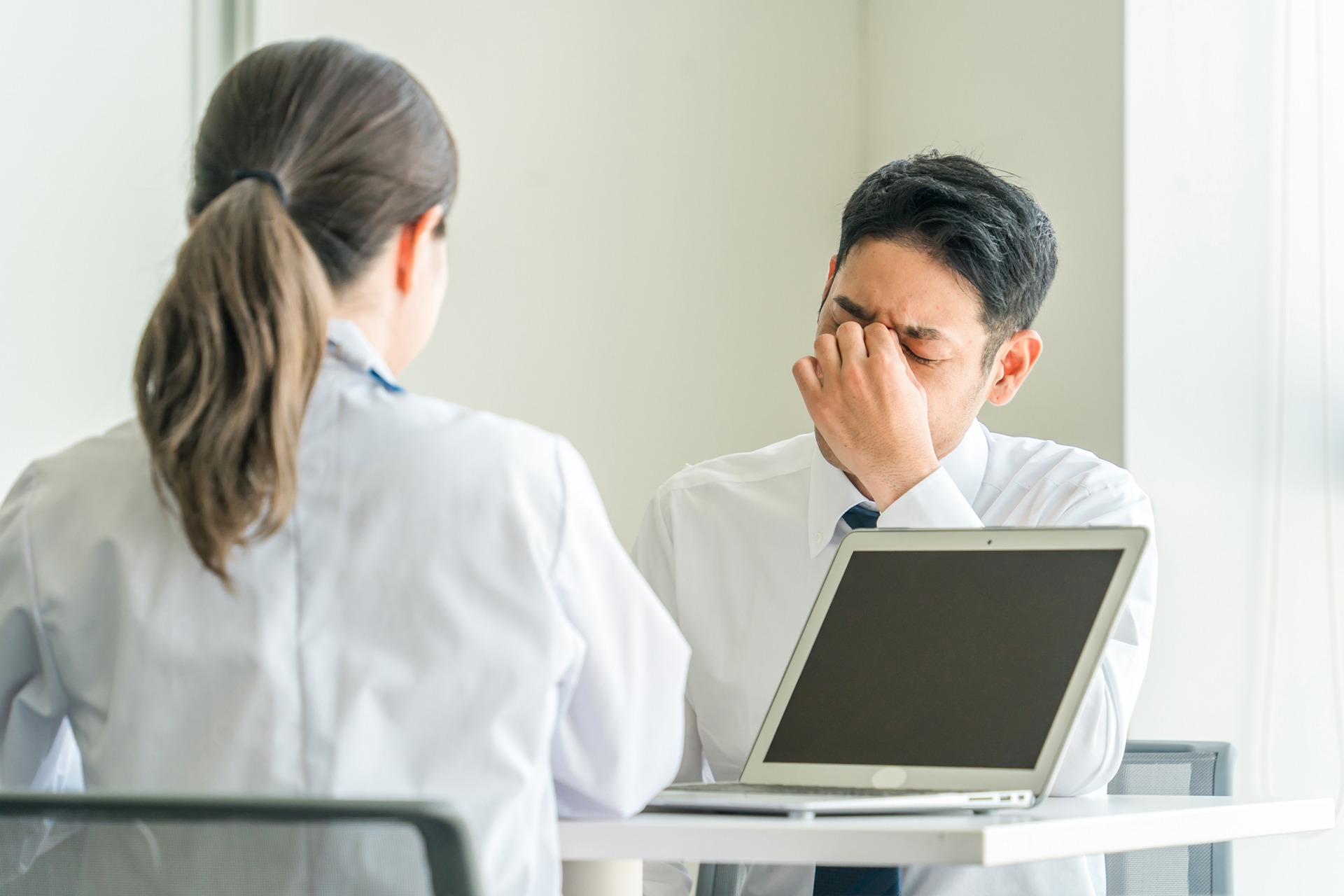
夏バテは多くの場合、上記のような対策で徐々に改善します。
しかし中には別の病気が隠れていたり、深刻な状態に陥ったりする可能性もあります。
次のような症状が続く場合は、早めに医療機関(内科など)を受診するようにしましょう。
夏バテの主な症状
夏バテを起こすと、全身の倦怠感、食欲不振、頭痛、めまい・立ちくらみ、下痢、吐き気、微熱、むくみ などが現れます。
これらが数日以上続く場合や、日常生活に支障を来すほどつらい場合は要注意です。
「ただの夏バテだろう」と自己判断せず、一度お医者さんに相談してください。
これらの症状が長引く場合、脱水症や熱中症に移行している可能性もあります。
たとえ症状が軽度でも、早めに受診してアドバイスを受けることで悪化を防げるでしょう。
無理をせず、「おかしいな」と感じたら遠慮なく受診することが大切です。
関連記事:日焼け後のケアはいつ何をするべき?正しい対処法とやってはいけないNGケア
オンラインメディカルクリニックでは夏バテの診察が可能
「病院に行くほどではないけど、夏バテがつらい…」「忙しくてクリニックに行く時間がない」という方には、オンライン診療の活用もおすすめです。
オンラインメディカルクリニックでは、夏バテのような体調不良についてもオンラインで医師に相談・診察してもらえます。
スマホやパソコンを使って自宅から気軽に医師に相談でき、必要に応じてお薬の処方を受けることも可能です。
オンライン診療では自宅にいながら専門家のアドバイスが得られるため、体力が落ちて外出が難しいときや、猛暑の中通院したくないときにも大変便利です。
忙しい方や遠方に住む方でも、自分に合った治療を継続しやすい方法といえるでしょう。
ただしオンライン診療もれっきとした医療行為のため、症状が重いと判断された場合は対面での受診を勧められる可能性があります。
明らかな脱水症状や酷い脱力感がある場合は迷わず救急を受診してください。
まとめ
日本の夏に多い「夏バテ」は、暑さによる自律神経の乱れや栄養不足で生じる体調不良です。
即座に治す特効薬はありませんが、栄養補給・水分補給と休養によって徐々に回復させられます。
最近ではオンライン診療で自宅から相談することも可能なため、状況に応じて活用しつつ、しっかりケアをしていきましょう。
監修医
島村泰輝
- 2012年3月 名古屋市立大学医学部 卒業
- 2014年4月 名古屋市立大学放射線科 入職
- 2015年4月 名古屋市立大学大学院博士課程入学 (専攻:生体防御・総合医学分野)
- 2019年3月 同大学院卒業、博士号取得
- 2019年6月 株式会社エムネス 入職
- 2022年10月 同 Medical Professional Service(医師部門)副本部長
- 2023年7月 オンラインメディカルクリニック開業
愛知県名古屋市出身。遠隔放射線画像診断を行う傍ら、AI開発、メディカル用プロダクト開発を行う。
医療としてはその他にも内科診療、訪問診療にも従事。医療はITでさらに良くなる事を信条として様々な取り組みを行う。
物理的、時間的に医療が届きにくい層に対して医療を届けるべくオンライン診療を中心としたクリニックを開業。今後は各種専門家とともに、遠隔地であっても質の高い医療を提供するサービスを構築していく。